代理出産のリアルを見る…ドキュメンタリー映画『Made in Boise』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:アメリカ(2019年)
日本では劇場未公開
監督:ベス・アーラ
めいどいんぼいし
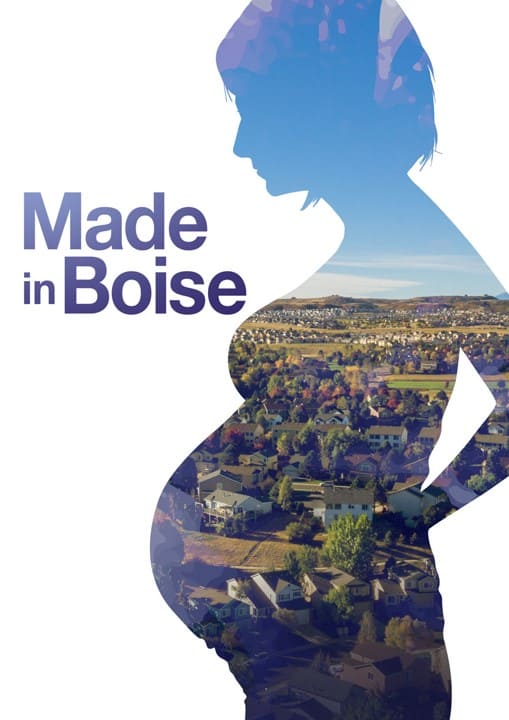
『Made in Boise』簡単紹介
『Made in Boise』感想(ネタバレなし)
実際の代理出産を知っていますか?
「代理出産(surrogacy)」というものがあります。
一般的に出産とは、男性と女性がいて、たいていは夫婦やカップルであることが多く、その二者の精子と卵子からなる受精卵によって、片方の女性が妊娠し、分娩に至ります。そのため、二者の遺伝子を受け継いだ赤ん坊が産まれます。俗にいう「血をわけた子」というわけです。
しかし、全く自身と血縁の関係にない子を産むことも、現代の医療技術では可能になっています。「体外受精(IVF)」を利用した妊娠です。
その体外受精の中でも、自分の卵子も用いず、パートナーの精子を用いるわけでもない、完全に赤の他人の子を妊娠し、自身で産む行為…それが代理出産です。
代理出産は、代理出産を依頼するクライアント…この人は後にその赤ん坊の親となるので英語では「Intended Parent(IP;複数形ではIPs)」と呼ばれます…そして代理出産として妊娠することになる「代理母(surrogate)」…この二者の合意によって成り立ちます。
代理出産には、対価として支払いを受ける「商業的な代理出産」もあれば、そうではない代理出産もあります。
これらの代理出産は国によって法的な扱いがまちまちです。代理出産を一切禁止(違法)とする国もあれば、商業的代理出産ではないものであれば認めるという国もあったり、商業的代理出産も全て認める(合法)とする国もあったり、はたまた法律の規定がなくあやふやになっている国もあります。現在の日本では代理出産に関する法整備が整っておらず、日本産科婦人科学会が該当の医療行為を行うことを認めていないので、表向きは不可能になっていますが、一部でわずかに実施例があります(朝日新聞)。宗教や政治的背景で代理出産が禁止されることもよくあります(The Advocate)。中絶の禁止の流れで、体外受精も禁止する動きもあります(LGBTQ Nation)。
一方、ネット上ではこの代理出産について厳しい反対意見が相次ぎ、是非の考察合戦は白熱して喧喧囂囂な論争に発展することもしばしばです。その中には代理出産に関して「女性の搾取である」「人身売買と同じだ」といったセンセーショナルな発言も目立ちます(Star Observer)。さらには「代理出産が助長される」という理論を持ち出して「LGBTQの権利運動」を批判しようという主張も観察されます。代理出産に関するデマや陰謀論も流れることも起きています(Snopes)。
しかし、こうしたネット上の血気盛んな論争を見渡しても、そもそも「代理出産とは何か」という実像が見えてきません。多くは「自分の頭の中にある代理出産の勝手なイメージ」で語っているだけで、現実の代理出産でどんなことが行われているのか、そのリアルは知られていないのが現状でしょう。
代理出産に激しく反対する人が思い浮かべるのは、ドラマ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』で描かれたような、残忍な搾取的出産でしょうか。確かにあれは代理出産を極めて悪魔儀式的に描いたような表象でした。
もちろん実際の代理出産があんなわけはないのは普通にわかると思うのですが(『ハンドメイズ・テイル』のあれは代理出産ではなくレイプです)、例えばもう少し現実感のある作品だと2024年にドラマ化されもした日本の『燕は戻ってこない』も代理出産を題材に扱っています。しかし、こうした作品の描写は代理出産を本当にリアルに描いているのでしょうか。それとも単に代理出産を都合よく誇張しているだけなのでしょうか。なかなかフィクションの影響力とは強いもので、しかも身近に代理出産が存在しない日本みたいな国で生きているとなおさら真実を知る機会など皆無に等しいです。
そんな中、代理出産のリアルを教えてくれるドキュメンタリー映画があります。
それが本作『Made in Boise』です。
代理出産を主題にしたドキュメンタリーは、他にも「BBC」製作の『The Surrogates』(2021年)などがあるのですが、本作『Made in Boise』はアメリカの「公共放送サービス(PBS)」の製作で、2019年の『Independent Lens』というドキュメンタリー・シリーズのひとつとして放送されました。
アメリカのアイダホ州の州都であるボイシ(ボイジー)を舞台にしており、そこで運営している代理出産事業団体を主な取材対象とし、その中で代理出産に関わる4人の代理母とその親志望者にカメラが密着しています。代理出産の事前交渉から、診断、体外受精、出産に至るまで、プロセスの大部分を映像におさめており、本作を観れば、代理出産の流れがわかります。それだけでなく、当事者がどのような心境でこの代理出産に向き合っているのかもじっくり伝わってくるでしょう。
『Made in Boise』を監督するのは、フィリピン系アメリカ人の”ベス・アーラ”で、2005年に誤解されがちなトゥレット症候群の子どもたちに光をあてたドキュメンタリー『I Have Tourette’s but Tourette’s Doesn’t Have Me』を手がけて高評価を得ています。
”ベス・アーラ”監督が代理出産の題材に関心を持ったきっかけは、大学時代の親友から代理母になってくれないかと持ちかけられた経験だそうです(American Film Institute)。その親友は不妊症に悩んでいて、幾度となく流産を経て、結局は無事に妊娠&出産できたそうで、”ベス・アーラ”監督が代理母になることはなかったそうですが…。
プロデューサーには、女性警察官の目を通してジェンダーや人種が交差する社会を映した『Women in Blue』(2021年)を手がけた”ベス・レヴィソン”が関わっています。
代理出産に興味がないという人でも、もしかしたら身近に代理母になる人が現れるかもですし、代理出産を出自ルーツに持つ人と出会うかもしれません。そのとき、やっぱり最低限の正しい認識は持っておきたいものです。
『Made in Boise』は、代理出産に賛成する作品でも反対する作品でもなく、現実を映し出す一作です。その映像は、そこらへんの粗末な議論もどきの切れ端よりは有意義ではないでしょうか。
『Made in Boise』を観る前のQ&A
オススメ度のチェック
| ひとり | :主題に関心あれば |
| 友人 | :学び合いながら |
| 恋人 | :互いに率直に語り合って |
| キッズ | :社会勉強に |
『Made in Boise』予告動画
『Made in Boise』感想/考察(ネタバレあり)
世間のイメージ以上に複雑なプロセス

ここから『Made in Boise』のネタバレありの感想本文です。
最初に留意事項として代理出産は各国で法規制が違うので、『Made in Boise』はあくまでアメリカの事例を紹介しています。加えて、アメリカでも州によって法規制は異なっており、作中で説明されるとおり、本作の舞台であるアイダホ州は代理出産を規定した法律がないです。
だからといって好き放題にやっているわけでは当然なく、相当にロジスティックで複雑なプロセスのもと慎重かつ入念に進められていました。本作では「A Host of Possibilities」という代理出産事業団体が中心に映し出されますが、こういう専門の仲介がないととうてい進行できないほどに面倒な流れがあります。
つまり、まずここで明らかになるのは「代理出産は手軽に実施できない」という事実です。
最初に「代理母の用意」という重要なステップがあります。誰でも代理母になれるわけではなく、スクリーニングが行われます。それはアメリカ生殖医学会のガイドラインに基づいて判断され、代理母の年齢は21歳から44歳までで、心身ともに問題なく、健康な出産経験がないといけません。そのための専門家の診断が必須です。
なので、代理母になる人はすでに子ども(こちらは実際に自分の血をわけた子)がいます。人生初妊娠が代理出産ということにはなりません。
作中で代理母になるチェルシー・フレイ、ニコール・ウィリアムソン、シンディ・フロイド、サミー・ディアスの4人は、それぞれ家庭の経済状況は違います。基本的に中産階級で、ネイリストのサミーが一番労働者階級に近い人物でした。極貧な人はたぶん参加は事実上難しいんじゃないかなと思います(ただでさえ医療福祉の整っていないアメリカにおいてそういう人は適切な診断を経た出産経験がないことが多いだろうし)。犯罪歴も調べられるようです。
一方で、代理出産に対するネガティブなイメージの元凶となった「ベイビーM事件」が本作でも取り上げられます。これは1986年に起きた事件で、ある代理母となった女性が赤ん坊の受け渡しを拒み、代理出産の有効性を問うアメリカ初の裁判となった親権訴訟でした。センセーショナルに報道されたことで、世間の代理出産の印象は「代理母が可哀想」という方向に傾きました。
こうした事態を防ぐためにも、作中では細心の注意を払って交渉が行われ、代理母と親志望者(IP)の間では双方の弁護士と中立なパラリーガルを挟んでの、綿密な契約合意が行われる過程も映し出されます。
それ以外にも、代理出産コーディネーターが常時サポートしていたり、セントルークス・ボイシ・メディカルセンターのような信頼できる医療体制があったり、代理母同士の月イチの集会で支え合ったりと、代理出産のシステムがオープンに広がっていました。
印象的なのは、弁護士すらも含めてほぼ女性で成り立たせていること。「女性の身体は女性が決める」という強い誇りと意志を感じさせる体制でした。
「A Host of Possibilities」の雰囲気が『コール・ジェーン 女性たちの秘密の電話』で描かれたような女性運営の中絶支援団体に近しいものを感じたのも、そういう理由からかな。
代理出産を依頼する親志望者の事情
一方で、需要という点でこちらも欠かせないのが、代理母を求める親志望者(IP)。本作『Made in Boise』では、スペインのマドリードから依頼してきたエルネスト、スペインのグラナドから依頼してきたジュリアン、はたまたシャノン・レイナー、さらにはデビッド・ツォンとトッド・カーゾンのカップルと、前述した代理母4人に対応する4者が映し出されます。
この親志望者(IP)も世間に誤解されやすい立場にいます。
それぞれに人生の事情があり、不妊症や不育症に悩み続けてきた女性もいれば、同性愛カップルもいれば、独身男性もいます。共通するのは「子どもが欲しい」と強く願っていることですが、たぶんこの人たちは周囲からこの質問をしょっちゅう受けてきたのでしょう。
「なぜ代理出産なの?」と…。
別に代理出産ありきですぐさま依頼してきたわけではないことは本作を観ていると、当人の口から語られます。
不妊を解消するためにあらゆる治療を試してきて、それでも全然ダメで、自己嫌悪と絶望を感じながら、代理出産に辿り着いたシャノン。また、デビッド&トッドからはそもそも「子を持つ」という選択肢が男性同士カップルにも制度的に平等に開かれているわけではないという社会のジェンダー認識の現実も…。さらに、エルネストからは、養子も当然のように検討したものの、そもそも養子制度は独身男性を門前払いするという恋愛伴侶規範的な厳しい壁が浮き彫りになり…。
いずれもマジョリティが当たり前に有している「子を持つ機会」を与えられていない人たちです。
本作で映し出される4者の親志望者(IP)は、最後の手段としてこの「A Host of Possibilities」に駆け込んでいるのでした。「A Host of Possibilities」では親志望者(IP)の多くが海外からのクライアントで、数少ない受け皿になっている現状がわかります。
なぜ代理母になるのか?
そして親志望者(IP)以上に代理母の存在がやはり最大の鍵です。繰り返しになりますが『Made in Boise』で映し出されるのは、チェルシー・フレイ、ニコール・ウィリアムソン、シンディ・フロイド、サミー・ディアスの4人。
おそらくこの代理母の人たちもこの質問を嫌になるほどぶつけられてきたでしょう。
「なぜわざわざ代理母になんてなったの?」と…。
でもその質問は逆説的に向けられるべき問いなのかもしれません。「なぜ自分の血をわけた子を産むのが当然だと思っているの?」と…。
人は2人目以降の子どもを持とうと思ったとき、当然「自分の血をわけた子」を産むものだという思考が真っ先に浮かびます。でも、作中の人物はそうじゃなかったんですね。「他人の子を産む」という選択肢をとった。それだけです。
作中の代理母たちはみんな子だくさんで、養子さえとっている人までいて、出産や育児にそんなに抵抗はない様子でした。無論、代理出産を強要される圧力は微塵もないです。
言うまでもなく出産にはリスクはあります。でも代理出産特有のリスクとして突出したものがあるわけでもないです。ならば子を産むなら「自分の子か」「他人の子か」…その選択が最終的には要になります。
困っている人を助けたいという慈善動機で代理出産に関わり、そこに喜びを感じる代理母もいます。代理母の人は1回やると2回目、3回目と繰り返す人も珍しくないらしく、”ハマる”だけのやりがいがあるのでしょう。ニコールなんて自分も代理出産をしながら「A Host of Possibilities」のCEOとして運営に全力で、28週目の妊娠後期に突入しながらもバリバリ働き、分娩後5週間後には職場で働きまくり、自他の出産尽くしのキャリア生活を送っていました。その姿は決して「産む機械」なんて形容できるものではありませんでした。
また、自分で自身の子を産むよりも経済的負担が少ないので代理出産をするという代理母もいます。世間の先入観でありがちな「経済的に困窮しているから代理母になる」というケースは前述したとおり、そもそもの代理母になるハードルの高さから難しいのだろうなとも作中からは感じました。ちなみに別の研究によれば、アメリカの代理母は基本的に中程度の社会経済的地位と平均以上の収入があり、貧困が理由で代理母になっているわけではないと統計分析されています(RBMO)。
決して代理母は「出産を賛美する」もしくは「出産の辛さをものともしない」スーパーウーマンな妊婦ではないです。作中で映し出されるとおり、一般的な妊婦と同じような不安や苦悩を抱える姿もあります。出産を無事に終えられるか、こればかりはわからないですから。作中では帝王切開となる人もいました。完璧な生殖理想主義者なんかではない代理母の心の内がよく見えるドキュメンタリーでした。
同時に、その代理母の心境に寄り添ってくれる、夫や親、子、友人といった存在の大きさも実感できました。作中に映る人たちはみんな頼もしい支援者で、そうやって見ている限りだと、本作の代理母は一般的な妊婦よりもはるかに充実した妊婦ケア環境にある感じでしたね。精神的健康状態は一般的な妊産婦死亡の主な原因ですから(約23%;Psychiatric News)、メンタルケアは本当に大事です。
これは私の勝手な推測ですけど、代理母当事者が代理出産事業団体を運営するケースは結構あるみたいで、その理由を考えてみると、やっぱり代理出産への偏見が社会に根深くあるというのもあり、当事者運営じゃないと安心できないというのもあるんじゃないかなと思います。
新しい家族のかたち
日本語では「”代理”出産」という言い方になっていますが、「代理」という言葉はミスマッチだなと『Made in Boise』を観て思ったりもしました。
というのも、「代理」だとどうもよそよそしく事務的な作業っぽさがでますが、実際の代理出産の現場ではそんなことは起こってないからです。代理母が親志望者(IP)に赤ん坊を渡したら「はい、おしまい」と切り捨てられるわけではありません。出会い系マッチングアプリのような気楽さで成り立ってもいません。
むしろ代理母と親志望者(IP)は、いかにしてエモーショナルなリレーションシップを構築できるか…そこが試されていました。これは一生続く関係性です。恋愛でも性愛でもない、特別な関係性を築かないといけないのです。
だからしょっちゅうビデオ通話したり、診察に一緒に立ち会ったり、出産も当然現場に居合わせたり、とにかく親密です。出産以降も両者の関係は永続し、また代理出産をしたりする場合もあったり…。家族なんですね。従来の家族の概念に当てはまらないかもしれないけど、間違いなく家族。
作中ではこれを「ニューノーマル」と表現していましたが、私は非常にポリアモリー的というか、クローバーファミリー的な実践だなと感じました。「妊娠・出産は家族制度と血縁で成り立たせるべし」という規範に真っ向から挑む、アナーキズムな取り組みともいうべきか。代理母だけでなく親志望者(IP)も同じで、作中でもある独身の親志望者男性は普通に友人男性と赤ん坊を育てていたり、もう育児自体だって従来の婚姻制度を超えた実践をしていて…。
代理出産の数は増加傾向にありますが、それは潜在的な需要に答えられていなかったぶん、今は事業団体の登場でそこにアクセスしやすくなり、顕在化しているのだと思います。
ただ、それだけでなく、代理出産の存在は私たちの社会に「妊娠・出産とはどうあるべきですか?」という将来的な問いかけをするものでもあるなと感じました。
生殖に関する医療技術はどんどん進化しています。代理出産はその問いかけの始まりにすぎないかもしれませんね。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
△(平凡)
関連作品紹介
出産・育児に関するドキュメンタリーの感想記事です。
・『ぜんぶ売女よりマシ』
・『一人っ子の国』
作品ポスター・画像 (C)PBS メイド・イン・ボイシ
以上、『Made in Boise』の感想でした。
Made in Boise (2019) [Japanese Review] 『Made in Boise』考察・評価レビュー
#医療 #育児 #出産



