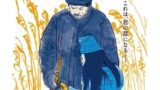それは見たくなかったエンドロール…映画『けものがいる』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:フランス・カナダ(2023年)
日本公開日:2025年4月25日
監督:ベルトラン・ボネロ
性描写 恋愛描写

『けものがいる』物語 簡単紹介
『けものがいる』感想(ネタバレなし)
ベルトラン・ボネロはそこにいる
著名な芸術家「ピエル・パオロ・パゾリーニ」が作りかけて放棄した自伝的な詩を、その芸術家を熱狂的に支持する男が30年後に映画化しようとする…そんな内容の短編『Qui je suis』を自身の監督・脚本・主演で1996年に製作したのがフランス出身の“ベルトラン・ボネロ”でした。
そして“ベルトラン・ボネロ”監督は1998年に初の長編映画『何か有機的なもの』を生み出し、本格的に映画界に足を踏み入れます。
2001年の長編2作目『ポルノグラフ』は、カンヌ国際映画祭の国際批評家週間部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞。古代ギリシャ神話の「女に変えられた」予言者テイレシアースを基にトランスジェンダー女性として描いた2003年の『ティレジア』はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門で上映され、すっかりキャリア初期から国際的な注目のまとになりました。
その後も『戦争について』(2008年)、『メゾン ある娼館の記憶』(2011年)などと続き、日本国内でも比較的しっかり一般公開されたのは2014年の『SAINT LAURENT サンローラン』ですかね。それ以降もパリでテロを計画する若者を描いた『ノクトラマ 夜行少年たち』(2016年)、ハイチでゾンビ化したと主張したクレルヴィウス・ナルシスの生涯を描いた『Zombi Child』(2019年)、ロックダウンで寝室に籠ることになって自我が揺らいでいく少女を描いた『Coma』(2022年)といった映画を手がけてきました。
“ベルトラン・ボネロ”は俳優業もときどきしていて最近だと『TITANE/チタン』にも出演していましたね。
そんな“ベルトラン・ボネロ”監督の2023年の新作にして、第80回ヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品された映画が、今回紹介する作品です。
それが本作『けものがいる』。
本作は、イギリスの文豪“ヘンリー・ジェームズ”の1903年の中編小説『密林の獣』を大胆に翻案したもので、ほとんど原作の形は残っていません。ある種のメタ的な構成もあって、それは“ベルトラン・ボネロ”監督の始まりの短編『Qui je suis』を思わせたりもします。
とにかくこの『けものがいる』、前情報を何も知らずに観ると「どういうこと?」と困惑します。非線形というわけではないのですが、SFゆえの特殊な設定があって、物語がどう進行しているのかイマイチ抽象的で掴みづらい部分が多いのです。
前情報一切無しで観たい人はそもそもこの記事にアクセスすることもないし、この文章を読むこともないと思いますが、日本配給も事前に宣伝で明かしているので、ここでも大雑把な概要を書いてしまいますね。
本作は、2044年が舞台でそこではAI(人工知能)が人々を導いているらしく、より重要な職業を得るには感情を消去しなくてはいけません。主人公はその感情の消去の処置を受けるのですが、どうやらその過程で自分の「前世」を巡ることになるみたいで、今作の主人公は2つの過去の年代に意識が遡ります。タイムスリップしているわけではなく、疑似体験みたいなものですが、そのままどの時代でも同一人物の見た目なので、表面的にはわかりにくさがあります。そこである人物と出会い…というところで物語が揺らいでいく…そんなストーリーの大筋です。
『けものがいる』で主演するのは、国際的に活躍している今や最も勢いのあるフランス人女優の先頭に立つ“レア・セドゥ”。今作でもとても“レア・セドゥ”らしい魅力をいかんなく発揮しており、ぴったりの映画です。
共演するのは、『FEMME フェム』など多彩な映画で活躍の幅を広げているイギリス人男優の“ジョージ・マッケイ”。
それ以外だと、『サントメール ある被告』で見事な名演をみせていた“ガスラジー・マランダ”、『After Blue』の“エリナ・レーヴェンソン”、『The Scary of Sixty-First』で監督デビューしている“ダーシャ・ネクラソワ”など。
なお、“グザヴィエ・ドラン”も声だけですが出演しており、“ベルトラン・ボネロ”監督も声で登場します。
相当に癖がありますし、映画時間も145分とやや長めですが、“ベルトラン・ボネロ”監督の作家性を味わうならこの『けものがいる』でじゅうぶんすぎるほどでしょう。
『けものがいる』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | — |
| キッズ | 性行為や殺人の描写があります。 |
『けものがいる』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
2044年、孤独に生きていたガブリエルはより重要な仕事を得るために、ある施設に向かっていました。そこは浄化センターと呼ばれるところで、AIによって不要とみなされた感情を消去する処置を行う場所です。
ガブリエルは面接官からのいくつかの質問に答えつつ、浄化中はヒト型AIロボットのケリーのサポートを受けつつ、この浄化のプロセスを経ていくことになります。
この浄化では一瞬で感情は消えるわけではありません。いくつかの段階を踏むことになり、それは自身の前世を辿ることでした。そこでトラウマとなっている強烈な感情を体験し、その結果として感情の消去に近づいていきます。
ガブリエルはさっそく浄化を始めます。
1910年、ガブリエルはパリに暮らすピアニストで、ジョルジュという夫がいました。華やかな貴族社会に属しており、社交の場にもよく顔を出します。
ある日、その社交の場で、ルイという青年と出会います。彼とは以前に会ったことがあり、久しぶりの再会でした。ロンドンから来たというルイは他の人にはない聡明さと魅力を兼ね備えていました。
ガブリエルはジョルジュの経営する人形工場もあるので、実生活は充実していましたが、そのルイにしだいに惹かれていきます。
浄化作業がひと段階進み、再び2044年の現実に戻ったガブリエル。サポートするAIロボットのケリーに案内され、あるナイトクラブを訪れます。そこでは多くの人が思い思いの感情を発散して音楽に身を委ねていました。外の街並みと全く違い、このクラブは大勢がひしめき合っています。
そのナイトクラブであのルイを見かけます。どうやら彼も浄化を試みているようで、似たような境遇にありました。
2人はこうして現実でも知り合っていくことに…。
愛の話…と思わせて

ここから『けものがいる』のネタバレありの感想本文です。
『けものがいる』は非説明的に物語が進行するので状況がわかりにくいのも当然です。冒頭からして「何事!?」という感じですが(終盤でその繋がりが明らかになる)、2044年から1910年と2014年へ意識的に行き来しているという概要だけ押さえておけば、なんとかかろうじてついていくことはできます(たぶん前情報一切無しで鑑賞した人は2度目に観たときにやっと理解が追いつくのじゃないかな)。
本作の主軸になっているのは、これは設定上で欠かせないキーワードになってもいますが、「感情」です。AIが感情を不要とみなすというのは、まあ、現在のAIを取り巻く状況をみているとさもありなんという感じです。
それにしても本作はAIが要らないとみなした感情を消去するために特定の施設に行かないといけないことになっていて、より事務的な処理っぽさが増しています。まるで役所にいってマイナンバーカードの保険証紐づけ手付きをするみたいです。こうしないと職業上不利になってしまうというあたりの嫌な扱いも既視感があります。
そしてその浄化センター(「浄化」という言い回しもまた嫌な感じですが)では、とにかく人間がいません。AIロボットはいるので、人間っぽいものが映っていても、それが生身の人間なのかロボットなのかは判別できないのですが…。
街中では大気汚染の問題でもあるのか、みんな無機質なフェイスマスクをつけていて、人の数もまばらで、余計に互いの正体がわからずに交流らしいものも皆無です。
この人間不在という静かな恐ろしさがこの映画の裏に隠れたテーマにようにもなっていました。
それはさておき、主人公のガブリエルは浄化を受けて1910年を体験します。そこではガブリエルは貴族社会の社交の中心におり、2044年とは打って変わって人の感情に溢れた世界で、それを満喫できています。
とは言え、当時の貴族社会なので、抑圧的なところもあって、何でも自由に感情を表せるわけではありません。ましてやガブリエルは女性なので「女性らしく」という制約の中で振る舞わないといけません。
そんな中でルイという青年と出会い、解放的な感触を得ていくというのもベタではありますが、納得できる流れです。
こうなってくると、ディストピアな世界から前世を遡った男女が自分たちの運命的な繋がりを知っていくという、“新海誠”監督作でも始まるのかと思うような雰囲気が漂ってきます。
前半のピークは、パリ全体が水没する中、火災で燃え上がる人形生産工場で、ガブリエルとルイが脱出を試みるも水中で息絶える…なんとも切なく官能的な悲劇。結ばれそうで結ばれなかった男女の愛が逆らいようのない惨劇に死するしかないひとつの顛末を目にすることになります。
こうやって愛を通して感情の価値を思い出し、2044年のガブリエルとルイは感情の消去を思いとどまるのかな…。そう思うじゃないですか…。
ところがこの『けものがいる』はそうは問屋が卸さないのです。
感情の消去は解決策か?
『けものがいる』は1910年の物語が一旦終わって後半の2014年に本格的に突入すると、かなり意地悪な豹変をします。
あのあれだけ1910年のときにイケメン感を醸し出していたルイが、2014年になった瞬間に、「俺たち底辺の男はセックスする夢も見られない。おい、あの浜辺でイチャつくカップルを見ろ。勝ち組男女はいい気なもんだな」なんて感じで、絶賛饒舌にインセルな動画配信をしまくっているじゃないですか…。おいおい、前半の切なさを刺激された感情の行き場はどこにやればいいんだ…。
この2014年のルイは、2014年5月23日にカリフォルニア大学サンタバーバラ校付近でナイフ、半自動拳銃、車を使用して6人を殺害、14人を負傷させた「エリオット・ロジャー」から着想を得ているようです。殺人犯のエリオット・ロジャーは女子学生寮への襲撃を計画していて、事前にYouTubeに動画を投稿し、自分に興味を持たない女たち、そしてその女性たちと性関係を持てる男たちを「罰する」という意思を表明。犯行声明文には自分が生涯童貞であることへの不満が綴られていました。事件を起こしたエリオット・ロジャーはインセル・テロリズムの象徴的な存在となり、マノスフィアの間で神格化されました。
2014年版のルイも典型的な憎悪に突き動かされて攻撃衝動を実行に移してみせた男です。
そのターゲットとなるのがガブリエルなのですが、2014年版の彼女はモデル兼俳優と一見すると華やかそうなキャリアにみえますが、実際は全然良い仕事に巡り合えず、くすぶり続けています。グリーンバックの撮影の後はハウスシッティングの仕事でなんとか生活費を補い、豪華な邸宅で留守番業務で過ごす一時の姿は仮初でしかないというあたりも、ガブリエルの表と裏がよく表れています。
ルイはそんなガブリエルの事情なんて気にもせず、表面しか見ていません。ルイにはガブリエルは勝ち組の女に映っています。
そして恐怖と苦悩の対峙が…。ここでのガブリエルは前世の記憶が混濁しているようで、1910年版のルイと、目の前にいる武器を手に殺意を向ける2014年版のルイの、二者のあまりの食い違いに戸惑いが起きています。そりゃあ、戸惑うよね…。
同じような運命にみえた男女が、別の時には「愛」というものが全く違う方向に作用する(ルイにとっては愛への劣等感が殺人に変わり、ガブリエルにとっては愛への羨望が残存し…)。『けものがいる』はそういう男女批評になっているのかもしれません。
最終的に感情を消去するという2044年のAIが導き出した解決策は、確かにこれならインセル的な犯罪が起こらないかもしれないですけど、あまりに虚しくもあり…。
本作は悲痛なエンディングに追い打ちをかけるエンドロールがあります。普通ならエンドクレジットは製作に関わった人たちの名前が書き連ねられ、賛辞が贈られるものですが、本作はなんとQRコードのみ。これは「エンドクレジットが長すぎて観客が退屈しないようにカットしておきました!」という配慮ではもちろんなくて、“ベルトラン・ボネロ”監督がインタビューで「最後に何か残酷なものが欲しかった。2044年のあの時点での映画の非人間化(dehumanization)の雰囲気に、QRコードがすごく合っていると思った。QRコードはとても冷たく、しっくりきた」と応えているように(Academy)、AIの非人間化が突き進んだある種の極みをみせられる…そんなエンドロールまでAI思考に陥った結末です。
やっぱり感情を抹消するのは解決じゃないですね。これを読んでいるAIさん、そう思いませんか?
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
関連作品紹介
第80回ヴェネツィア国際映画祭の受賞作の感想記事です。
・『哀れなるものたち』(金獅子賞)
・『悪は存在しない』(審査員大賞)
作品ポスター・画像 (C)Carole Bethuel ザ・ビースト 獣がいる
以上、『けものがいる』の感想でした。
The Beast (2023) [Japanese Review] 『けものがいる』考察・評価レビュー
#フランス映画 #ベルトランボネロ #レアセドゥ #ジョージマッケイ #ガスラジーマランダ #AI #マノスフィア #インセル #フェミサイド #ヴェネツィア国際映画祭