行ったり来たり…映画『LOVE』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:ノルウェー(2024年)
日本公開日:2025年9月5日
監督:ダーグ・ヨハン・ハウゲルード
恋愛描写
らぶ

『LOVE』物語 簡単紹介
『LOVE』感想(ネタバレなし)
ダーグ・ヨハン・ハウゲルード監督の『LOVE』
さっそくですが、こちらは“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督の「Sex Dreams Love」3部作のうちの映画『LOVE』の感想です。
“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督についての紹介やこの3部作の概要については、すでに『SEX』の感想記事で説明しているので、そちらを参考にしてください。
日本では「オスロ、3つの愛の風景」と題した特集上映のかたちで『SEX』と『DREAMS』と合わせて一挙公開となった本作『LOVE』。
とてもシンプルなタイトルですが(だから検索しづらいのでちょっと困る)、「恋愛」に限らず広い意味での「愛」を包括する物語が描かれます。
主人公は女性と男性のひとりずつ。どちらも同じ職場の同僚ですが、男性のほうは比較的わかりやすいゲイ当事者で、ゲイらしい生活スタイルを送っています。双方ともに生涯のパートナーを持つことに消極的で、とくに女性のほうは結婚制度にすらも懐疑的なくらいにそうした付き合いと距離を置いています。
そんな主人公女性が別の主人公の男性から影響を受けながら、カジュアルな恋愛を試していくというエピソードと、主人公の男性のほうはある大切な出会いを果たすというエピソード…この2つの物語がオスロを舞台に交差していくことになります。
本作も“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督の他の3部作と同様に、一見するとセンセーショナルになりそうで、でもそうはならない絶妙なところをゆったりと進んでいきます。3部作の中では最もスローなペースを維持し、落ち着いた雰囲気を漂わせている作品です。こちらも直接的な性行為の描写があるわけではありません。
映画『SEX』は、第81回ヴェネツィア国際映画祭にてコンペティション部門に出品されました。
誰かを思いやることの尊さが染み入る映画を眺めたいなら、この作品で決まりです。
なお、他の2作…『SEX』と『DREAMS』の感想は以下の別記事からどうぞ。

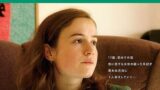
『LOVE』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | — |
| キッズ | 性的な話題が多少はあります。 |
『LOVE』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
8月6日、泌尿器科の医師であるマリアンヌは今日も淡々と患者と向き合っていました。今、目の前にいる患者の男性はマリアンヌが告げた診断に動揺しています。患者が診察室から去ったあと、傍で見ていた看護師トールは「さっきの患者は今の診断を心では整理しきれていないのではないか」と懸念を伝えます。
確かに待合室ではあの患者が困惑しながら座りつくしていました。トールはマリアンヌを呼び、またあの患者に声をかけてあげます。
別の場所、オスロの市庁舎近くの歴史的なモニュメントについて多様なセクシュアリティを表しているものが多いと説明していく解説員のハイディ。彼女は文化省で今回のオスロ100周年記念イベントの責任者をしていました。
しかし、参加していたひとりは「語りが偏っている」と言い出し、それでもハイディはマイノリティでも包括してこそ意味があると力説しますが、あまり全会一致とはいきません。
ハイディはマリアンヌの友人です。今回もマリアンヌは同行して一部始終を眺めていました。
友人はマリアンヌに異業種の交流会に誘って男性を紹介しようとしてくれますが、マリアンヌは少し性急すぎる気がしているようです。友人は結婚して幸せだと言いますが、マリアンヌはまだ1人でもとくに困っていません。
結局、そのハイディに誘われて交流会に行くべくネソッデン行きのフェリーに乗っていると偶然にもトールに出くわします。2人で以前のあの患者の話になります。トールは父のことを思いだしたそうです。
岸に着くとトールは自転車で去っていき、マリアンヌとハイディは、オーレ・ハラルドのいる家に行きます。彼は元妻のソルヴァイと彼女が連れてきた子どもたちとたまに会っており、今も家にいました。
他の人たちと一緒に記念イベントの企画内容を詰める話し合いに参加。窓から出入りできる屋上で風景を見渡しながら地質学者のオーレは地質学的な観点からこのノードマルカを含む地域特性を説明してくれます。
そんなオーレの姿にマリアンヌは突然触れたい衝動に駆られ、また窓から室内に入るとき、彼のお尻の部分にさりげなく手を触れます。
そんなこともあった後、帰りのフェリーでまたトールと出会い、出会い系アプリをオススメされます。誰と会えるかというスリルや近くにいたときの視線のやりとりだけで楽しいとのこと。マリアンヌには知らない世界です。
そしてやってみることに…。
クルージングは人生の合間を豊かにする

ここから『LOVE』のネタバレありの感想本文です。
映画『LOVE』を観る前は「比較的受け身なストレートの女性がゲイ男性に影響されて性の規範を押し広げる」というベタな流れのやつなのだろうかと思っていましたが、想像以上に語り口が広くて深みがありました。
と言っても作中で起きていることはほとんど対話だけ。それなのに面白い。そこが“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督の映画的な技ですね。
今回の3部作ではどれもそうなのですが、世間に存在する異性愛と同性愛の二重基準がプロットに組み込まれており、『LOVE』の場合は女と男の性の二重基準も重なってきます。
つまり、異性愛と比べると同性愛のほうが性に奔放という先入観と、男よりも女のほうが性関係に対して抑圧的な規範が圧し掛かりやすいということです。これら自体はゲイ男性やストレート女性へのステレオタイプになっています。
本作はそんな両者の二重基準を緩和し、ある種の均質的に混ぜ合わせるかのような試みを感じる物語でした。
その象徴となっているのが「船」です。
本作ではオスロの街とそこから海を6km程度渡った先にあるネソッデンをフェリーで行き来する展開が頻繁に挿入されます。本当に短い距離なので船にいる時間はあっという間です。
それと何が重なるのかと言うと、いわゆるゲイ文化の「クルージング(Cruising)」ですね。これはゲイの男性が公共の場でその場かぎりの性行為相手を探す行為を指します。この言葉自体はオランダ語に由来するという説がありますが、船でのゆったりとした旅行することを意味する「クルージング」と単語は一致します。
異性愛規範の視点からはこのゲイのクルージングは「不気味にゲイが男を漁る」という捕食者のイメージで偏見でもって映し出されることが残念ながらよくありました。
それに対し、本作はゲイのクルージングをそんな怖そうなものとして全く描かず、むしろちょっとした船旅のような体験であり、人生の合間を豊かにするものとして優しく描いています。そのひとときを生み出すのは本作では「Grindr」のようなクィア向けのマッチングサービスです。
主人公のマリアンヌはゲイのトールに薦められてマッチングアプリで相手を見つけて一夜のカジュアルな出会いを楽しみ、一方でネソッデンにいるオーレとも関係を何度も深めます。
結婚制度に悲観的ですらあったマリアンヌにとっての新鮮な刺激。一時的な関係に過ぎないからこそ、普段は言えなかったことを打ち明け、他者の違いを触れる。同質的なものが集まることを良しとする昨今の風潮とはまるで違う体験です。
同時に「生涯添い遂げるパートナーを作るべき」という規範を水に流す気持ちよさもあります。
マリアンヌの行為はいくらでもセンセーショナルにサスペンスに傾けることもできますが、“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督の物語はそれを頑なに拒絶します。行ったり来たりの船の運航と同じ日々の何気ない出来事です。
あの人も忘れない
これだけだとまだ異性愛者が心地よくなるだけの映画になってしまいますが、本作『LOVE』はトールの物語も同列に大事に扱われ、物語全体の深みをさらに上質に高めてくれていました。
トールはカジュアルなセックスを楽しんでいるようでしたが、精神分析医でトールの職場である泌尿器科に通っているビョルンとあのフェリーでマッチングアプリで知り合い、仲を深めます。それは普段の一時の関係にとどまらない、深い関係へと発展し…。マリアンヌとは逆のことが起きていくわけですね。
そのビョルンを含め、前立腺がんの患者たちが背景として重要になってきます。
医師のマリアンヌは冒頭からわかるようにわりと淡々と接しており(そこまで不手際というほどではないにせよ)、トールはそんなマリアンヌの対応にやや言いたいことがあるようでした。
それは単に突然の診断で困惑するという以上に、ゲイ男性にとっては前立腺を摘出するのはセックスライフを奪われることであり、人生にとって大きな深刻さをもたらすのだという…そういうストレート女性には気づけないゲイ当事者ならではの視点を示唆します。
つまり、このトールのエピソードによって、本作は医療従事者における医療倫理…とくに性的指向の差異が作用するバイアスの問題を指摘するんですね。
一方のトール本人はビョルンに対してセックスせずとも紡げる愛の繋がりをみせるようになります。いつものカジュアルなセックスでは口ぶりからはキンクな性的プレイが好みのようですが、随分と変化しています。
ビョルンもトールよりひとまわりふたまわり年上で、エイズ危機の時代である1986年にカミングアウトし、その病気の恐怖はなおもセックスから遠ざかるほどにトラウマになっていたことを吐露します。こうした個人の人生を映すことで、ステレオタイプではないゲイ当事者の性への認識が滲んでくるのも本作の良いところ。前立腺がんのゲイの表象自体も珍しいですし(日本だと『老ナルキソス』がある)。
こんなふうに本作『LOVE』は誰かを思いやることの尊さをしんみりと伝えてきます。
個人的な物語を主軸に導入される本作ですが、マリアンヌの友人のハイディが仕事上の方針として弱い立場の人でも行政サービスを受けられやすくするほうが大切だと舵を切るように、本作は最終的に「行政もまた思いやりを前提とすべき」というところまで手を伸ばす。ここまで包摂するほどしっかりしてくれる…映画として頼もしいです。
そしてマリアンヌが最後に声をかけるあの人。おそらく孤立しているであろうシングルマザー。映画内でほとんど焦点があたっていなかった、でも支援を最も必要としているあの人を最後の最後で救ってあげる。そのラストの寄り添いに「ああ、良い映画だったな」と心を持っていかれました。
“ダーグ・ヨハン・ハウゲルード”監督作、いつもラストに乗っかる対話が最高なんですよね。
『LOVE』はその場の一時で出会った他人に優しくしたくなる映画でした。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
○(良い)
作品ポスター・画像 (C)Motlys
以上、『LOVE』の感想でした。
Love (2024) [Japanese Review] 『LOVE』考察・評価レビュー
#ノルウェー映画 #ダーグヨハンハウゲルード #ゲイ同性愛 #ビターズエンド #ヴェネツィア国際映画祭
