映画のエンドクレジットを最後まで見るか、飛ばすかは、人それぞれだと思います。でもしっかり最後まで見ている人の中には、“これ”が気になったことはないでしょうか。
エンドクレジットの最後のあたり(どの税金控除を受けたかなどの表記の後くらい)で表示されるこんな感じの内容の文章。
「この映画を製作するにあたりいかなる動物も傷つけていません」
実際は英語で書かれているので、英語が読めないと気づかないかもしれませんが、多くのハリウッド映画ではこの内容の表記が観察できます。
たいていの人はこれを目にして、そのまま素直に受け取って、こう思うでしょう。
「ああ、確かに動物が映画内ででてきたけど、撮影では実際に動物が傷つけられたことはなかったんだな」と。
でもこれは誰がどんな基準で判断しているのでしょうか。映画鑑賞を趣味にしている人でも意外と知らない、この「動物を傷つけていません」のクレジットの意味と歴史を、今回の記事では整理しています。
「American Humane」とは?
ハリウッド映画のエンドクレジットで見られる「動物を傷つけていません」の表記。これは映画製作者が勝手に自認しているわけではありません。
この表記のすぐそばに「American Humane」と書かれたロゴがセットで表示されているのがわかると思います。英語で「No animals were harmed®」とも明記されているはずです。
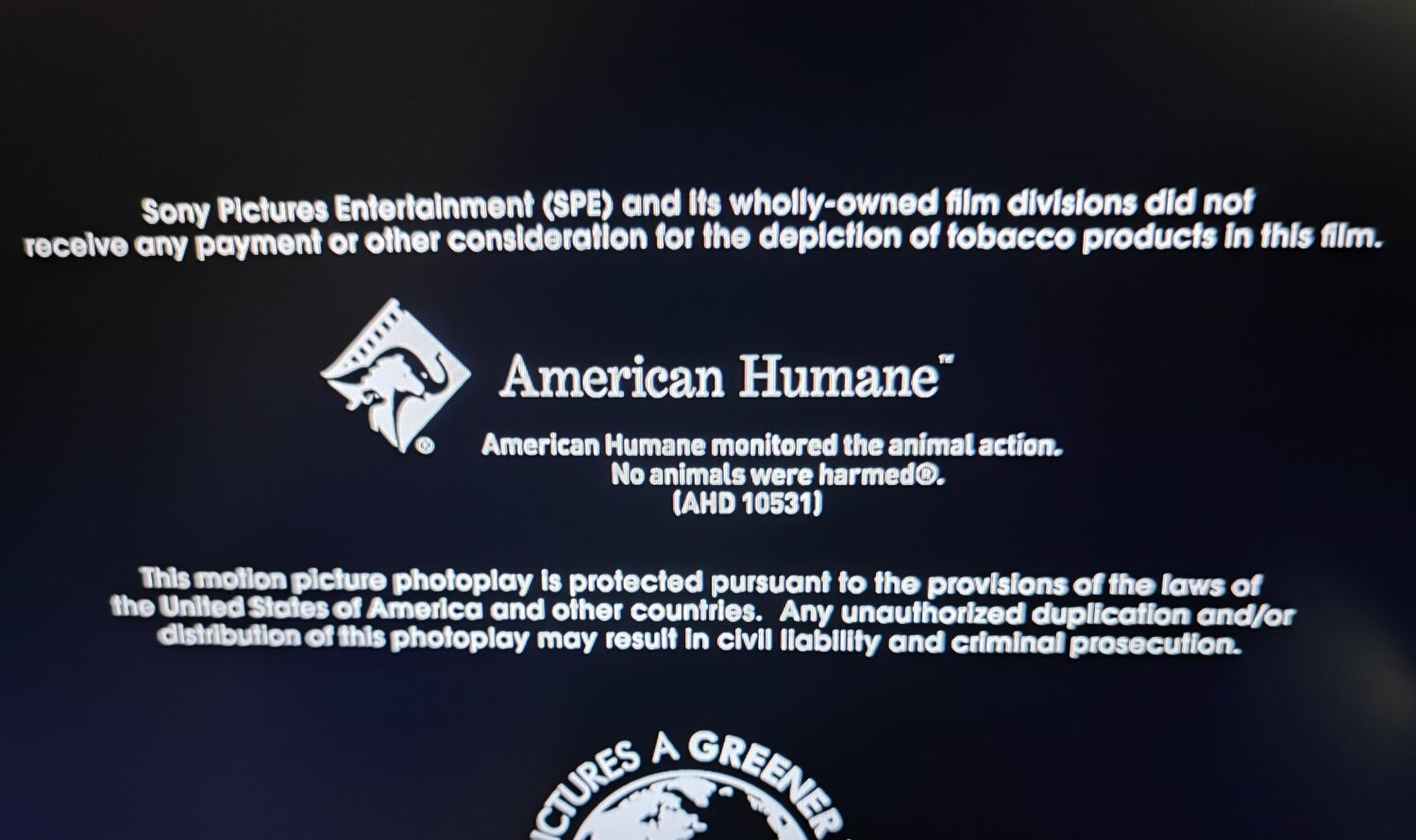
映画のエンドクレジットに表示される「American Humane」の「No animals were harmed」の表記(上記は『スパイダーマン ノー・ウェイ・ホーム』のもの)
実はこの「動物を傷つけていません」の表記は「American Humane」という組織による認証マークなのです。
「American Humane(アメリカ人道協会)」とは、1877年に設立された非営利組織で、当初は「International Humane Association」や「American Humane Association」という名称でした。
この「American Humane」は、映画やドラマで撮影で関わる動物を監視し、独自の厳格なガイドライン基準を満たす作品に「No Animals Were Harmed」とエンドクレジット認証を授与する独占的権利を持っています。
つまり、「American Humane」が「この映画の撮影では動物は傷つけられていないことを確認しました」と保証してくれているわけです。
ちなみに「American Humane」は動物だけを取り扱う組織ではなく、(人間の)児童保護なども対象範囲にしており、1890年代には学校での子どもへの体罰に反対する活動などを展開していました。
映画と動物の歴史
動物愛護運動の盛り上がり
では、この「American Humane」は一体いつから映画に対して「No Animals Were Harmed」という認証を始めたのでしょうか。
それを知るうえでまずはそもそもいつ頃から「動物愛護」という視点の活動が人間社会で定着したのか、その歴史から振り返ってみましょう。
本格的な「動物愛護」運動の誕生は、1800年代後半から1900年代前半に始まりました。これを理解するために同時に知っておくべきは、フェミニズム運動です。実は「動物愛護」運動とフェミニズムは切っても切れない関係性にあります(Active History)。
当時、第1波フェミニズムが巻き起こり、家庭に閉じ込められていた女性たちが平等を求めて声をあげ、参政権や選挙権などを訴えました。女性たちが政治社会やビジネスに意見する勢いが格段に増えたのですが、その中で多くの女性たちが今で言うところの「動物の福祉」や「動物の権利」に相当するような「動物愛護」を訴えるようにもなったのです。
例えば、“フランシス・パワー・コブ”という女性が中心となって1898年に生体解剖に反対するために設立したイギリスの組織「Cruelty Free International」、“リジー・リンド・アフ・ハーゲビー”らが1903年に設立した「Animal Defence and Anti-Vivisection Society」、“キャロライン・アール・ホワイト”によって1883年に設立された「American Anti-Vivisection Society」など…。また、1889年に創設された鳥類保護組織「Royal Society for the Protection of Birds」も“エミリー・ウィリアムソン”といった女性のグループがその起源にありますし、今や自然保護団体として巨大な規模となっている「全米オーデュボン協会」の組織化に貢献した「Massachusetts Audubon Society」は“ハリエット・ヘメンウェイ”が1896年の設立時に関与しています。他にもたくさんあり、全部はとても挙げきれません(In Defense of Animals)。
とにかく「動物愛護」は女性たちによって先導されていたのです。
動物を残酷に扱ってきた映画の黎明期
偶然ではあるのですが、映画の歴史も1895年のリュミエール兄弟に象徴されるように、この動物愛護の高まりと同時期に産声をあげました。
この映画の黎明期の時点からすでに、人間ばかりではなく、多彩な動物がたくさん出演していました。馬、牛、鳥、犬、猫、チンパンジー…。立派な映画の立役者です。
しかし、残念ながら、初期の映画は撮影現場で動物を死傷させることも珍しくなく、動物の扱いはときに残酷で、乱雑としていました。
動物を残虐に扱った最も初期の映画としてひとつ挙げるなら、1903年の“トーマス・エジソン”の『Electrocuting an Elephant』があります。これは74秒しかない映像ですが、当時ではこれも「映画」です。この映画は、コニーアイランド遊園地でのトプシーという名のゾウが感電死させられる瞬間を映像におさめたものです。『エジソンズ・ゲーム』という映画でも描かれたとおり、1880年代~1890年代の間は“トーマス・エジソン”は電気業界の覇権を握るべく、かなり乱暴な手段にもでていたのですが、その「電流戦争」から10年後でも『Electrocuting an Elephant』のような酷い行為が行われていたのです(ネットを探せば映像が見つかると思いますが、非常に残酷なのでこちらではリンクなどは紹介しません)。
ハリウッドの黄金期となった1920年代も撮影中に動物がそれも多数死亡した映画がいくつもあります。1925年の『ベン・ハー』では少なくとも100頭の馬が死亡し、1936年の『進め龍騎兵』ではトリップワイヤーで突撃する軍馬を大量に転ばせたことで25頭が亡くなったと言われています(The Week)。馬はとくにアクション・シーンが多いので、危険な撮影となっていました。

馬は初期の映画の撮影現場では過酷な目に遭いました。
始まりは、ひとつの映画から…
そんな動物虐待が常態化していた初期の映画界に「動物愛護」はどのように持ち込まれたのか。
1800年代後半の動物愛護はもっぱら医療における動物実験や狩猟による動物製品を批判の対象としていました。それが映画へと波及し、動物虐待防止の取り組みへと繋がったターニングポイントとなった映画があります。
それが1936年に公開された“ヘンリー・キング”監督の『地獄への道(Jesse James)』です。
この映画では終盤に馬が乗り手とともにかなりの高さの崖から水に真っ逆さまに落下して着水するシーンがあります。馬が空中に投げ出されている姿もハッキリ視認でき、テクニカラー作品だったこともあり、鮮明でした。馬は実際には死んでいないとの主張もありますが、結局のところ、真偽は不明です。
この『地獄への道』の馬のシーンは当時非常に論争となり、抗議の結果、「American Humane」が映画撮影現場で動物虐待が起きていないかを監視することになりました。ここからあの認証の原点が始まったのです。
この「American Humane」による動物虐待監視は、ヘイズ・コードと共に運用されていました。このヘイズ・コードは宗教保守の思想を反映し、映画の表現の自由が著しく制限された、今では検閲と評価されるような代物だったわけですが、一応は動物虐待防止にも寄与していたのでした。
しかし、ヘイズ・コードは1968年に廃止されます。映画業界にとっては表現の自由が戻ってきたので朗報ですが、動物愛護にとっては悲報でした。「American Humane」による動物虐待監視もこの時期を境に無くなったからです。
1970年代から1980年代にかけて、またも映画の撮影現場で動物が残酷に殺される事態が多発することになります。1979年の『地獄の黙示録』、1980年の『天国の門』など、実際に動物が殺される映像が映画で使用されました(Salon)。
こうした実情によって大衆が猛抗議してボイコットも激化し、映画業界は再び重い腰をあげることになりました。全米映画俳優組合(SAG)および映画テレビ製作者協会(AMPTP)は 「American Humane」と協力し、1988年からガイドラインを発行し、撮影現場で動物虐待が起きていないかをモニタリングすることにしたのです。なので業界の自主ルールで運用されています。
なお、「American Humane」は以前からすでに自主的に「No Animals Were Harmed」を付与する取り組みを始めていて、最初にエンドクレジットに「No Animals Were Harmed」が表示されたのは1972年の『ドーベルマン・ギャング』という映画だそうです(American Humane)。
こうして今に続くあのおなじみのエンドクレジットの「No Animals Were Harmed」が本格始動した…という経緯です。
何を基準に評価しているのか?
対象とする生き物は多種多様
歴史についての解説はこれくらいにして、次はこの「No Animals Were Harmed」の認証がどう行われているのか、その詳細を整理しましょう。基本的に「American Humane」のウェブサイトで説明されています。
原則として「American Humane」の専門スタッフが、映画などの制作準備の初期からマーケティングに至るまでの全プロセスに関与します。当然、撮影現場にも直接スタッフが赴き、問題が起きていないかを監視します。制作会社は動物を使用する場合は、「American Humane」に前もって通知するよう定められています。もし動物を適正に扱ううえでの不安や疑問があるときは、「American Humane」が支援し、課題を乗り越えられるように検討します。脚本の段階で「これは本物の動物ではなく、CGIを使うべき」と提言することもあります。
そしてこの認証で欠かせないのがガイドラインです。このガイドラインは「American Humane」のウェブサイトに掲載されており、誰でも見れますが、かなり膨大です。
そして非常に細かく、動物のカテゴリごとにもガイドラインは分けられています。
例えば、「犬」「猫」だけでなく、「馬」「霊長類」「鳥」「爬虫類」「両生類」「昆虫とクモ」など。
そうです、虫も対象です。具体的にはこんなガイドラインの内容があります。
「撮影に使用されたすべての昆虫はきちんと回収すること」…1匹も殺したり逃がしたりしてはいけないのです。「昆虫が照明に飛び込まないようにすること」…光に引き寄せられるので大変です。「昆虫やクモ類の近くで働く人々は喫煙しないこと」…虫は化学物質に弱いことがあるので警戒しないといけません。
魚のガイドラインもなかなか面白いです。魚なら定番の釣りのシーンは、死んだ魚やアニマトロニクス、その他の生きた魚以外の方法で撮影するように定められています。つまり、実際に本物の魚を釣るのはダメなんですね。魚が水から出ているシーンを撮る場合は、事前承認なしに魚を30秒以上水から上げてはならず、魚は2回続けて使用しないようにローテーションし、1日に3回以上使用することはできないと事細かく決められています。
映画で目立つ魚と言えばサメですが、サメは生体を輸送・保管するなどは基本やらずに、ドキュメンタリー的に実際のサメを撮るように推奨されています。
犬や猫の場合は、感染症の予防などかなり事前の条件がいくつも規定されています。
鳥の場合は、 ぶつかる危険性があるので鳥の周囲にガラス板を使用することは推奨されていません。また、鳥を放つときは回収は必須ですし、周囲に捕食者がいない環境を確保しないといけないと定まっています。
“傷つけてないか”だけでない、意外な評価も
また、ガイドラインは「動物を傷つけていないか」だけを論点にしているわけではないです。中には意外な評価点もあります。
まず動物が安全に落ち着ける環境を用意するのは絶対に大事で、ストレスを与えてはいけません。食事、日陰などのスペースは欠かせない要素です。
動物にコスチュームを着せる場合は、安全性が最優先で求められ、すぐに着脱できる状態にしないといけないと書かれています。爆発などの特殊効果で動物にストレスを与えないように配慮することも大事です。
また、動物が撮影現場にいるとつい触れ合いたくなってしまいますが、専門スタッフの許可がない限り、カメラの外で動物を撫でたり、餌をやったり、遊んだりすることはダメだとのこと。
これらは全て「動物の福祉(アニマル・ウェルフェア)」の範疇です。
そして「生態保全」の観点も強く重視されています。要するに動物を野外へ放つことに関して、とくにそれが侵略的外来種と指定される生き物の場合は厳禁となります。生息地を破壊するような行為も無論ですが認められません。
加えて、生きている動物だけでなく「死んだ動物」、つまり死体にもガイドラインがあり、衛生的な観点の他に、その動物の死体が適切に処理されたものであることを証明できないといけないなど、非常に隙の無い規定になっています。
具体的にこの映画では?
以上、ガイドラインを部分的に取り上げて説明してきましたが、でもなかなか実際の映画ではどうなっているのか、詳細が見えてきません。「No Animals Were Harmed」と表示されていても「いや、具体的にはどうやって傷つけていないの?」と半信半疑の人もいるでしょう。
「American Humane」のウェブサイトには、認証を受けた作品ごとに個別の詳細なレポートが公表されていて、それを読めば詳しくわかります(英語なので英語がわからないとダメですが)。
以下に一部をピックアップしましょう。
例えば、2022年の映画『バビロン』。この作品はそれこそ動物が虐待されてきたことで悪名高い1920年代のハリウッドが舞台になっており、たくさんの種類の動物が映画内で描かれます。まず冒頭でゾウが登場しますが、これは100%CGIだそうです。俳優がガラガラヘビと対峙するシーンでは、本物のヘビも使用されつつ、ゴム製のヘビも併用されたとのこと。生きたネズミをつかんで食べるゾっとするシーンでは、5匹のネズミを使い、実際に食べたのは偽の作りもののネズミです。さらに映画ではワニも登場するのですが、これはCGI…ではなく本物だとこのレポートには説明されています。
これらのレポートは映画の撮影の意外な裏側を知れて結構面白いので、映画鑑賞後に目を通してみるといいかもしれません。
認証システムへの批判
「American Humane」の「No Animals Were Harmed」は年間1000以上の作品で約100000頭の動物を保護するために取り組んでいるそうです。
一方でこの認証システムは全ての撮影現場の動物を網羅しているわけではありません。全米映画俳優組合(SAG)などが関与していない作品は対象外になるので、インディペンデント系の小規模な作品はチェックされないことがあります。また、アメリカ国外の撮影でもガイドラインをカバーできていないことがあります。
認証システムのチェックがないときは、当然ながらエンドクレジットに「No Animals Were Harmed」の表記はありません。
また、「No Animals Were Harmed」の認証があっても動物虐待が行われているのではないかと批判が起きるケースも勃発しています。
2011年から2012年にかけて配信された『Luck』という競馬を題材にしたドラマシリーズでは、「American Humane」のチェックがあったにもかかわらず撮影中に3頭の馬が死亡し、大きく非難を浴び、結果的にこのドラマはキャンセルされています(Slate)。
「American Humane」の組織自体への批判もあります。そもそもこの「American Humane」は映画業界からの資金提供で成り立っています。なので利益相反が起きやすく、本当に客観的に監視できるのかという疑念が払拭できていません(Vulture)。
こうした事情もあり、他の動物愛護団体がこの「American Humane」を非難することもしばしばです。
日本は?
ハリウッドの話をずっとしてきましたが、日本の映画界はどうなのでしょうか。
日本には「American Humane」の「No Animals Were Harmed」と同等の認証システムはありません。各映画製作者の良識に委ねられているのが現状です。
だからといって撮影現場で動物に何をしてもいいわけではありません。
日本では「動物の愛護及び管理に関する法律」、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」などがあり、これらは当然ですが、映画の撮影現場でも遵守しないといけません。違反行為は罰せられます。
問題はこれらの法律を守っているのか監視する人がいないということです。内部告発でもない限り、撮影現場での動物の扱いは不透明なままで、違法行為も浮き彫りになりようがありません。
日本を含め、世界中の映画でこれからも動物は出演し続けるでしょう。動物も映画のスターです。であるならば常に映画で仕事する動物のことを親身に考えて、業界を改善していきたいものです。
【ネット】
●2012. Hollywood’s long history of animal cruelty. Salon.
●2013. That “No Animals Were Harmed” Movie Credit Is Meaningless. Slate.
●2013. ‘No Animals Were Harmed’ Film Credit Is Often BS. Vulture.
●2015. 8 troubling tales of animal abuse on film shoots. The Week.
●2017. Genealogical Entanglements of Animal Rights and Feminist Movements. Active History.
●19 Women Making History for Animals Past & Present. In Defense of Animals.
