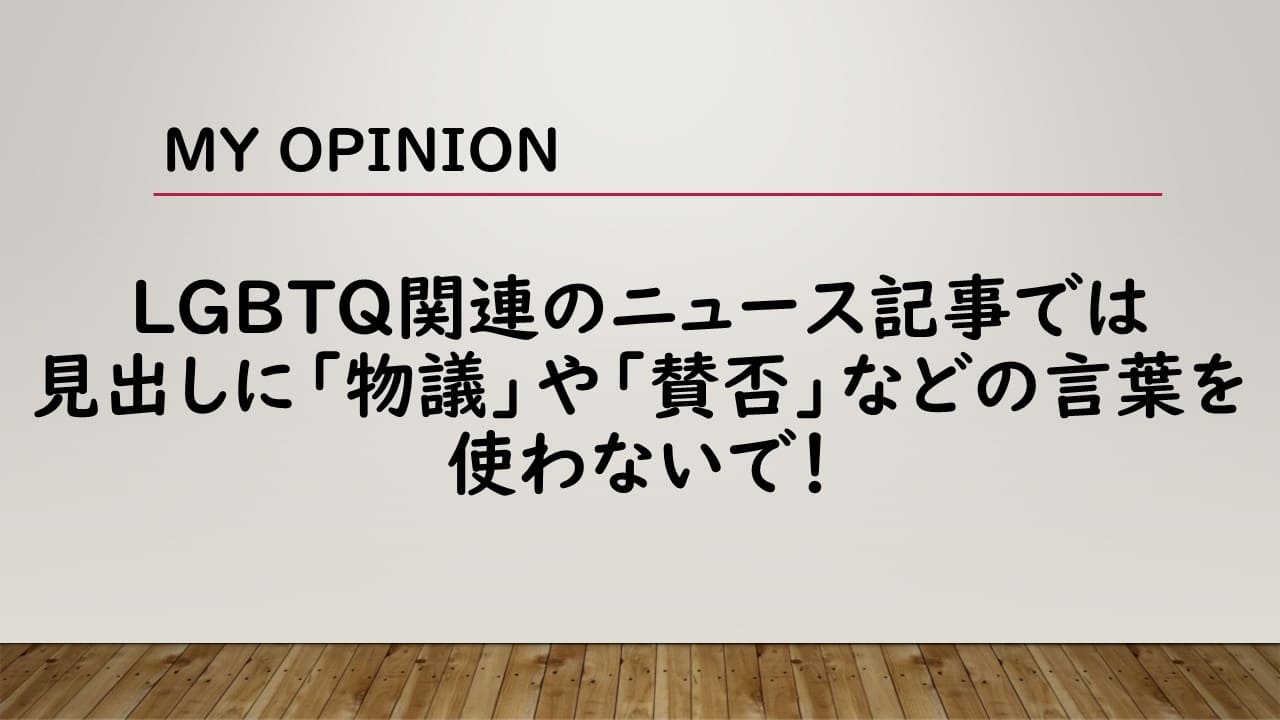今回は「LGBTQ関連のニュース記事では見出しに“物議”や“賛否”などの言葉を使わないで!」という題で、あれこれと思ったことを整理しています。
その見出しで大丈夫?
最近は日本でも大手メディアが当たり前のように性的マイノリティ(LGBTQ+)に関する話題のニュース記事などを報じることが増えています。
こうした報道において見出しは重要です。テレビでも新聞でもインターネット・メディアでも、見出しは欠かせません。その報道の印象はそれで決まると言っても過言ではないです。
そんな中、性的マイノリティに関する話題のニュース記事の見出しについて、やや残念な傾向がみられるように思います。
それはやたらと「賛否」や「物議」などの言葉を使いたがる…ということです。
例えば以下のようなかたちです。
- 「選挙候補者の同性婚への立場。賛否わかれる」
- 「女子大学がトランス女性を受け入れ。物議を醸す」
メディア側からすれば「だって実際にそのとおりだから」と主張するかもしれません。「この見出しは中立的なものを心がけました」と言い張るかもしれません。
しかし、それは本当に理由として正当でしょうか?
そもそも「賛否」がない事象なんて存在しません。たいていは賛成寄りもいれば否定寄りもいます。なんだって「賛否がわかれる」と言えるはずです。それなのにあえて今回に限って「賛否」という言葉を見出しに使うのは、見出しを考えた人の(無自覚にせよ)“意図”や“先入観”があるからでしょう。
「物議」も同様です。性的マイノリティは歴史的に常に差別を受けているのですから、「物議」なのは当然です。「物議」の根源にあるのは差別的な反応です。しかし、見出しに安易に「物議」と用いれば、その題材自体を咎めているだけになります。
結局のところ、こうした見出しのつけかたは、いわゆる「クリックベイト(Clickbait)」と同一になってしまっています。クリックベイトとは、興味を引くために誇張された表現を用いて情報媒体へのアクセスを促す手法のことです。「物議」や「賛否」といった言葉の見出しでのワンパターンな乱用は、「何やら性的マイノリティがまた論争を巻き起こしているのか?」と印象づけさせて行動を喚起する典型的な手口になってしまっています。
また、見出しだけでなく、付随して報道の中身も問題が多々あります。とくに結果的に差別に加担していると同じ効果をもたらすメディア・バイアスは無視できません。
例えば、2つの主張のうち、一方の側は全く根拠がないなど有効性に問題があるにもかかわらず、有効性がある側の主張と並列に提示することで、まるでどちらも対等な主張のようにみせてしまう…という「Bothsidesism(嘘のバランスの誤謬)」はよくみられます。
例えば、専門家の意見とネットの反応を同列に併記する(まあ、専門家の意見すら掲載していないこともよくあるのですが…)などです。
これは中立的でも事実を報じているわけでもなく、メディアが意図的に論争化を煽って、それで稼いでいるような状況でしょう。そして根本的にマジョリティ側の視点で見出しが作られてしまっています。
これらは日本のみならず世界中でメディアの問題点として浮上しています。
メディアのLGBTQ報道の問題点を厳しく指摘してきたメディア監視団体の「FAIR.org」や、LGBTQ専門のジャーナリストである“エリン・リード”氏は、報道内における「専門家や当事者の声の不足」に言及しています(FAIR;FAIR)。差別的なレトリックを何の注釈もなしに用いていることもあります(FAIR)。
一例として「FAIR.org」の調査によれば、何かと反トランスジェンダー側に偏った報道が問題視されているニューヨーク・タイムズ紙におけるトランスジェンダーに関する年間の報道を精査すると、トランスジェンダーに直接的な情報源の引用があるのは全体の11%だけだったそうです(FAIR)。「トランスジェンダーの人々や彼らが直面している問題に焦点を当てたものではなく、シスジェンダーの人々にとっての問題としてのトランスジェンダーの人々に焦点を当てたものでした」と「FAIR.org」はその報道論点の偏向を指摘しています。
日本であれば、LGBTQに関連する話題に対して、専門知識を持たない芸能人や保守主義的なコメンテーター、もしくは反LGBTQ(反トランスジェンダー)団体からのコメントを付け加えて報道し、印象を操作している事例も見受けられます。
当然、内容が偏っていれば見出しも偏りやすいです。
ではどういう見出しがいいのか。対立や論争を強調する必要はありません。それは弱い立場の人たちへのスケープゴート化を招くだけです。単純な二項対立を煽ったり、センセーショナルさを際立たせるのではなく、背景にある複雑な構造に興味を持ってもらう入り口になるような見出しが良いと思います。とくに専門家のコメントを参考にするといいでしょう。
- 「選挙候補者の同性婚への立場。背景に異性愛規範」
- 「女子大学がトランス女性を包摂へ。専門家は学問の平等を重視」
差別的な反応を反論なしで見出しに採用するのはやめましょう。
たかが見出しひとつでも、ときにはそのせいで当事者への誹謗中傷が急増することもあります。メディアは命や健康に間接的に関与するものだという意識が必要だと思います。
なお、今回はLGBTQなどの性的マイノリティに焦点をあてましたが、これはあらゆるマイノリティ(障害、人種、民族、宗教など)に該当する問題です。
まずは見出しから改善していきましょう。
今回の題材と関連のある詳細特集・用語解説特集の記事です。
・反トランスジェンダーのレトリックとは何でしょうか?

・「生物学的性別」という言葉を安易に使っていませんか?
・「LGBT」という言葉の意味を正しく理解していますか?