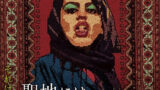そして穴が残る…映画『聖なるイチジクの種』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:ドイツ・フランス・イラン(2024年)
日本公開日:2025年2月14日
監督:モハマド・ラスロフ
DV-家庭内暴力-描写
せいなるいちじくのたね

『聖なるイチジクの種』物語 簡単紹介
『聖なるイチジクの種』感想(ネタバレなし)
イランから脱出した監督
禁錮8年。突然そう告げられたら…。
日本で懲役8年と言えばそれは危険運転で人を轢き殺したとか、そういうレベルの犯罪です。
しかし、政府に都合が悪い映画を作ったという理由で、そんな刑を下される人もいます。
“モハマド・ラスロフ”はまさにそんな経験をしました。
“モハマド・ラスロフ”はイラン人の映画監督で、2002年に『Gagooman』で長編監督デビューを果たし、その後も『Iron Island』(2005年)、『The White Meadows』(2009年)、『Goodbye』(2011年)、『Manuscripts Don’t Burn』(2013年)、『ぶれない男』(2017年)、『悪は存在せず』(2020年)を公開。『悪は存在せず』はベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞を受賞しました。
ところがそれを全く喜んでいなかったのが母国のイランです。表現や言論の自由を弾圧するイラン政府は、“モハマド・ラスロフ”監督を2010年に無許可の撮影を理由に逮捕。このときは懲役6年の刑を宣告し、後に減刑されます。しかし、それで終わらず、2017年に出国禁止。さらには2019年に制作した映画を理由に国家安全保障に反する罪だとして懲役1年の判決を受け、それ以降も続々と映画製作禁止を命じられつつ、控訴しながら闘っていました。
それでもついに2024年に懲役8年、鞭打ち、財産没収の実刑判決を受け、その年に国外へ脱出することを余儀なくされます。
その2024年にカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され(特別賞を受賞)、イラン当局が懲役8年とするほどに封じ込めたかった映画が本作『聖なるイチジクの種』です。
“モハマド・ラスロフ”監督はなんとか国外へ逃げられましたが、『聖なるイチジクの種』に関わった俳優や撮影スタッフの一部はまだイランにおり、諜報機関から圧力を受けたり、取り調べられたり、家族も含めて脅されたりしている人もいるそうです。
そんな状況の中、この『聖なるイチジクの種』を観賞するのは複雑な気持ちになりますが、観るぐらいしか自分にはできないという現実もあるので…。
『聖なるイチジクの種』というタイトルもなかなかに凄い意味不明ですが(その意味は後半の感想で詳しく)、物語はイランで暮らす一組の家族が主人公です。父と母、娘2人の構成。この家族がイラン国内の揺れる社会情勢の中で、ある危機を経験することになる…という家族ドラマのサスペンスです。
フィクションですけども、実際の近年のイランで起きた事件も取り上げられ、映画用に撮られたものではない映像も交えながら、イランの現実を切り取っています。
また、『聖地には蜘蛛が巣を張る』とも通じる、イラン社会における家父長制の根深さ、ミソジニーの醜悪さを徹底的に映し出しており、その構造を有する国家と家族の類似性を重ねて露にしてもいます。
まさしく生で体感した“モハマド・ラスロフ”監督だからこその迫力と言えますが、イランという国特有のものではなく、これはどの家族でも起きる恐怖だと示唆していくあたりは、警告的でもあります。
『熊は、いない』の“ジャファル・パナヒ”監督といい、今やイランで監督をしていた人はどんどんと映画を国内で作れなくなってしまっています。
もうイラン国内で映画を撮るのは厳しいのか…。イラン映画の未来は暗く、先が見えません。
でも『聖なるイチジクの種』を観て、絶対に覚えておきたいのは、監督だけが迫害を受けているわけではないということです。本作にも多くの無名の庶民(多くは若い女性)が酷い扱いを受けながらも抗議の声をあげている姿が映し出されます。
この映画はその現場で生きる人たちの感情を世界に届けています。それが何よりも政府が気に入らないことなのでしょうね。
『聖なるイチジクの種』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | 男性による妻や子への乱暴な描写があります。また、実際の暴力や死体が映るシーンが一部に含まれます。 |
| キッズ | 暴力的な映像がいくつかあるので、鑑賞には注意が必要です。 |
『聖なるイチジクの種』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
イランのテヘランで暮らすイマンという男は、車に乗って職場から家に帰るところでした。助手席には銃が一丁置いてあります。場違いに見える銃。イマンにとっても見慣れていないものがすぐそばにある違和感。これはつい今しがた国から支給されたものでした。
夜中に帰宅。妻のナジメが迎えます。家族は長女レズワン、次女サナ…この4人です。2人の娘たちはすっかり成長し、もう子ども扱いはできません。
やや疲れた顔のイマンは妻に例の銃をみせます。護身のために持つことになったものでした。イマンの仕事は予審判事に昇進したばかり。20年の地道な勤務が評価されたのは嬉しいですし、そのおかげでこうして家族はそれなりに良いアパートで暮らせています。生活は確実に安定しました。
ただ、その仕事柄、昨今は何かと反政府の抗議運動も起きているため、イマンも身を守る必要があると上からの判断のようです。
妻はその銃を手にすることを嫌がりますが、触れてその重みを実感。娘たちにこの銃について言うのかとイマンは聞かれ、娘たちには言わないと今は告げて、とりあえず寝ることにします。銃は無造作にそばに置いておくことに…。
イマンはこの家族は安全だとなだめますが、妻のナジメは心配が尽きません。テレビをつければエスカレートしていく抗議運動が報道されており、いつ自分たちに影響があるかと悩みが募るばかり。
母として娘たちには「注意深く行動しなさい」と事あるごとに言いつけ、「この生活があるのだから」と釘を刺します。
全国的な政治抗議運動が激化する中、イマンは仕事で憔悴していました。事務仕事とは言え、抗議運動のさなかに捕まった人たちに刑を下していく作業は気分が沈みます。裁判らしいことはほとんどしていません。
一方、レズワンとサナは家でくつろいでいるような素振りでしたが、スマホで抗議運動の情報を得て、こっそり2人でやりとりしていました。親友の中にはその抗議に参加している者もいて、現場の生々しい映像の数々がスマホに流れてきます。それにはテレビの報道では見られない抗議者の切実な訴えも含まれていました。
こうして家族それぞれが違う目線で世間を見つめていたある日、イマンが引き出しにしまっていたはずの銃が消えてしまいます。家のどこを探しても見つかりません。家族以外は家に来ていません。焦るイマンは娘たちにも銃の話をしますが、発見には至りません。
そしてある疑惑がイマンの頭をよぎります…。
背景にあるマフサ・アミニの死

ここから『聖なるイチジクの種』のネタバレありの感想本文です。
『聖なるイチジクの種』の物語自体はフィクションですが、作中では実際のイラン国内で起きた抗議運動の映像が挿入されます。その多くはスマホで撮影されたものです。これは臨場感をだすための演出ではなく、映画の最後もそれらの映像で締めくくられることからもわかるように、本作の重要な主題であることが提示されます。
あの抗議運動は主にイランにおける女性差別への抗議です。なので参加者の多くは若い女性であることが目立っていました。
とくに作中でも取り上げられているのが、「マフサ・アミニ」の死に関する事件。この事件は日本ではそこまで知られていないので、一応簡単に説明すると…。
2022年9月13日、22歳の“マフサ・アミニ”というイラン国籍のクルド人女性がイランのテヘランにおいてヒジャブ(ヘジャブ)の着け方およびタイトなズボンの着用を理由に道徳警察に拘束されました。イランのような保守的なイスラム国家では女性の服装に対する取り締まりが非常に厳しいです。
逮捕当時、“マフサ・アミニ”は警察のバンに乗せられたのですが、その後に意識不明になったということで病院に急遽搬送。3日後に死亡が確認されました。
警察当局は心臓発作だと発表しましたが、“マフサ・アミニ”の家族は健康上の問題はなかったと語り、また同じくバンの中にいた女性は“マフサ・アミニ”が警察に暴行を受けていたと証言。
これにイランの大衆の一部は激怒し、全土での大規模な反政府デモに発展しました。政府当局はこれを武力で弾圧。大勢の犠牲者と逮捕者をだしました。また、抗議に反発する国内のイスラム原理主義が活発化し、若い女性を狙って毒ガステロを行う事件も相次ぎました。
この一連の正義を求める抗議の拡大によって「Mahsa Amini」の名は一種のアイコンとなり、現在もイラン、そして世界の女性の人権を保護する運動の象徴のひとつです。
『聖なるイチジクの種』も、挿入される抗議運動の映像でヒジャブを振り回して厳格な着用強制の圧力に反対する女性たちが多数映し出され、作中の主役家族の娘たちであるレズワンとサナも感化されていく姿が描かれます。
この娘たちの描写はまさにイランのリアルタイムそのものでした。強調されるのは見ているメディアの違いですね。やはりメディアの責任は大きいです。人を保守的に従順にさせるのも、正義の抵抗に駆り立てるのも、メディアしだい。
まず最初に娘たちが感化され、次に母であるナジメを葛藤させることになります。ナジメも典型的な事なかれ主義で、家庭の平和を第一に考え、抗議運動を「過激」と他者化し、関わらないように娘たちをなだめようと最初はします。
しかし、やっぱりそうも言ってられません。なぜなら無関係ではないからです。女性であるという事実は否定しようがなく、問題は娘ではなく社会にある。
そして決定的な恐怖が家庭内部から襲ってくることに…。
イチジクの意味
『聖なるイチジクの種』はフェミニズムなテーマが土台にある以上、娘たちなど女性を主役の視点だけにしても良かったはずですが、そうはなっていません。男性である家族の夫&父であるイマンの視点が半分以上は軸になっています。
このイマンについて、物語の途中から劇的な変化が起きます。結構な急展開なので(ジャンルも変わったようにすら思える)、面食らうのですが、作り手としては意図的な仕掛けなのだろうなとは察せます。
そもそも冒頭のイマンが銃を配給されて廊下を歩いていくシーン。この廊下には指導者の肖像がいくつも並んでおり、映画終盤のイマンの未来を暗示しています。非常にこの映画を象徴するショットでした。
そして「銃」。作中ででてくる銃はハンドガン。平凡な銃です。これもまた権力の象徴であり、興味深いのは「本人は別に欲しくなかったけど、護身のためという口実でもらってしまったもの」という扱いになっていること。そんな程度であっても男性を権力化するにはじゅうぶんだという鋭い批評があったと思います。
イマンは当初は仕事に疑問を感じ、心身に不調を感じてもいたようですが、それでもこの銃の消失が完全にスイッチとなります。
私はこの「事態を収拾せねばと焦る家長の暴走」という描写も、このタイプの男性の生態としてすごくリアルだと感じました。一見まだ良識がありそうでも、追いつめられると途端に権力化する男というのはいるものです。それをわかったうえで国など組織的権力者はそれら男性の心理までも巧みに操ります。
後半のイマンは妻や娘を監禁して脅すことに躊躇いなくなり、道徳警察状態になります。家庭でも男はいくらでも道徳警察になりうる…。国が直接は手が届かない家庭というプライベートなスペースでもこうやって権力は統治する…そういう仕組みです。
そこで寓話的に活用されているのが、タイトルにある「イチジク」です。
イチジクは日本でも知られるあの植物のことですが、もともと中東あたりが原産地とされており、古来から人間社会の文明でよく言及され、宗教文化でも頻繁に登場する身近な落葉高木です。
このイチジクの仲間には「絞め殺し」という生態があります。イチジクが土から芽ぶく際に近くの木に絡みつくように成長するのです。こうして日光を浴びやすい上方へと幹を効率的に伸ばします。そして絡みつかれた側の木は枯れてしまいます。絡みつかれた側の木が枯死して崩れ去ると、中空ができた状態で外側にイチジクだけが伸びている異様な構造が出来上がります。空洞の中から見るとまるで「穴」です。
『聖なるイチジクの種』でもラストで唐突に「穴」が出現し、イマンは消えます。それこそ国家というイチジクにいつの間にか利用され、最後は枯れて捨てられる樹木のように…。
本当に小さくて何気ない種(銃)でも、それはもしかしたら身近なものを絞め殺して利用するイチジクのような存在かもしれない…。そんな警告を私たちは噛みしめて声をあげていきたいですね。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
関連作品紹介
第77回カンヌ国際映画祭の受賞作の感想記事です。
・『憐れみの3章』(男優賞)
作品ポスター・画像 (C)Films Boutique 聖なるいちじくの種 ザ・シード・オブ・ザ・セイクレッド・フィグ
以上、『聖なるイチジクの種』の感想でした。
The Seed of the Sacred Fig (2024) [Japanese Review] 『聖なるイチジクの種』考察・評価レビュー
#イラン映画 #中東 #モハマドラスロフ #政治迫害 #抗議運動 #カンヌ国際映画祭 #アカデミー賞国際長編映画賞ノミネート