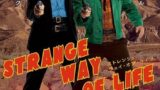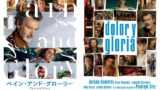私は落ち着いて死ねそうにない…映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:スペイン(2024年)
日本公開日:2025年1月31日
監督:ペドロ・アルモドバル
自死・自傷描写
ざるーむねくすとどあ
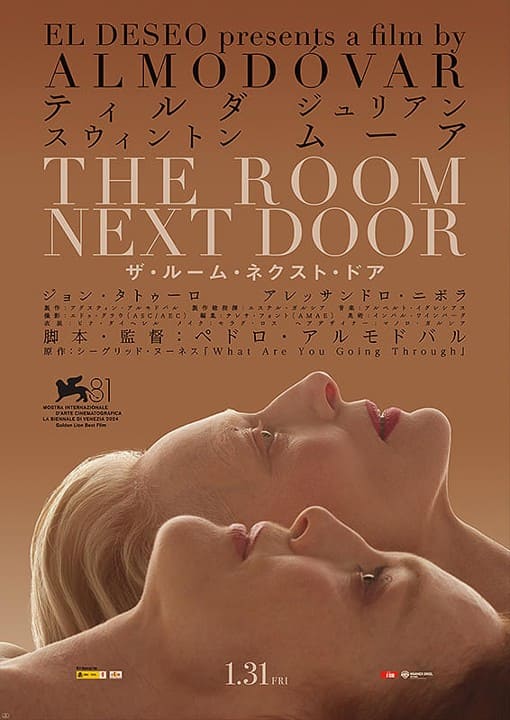
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』物語 簡単紹介
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』感想(ネタバレなし)
シモーヌ・ヴェイユが現代に蘇る
「シモーヌ・ヴェイユ」という哲学者がいました。1909年生まれのユダヤ系のフランス人でしたが、哲学者として有名になったのは死後です。シモーヌ・ヴェイユは34歳という若さで亡くなってしまいました。急病で倒れたのですが食事を拒否して、事実上、自ら息を引きとる道を選んだようなかたちでした。
死去したときに埋葬に立ち会ったのもわずかな友人だけ。そして友人のひとりがシモーヌ・ヴェイユの思想を書き留めたノートを受け取り、それらが編集されて出版。こうしてシモーヌ・ヴェイユはこの世を去ってから哲学者になったのです。
そのシモーヌ・ヴェイユの著作『神を待ちのぞむ』の一節から引用したタイトルの小説を2020年に“シーグリッド・ヌーネス”という小説家が発表します。『What Are You Going Through』という題名の作品です。
この作品は主人公が昔からの友人付き合いがあったひとりの人物から「末期癌で安楽死しようと思うから死ぬときは隣の部屋にいてほしい」と頼まれる…というざっくり言えばそういう物語です。
物語と言っても、波乱万丈の起承転結があるわけでもなく、起伏の乏しい淡々とした会話と自問自答な振り返りで成り立っています。しかし、どこかシモーヌ・ヴェイユの思想とその人生の幕引きを現代に再解釈したような手触りがあり、独特の味わいがあります。
その“シーグリッド・ヌーネス”の小説が2024年に映画化されました。
それが本作『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』です。
特筆すべきは、この映画を監督したのが“ペドロ・アルモドバル”だということ。知る人ぞ知るスペインの巨匠です。なんでも今回が初の英語の長編作品になるらしいですね。「あれ? これが初めての英語だっけ?」と思って振り返ったら、『ヒューマン・ボイス』(2020年)や『ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ』(2023年)のような短編の英語作品はあったけど、長編は初でした。短編も普通に長編と変わらずに楽しんでいたから、最近は英語多めだと思ってましたよ…。
そして、“ペドロ・アルモドバル”監督は今作『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』によってヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞に輝きました。三大国際映画祭で最高賞を獲ったのはこれが初だそうで…。「あれ? そうだっけ?」と思ってこれも振り返って調べたけど、確かにそのとおりでした。『オール・アバウト・マイ・マザー』とか『ペイン・アンド・グローリー』とか、じゅうぶん評価が高かったし、何か三大国際映画祭で最高賞を獲ってるだろうと思い込んでいたけども、意外とこぼれていたんですね…。
そういう意味では今回の『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は“ペドロ・アルモドバル”監督の最高傑作!というよりは、功労賞的な意味合いでの受賞が大きい感じもするな…。個人的には英語映画よりもスペイン語映画が最高傑作扱いになってほしいところはある…。
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』で主演するのは、“ティルダ・スウィントン”と“ジュリアン・ムーア”。誰もが認める実力あるベテラン俳優2名。この2人の掛け合いで物語の90%は成立しています。正直、この2人の組み合わせがあれば、見ごたえは一定の確保ができたところはありますね。
もちろんいつもの“ペドロ・アルモドバル”監督作らしい色彩豊かな映像カラーコーディネーションは健在。スクリーンが絵の具のパレットのようになりますよ。
“ペドロ・アルモドバル”監督作が好きな人は必見の映画です。
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | 安楽死(厳密には自死)が描かれます。 |
| キッズ | 大人のドラマなので子どもには退屈かもしれません。 |
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
イングリッド・パーカーは書店でサイン会を開いていました。多くの女性が並んでいて、イングリッドは気さくに対応します。ベストセラー作家になり、キャリアは順風満帆でした。
そのとき、ひとりのその場にいた人からマーサ・ハントの名をだされます。懐かしい名前です。イングリッドとは若い時の親友であり、以前は出版関係で交流もありました。しかし、すっかり交友は消えてしまい、疎遠になっていました。
どこかで元気にやっているだろうと思っていましたが、なんでも末期癌らしいです。それが事実ならば無視するわけにはいきません。
イングリッドはマーサがいるという病院に足を運んでみます。マーサは病室に現れたイングリッドを見て嬉しそうな声をあげました。病室はマンハッタンの街並みが見渡せる窓が一面にあり、綺麗な部屋です。マーサはそこでベッドに横になっていました。
ベッドに横たわっている姿はそこまで酷い状態ではないように思えます。しかし、マーサは病気なのは動かぬ事実でした。
久しぶりに2人は会話を楽しみます。昔話もいくらでも口からこぼれます。この2人は実は同じ男性と付き合っていたこともありました。最初はマーサ、次にイングリッドというかたちで交際が流れたのです。マーサにとっても、イングリッドにとっても、楽しい思い出ばかりではありません。マーサは従軍記者だったこともあり、過酷な現場も知っています。それでも過去を語ることはしばらく止められそうにありません。
これを機会にイングリッドはマーサのもとに何回か通っていき、久しぶりの交友を重ねて、かつてのあの時間を取り戻していきます。
マーサはときおり苦しそうに感情を露わにします。そのたびにイングリッドは落ち着かせ、寄り添います。今やマーサにとってイングリッドが一番の信頼できる相手になっていました。
そしてマーサはあるお願いをしてきます。マーサはもう治療をする意思はないとのこと。さらに自らの意志で安楽死を望んでいるというのです。しかも、人の気配を感じながら最期を迎えたいそうで、どこかで死ぬときはイングリッドに隣の部屋にいてほしいと頼んできます。
すでに何人かにお願いしたものの断られたらしいです。さすがに深刻なお願いなので、マーサも躊躇します。しかし、目の前の友人を放置できません。悩んだ末にマーサの最期に寄り添うことを決めました。
こうしてイングリッドはこのためにマーサが借りた郊外の森の中にある家で暮らし始めます。そこは落ち着いた室内で、景色が一望できます。喧騒はなく、静かです。
マーサはイングリッドに「自室のドアを開けて寝るけども、もしそのドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいない」と告げます。
穏やかな日常がいつ2人から1人に変わるのか、それはマーサの気持ちしだいで…。
思想が物語に色づいていく

ここから『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』のネタバレありの感想本文です。
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』は“ペドロ・アルモドバル”監督いわく『ペイン・アンド・グローリー』の一種の姉妹作として機能するような位置づけだと考えているそうです。
確かにこの2作品は大まかに似た軸を持っています。あるひとりの主役が病気で死が近づき、自分なりの人生の振り返りをし、終わり方を考え、その人生が何かの創作に溶け込んでいく…。終活映画といった様相でしょうか。
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の場合は安楽死を望みます。ただし、ここで注意が必要なのは、作中でも少し言及されますが、アメリカでは全面的に安楽死制度が整備されているわけではないということです。医療による安楽死の試みは、カリフォルニア州やワシントン州など11のアメリカの管轄区域で合法となっていますが、大部分の地域では違法であり、自殺ほう助とみなされます。州によって違うのでかなりグレーな部分が多く、関与は極めて法的にも難しい面があります。
なので作中でイングリッドがマーサの安楽死(実質は自殺)に事実上加担するか悩むのも当然です。下手すれば有罪ですから。終盤ではイングリッドは警察の取り調べを受けるハメになり(当然警察も疑いはするでしょう)、状況はやや面倒になります(それでもお咎めなしで済む)。
とはいえ、この映画は「安楽死は合法化されるべきか?」を問うような社会問題提起を前面には打ち出してはいません。
むしろこの記事の最初に触れたように、当時の亡くなり方としてはそれしか手段が無かったのであろう、シモーヌ・ヴェイユの人生史を素材にして、現代解釈を加えながら、その哲学思想をなぞるような物語になっています。そのため、創作的な膨らまし方をかなり盛り込んでいました。
映像化においても安楽死のリアリティとかもあまり考えてはいない感じです。とは言え、尊厳ある人生の終わり方についてのテーマを軽視しているわけでは当然ないです。
渦中のマーサも病で衰弱しているとは言え、妙な存在感を放っています。これは演じているのが“ティルダ・スウィントン”であるという事実も無視できず、本作のマーサはほぼ“ティルダ・スウィントン”ありきの個性で佇んでいます。末期の人がいるというよりは、“ティルダ・スウィントン”がいるって感覚ですかね。“ティルダ・スウィントン”はどうも現実離れした人物性を当人が持っていますから、どうしたって雰囲気がでます。
従軍記者という設定はやや浮き出すぎているようにも思いましたが…。
対する“ジュリアン・ムーア”演じるイングリッド。“ジュリアン・ムーア”もフィルモグラフィー上において、何かと自分が死ぬ役柄か、親しい人が死ぬ役柄なことが目立つ人です。だからこの映画にもぴったりだとしてキャスティングされたのかもしれません。いつも深く葛藤している役で、なんか可哀想にも思うけど…。
この2人の対話がそれ自体で哲学を形作るように続いていくのがこの映画の大部分の見せ場となります。“ティルダ・スウィントン”と“ジュリアン・ムーア”の会話が面白くないと感じてしまったら、この映画はまず楽しめないくらいにはメインの構成要素です。話していることは結構些細なことだったりもしますが、思想文学的な読み取り方があると深く心に刻まれやすいかもしれませんね。
実在するあの家
『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』のもうひとつの最大の特徴は、“ペドロ・アルモドバル”監督作らしい色彩豊かな映像カラーコーディネーション。これが想像どおりの鮮やかさでした。
まず序盤の病院からしてカラフルです。たいていは無機質な空気であるはずの医療施設空間なのに、なぜかここでは四季すら感じさせます。この四季を匂わすのは映画全体を通して明らかに意図していました。
主に使用されるのは「赤」と「緑」。クリスマス・カラーなのではなく、生命と生死を最も感じさせる色であり、同時に四季を感じさせる二色でもありますから、そういう設定なのかもしれません。
イングリッドは最初は赤い服で、車も赤く、例のドアすらも赤いです。対するマーサは緑色で、ファッションは落ち着いています。
作中では緑溢れる家で死の到来を待ち、それは色づいて落葉するかのように変色し、やがては雪舞う季節となります。それは自然の成り行きであり、自然のサイクルなので、循環として繰り返されます。そのため、本作における死は終着点ではなく、次の循環の始まりです。悲壮感は薄まるようにカラーデザインで演出されています。
その四季による死生観をそのままなぞるように、マーサからイングリッドへ、そして次の(終盤にでてくる)あの人物へと物語は引き継がれていきます。
それにしてもあの家もやけに凄かったですよ。撮影はマドリード近郊で、あの家もそこに実在するもので、デザイナーが設計した特別な家らしいです。ネットで調べると「周囲の自然環境に家を溶け込ませることを目指した」と書かれているのですけど、正直な感想を言えば、全然溶け込んでいないと思う…。あんなガラス張りだと、野鳥がガンガンぶつかって怪我するだろうな…と想像してしまう私…。
こういうオシャレな家で、完璧な彩りの室内の中、クラシック映画なんか見ちゃったりして、死を迎えるのはステキだろうと思える人には心地良い映画なのでしょうけども、こう言ってはなんですが、私はこういう空間が体質的に大の苦手なので、たぶん落ち着いて死ねそうにないですね(私は慣れ親しんだ地味な空間のほうが安心するタイプなんです…)。
そういう意味でちょっと私には『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』はフィットしない映画ではありましたが、きっと好きな人には趣味に刺さる内容なのはよくわかりました。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
作品ポスター・画像 (C)2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. ザルームネクストドア
以上、『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』の感想でした。
The Room Next Door (2024) [Japanese Review] 『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』考察・評価レビュー
#スペイン映画 #ペドロアルモドバル #ジュリアンムーア #ティルダスウィントン #安楽死 #死別 #ヴェネツィア国際映画祭