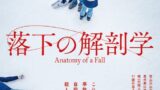あなたのゾーンはそれでいいのか…映画『関心領域』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:アメリカ・イギリス・ポーランド(2023年)
日本公開日:2024年5月24日
監督:ジョナサン・グレイザー
人種差別描写
かんしんりょういき

『関心領域』物語 簡単紹介
『関心領域』感想(ネタバレなし)
ゾーン・オブ・インタレストを眺める
第二次世界大戦時、各地を占領して支配権を強めたナチス・ドイツは、強制収容所を設置し、ユダヤ人や少数民族、性的少数者を閉じ込め、残虐に苦しめました。
その強制収容所は「Vernichtungslager」(「絶滅収容所」の意味)と呼ばれていましたが、それに関連した用語で「Interessengebiet」というものがありました。
これは英語では「Zone of Interest」と表現され、直訳すると「興味関心の領域」となります。これだと何を指しているのかさっぱりですが、強制収容所設置の際に確保される周辺地域を示す用語でした。
「Zone of Interest」は基本的に強制収容所の周囲40平方km(4000ヘクタール)の区画で、そこにもともと住んでいる人は排除し、農地も接収します。かなりの広さです。こうして強制収容所に地域住民が接触できないようにするのですが、その区画の農地で収容所囚人を労働させ、農作物で儲けをだしたりもしていたそうです。
ドイツ占領地のポーランド南部オシフィエンチム市に設置されたアウシュヴィッツ強制収容所の「Zone of Interest」は、当然ながらそのエリア内を親衛隊(Schutzstaffel; SS)が厳重に監視していたのですが、その管理を現場指導していたのが「ルドルフ・フェルディナント・ヘス」という人物です。
ルドルフ・ヘスは親衛隊将校であり、アウシュヴィッツ強制収容所の所長に任命された後、その施設の拡大に寄与しました。戦後、捕まったルドルフはニュルンベルク裁判で証言し、絞首刑で処刑となりました。
今回紹介する映画は、そのルドルフ・ヘスとその家族を主題にしているのですが、アプローチはかなり変わっています。
それが本作『関心領域』です。原題はずばり「The Zone of Interest」。
この映画の特異な点をまず挙げるなら、先ほども説明した「Zone of Interest」のエリアだけしか描いていないということ。強制収容所内は全然映しません。いろいろなホロコースト映画は過去にもありましたが、この「Zone of Interest」だけに着目するというアイディアが非常に効果的に活きてくることになります。
本作で描かれるのは、ルドルフ・ヘスの家族の日常。穏やかな生活がのんびり淡々と、まるで家族密着番組の固定カメラで覗いているような感じで繰り広げられます。
演出的な狙いは明白で、凄惨な強制収容所のすぐ隣接した場所で平穏な家族ドラマがあるというギャップですね。これでもかとそれを対比させてきます。こうして加害者の実像に迫っていきます。
歴史を説明するような作品ではありません。そういう背景を知りたければ『ファイナル アカウント 第三帝国最後の証言』や『アウシュビッツの会計係』のような加害者を題材としたドキュメンタリーを補足で観るといいでしょう。
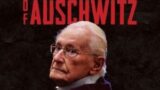
ホロコーストの加害者の視点で描いた劇映画もこれまでもいくつもありましたが、『関心領域』はそれとは抜きんでて突出した一本になったのは、この監督のセンスゆえです。
『関心領域』を監督したのは、“ジョナサン・グレイザー”。2000年の『セクシー・ビースト』で長編映画監督デビューを果たし、2004年の『記憶の棘』からしばらく映画を離れましたが、異色のSFカルト作『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2014年)で強烈にカムバック。
『関心領域』は10年ぶりの長編監督作となり、“ジョナサン・グレイザー”監督のフィルモグラフィーで最大の高評価作となりました。
一応、本作は“マーティン・エイミス”による2014年の小説を大まかに参照しているのですが、完全に“ジョナサン・グレイザー”監督の作家性で塗り直されていますね。ホロコースト映画の中でも相当に癖の強い一作ですが、おそらくしばらくはベスト級のホロコースト映画として語り継がれていくのだろうな…。
主演でルドルフ・ヘスを演じるのは『ヒトラー暗殺、13分の誤算』の“クリスティアン・フリーデル”。そのルドルフの妻を演じるのは『落下の解剖学』の”ザンドラ・ヒュラー”。2人の演技も目が離せません。
『関心領域』は直接的な残酷描写はほぼないので、見やすいと言えばそうなのですけど、それが実は一番残酷だよ…という映画でもあるので…。
ともあれ加害者の立場を体感する最悪な映画体験にはなるでしょう。
『関心領域』を観る前のQ&A
オススメ度のチェック
| ひとり | :必見の傑作 |
| 友人 | :強烈な体験を共有して |
| 恋人 | :デート気分ではない |
| キッズ | :わかりにくいかも |
『関心領域』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
湖畔でピクニックを楽しんでいる一組の家族。穏やかにくつろいでおり、水に入り、じゃれあったり、茂みを散策したりと自由気ままです。他に人はおらず、安心しきっていました。
ぞろぞろ歩いて森を通り、帰路につきます。車で林道から少し大きな道路にでて、夜道も車内の楽しい会話と共に帰宅。家族の住む邸宅はすぐ近くにありました。
こうして充実した1日は終わり。
ルドルフ・ヘスの家族はそんな暮らしを送っています。妻のヘートヴィヒ、そして幼い息子や娘たち。幸せな家庭を築いていました。
翌日、子どもたちは父ルドルフにカヤックをプレゼントします。誕生日なのです。温かい好意にルドルフも嬉しくなり、今後一緒に乗ろうと約束し、戯れます。
そんなルドルフもすぐに仕事に向かわなければなりません。といっても職場はこの区画です。家の門を通れば、同僚たちがたくさん働いています。ルドルフはこのエリアを任せられた所長なのです。多くの部下がおり、みんな一丸となって国家に尽くしています。
邸宅には広々とした庭があり、ヘートヴィヒが赤ん坊を抱えて、美しいたくさんの花々を鑑賞します。メイドが家事をしてくれており、庭の管理も行き届いているので、時間はたっぷりあります。
ときおり衣類などの品を受け取ることもでき、メイドや子どもに分け与え、毎日は楽しいです。
数時間後、ルドルフは建築設計士と焼却炉の図面の説明を受けます。2つに分離した仕組みになっており、一方を冷やしている間にもう一方を燃やせるので、効率的に遺体を燃やし続けられると設計士は解説。ルドルフの運営する施設にとってはこの処理はとても大切なので、効率性の向上にルドルフも満足します。きっと上層部も納得するでしょう。
ルドルフが外に出ると大勢の制服姿の同僚が集まっていて、誕生日を祝ってくれました。
その後は、長男と馬に乗って散歩。背の高い農地の茂みを通り抜けて、また子どもとの憩いの時間を過ごします。
夜、ルドルフはタバコを吸いながら庭で今日の疲れを癒します。仕事は順調で、このままいけば何も支障はないでしょう。
ルドルフは家の鍵を厳重に閉じ、電気を消して今日を終えようとします。
ところが、娘のひとりが寝られなかったのか廊下でうずくまっていたので、ルドルフは娘に物語を読み聞かせてあげます。
それも終え、やっと夫婦で別々のベッドに寝転んで、向き合いながら気楽に談笑。冗談好きのヘートヴィヒは愉快そうです。
家族のために、明日も精一杯働こう。働けば自由が手に入るのだから…。
見えない…聴こえる…

ここから『関心領域』のネタバレありの感想本文です。
私は、差別における社会構造の悪化は、「無関心・冷笑」⇒「他者化(othering)」⇒「非人間化(dehumanization)」の順で、段階を踏むように進行していくと考えているのですけども、本作『関心領域』はその様態をまざまざと突きつける一作でした。
とにかくエグるような狙った演出が冒頭から刺さりまくります。まず、映画が始まると、鳥のさえずりや水の流れる音、風のざわめきなど、自然の音が耳に流れてきます。これはごく普通の音です。しかし、この環境音が本作の最大の残酷さになるという前触れで…。
以降、ヘス家の家族の日常がのほほんと映されますが、その背景には、乾いた銃声、罵声、悲鳴…そんな音がこれも”ごく普通に”耳に流れてきて…。
ヘス家にとってはこの音さえも、自然音と同じ。その現実に、慣れ切っていない観客側にしてみたら戦慄です。
加えて聴覚だけでなく視覚表現でも、その残酷さを重ねてきます。直接的な暴力表現はありません。むしろその”見せない”ことが恐怖を想像させる嫌な演出になっています。
ヘス家の邸宅は本当に強制収容所に塀1枚で隣接していて、庭を映すシーンではよくわかりますが、身長の2倍くらいある塀は上部に有刺鉄線があり(しかも奥側を向いていることでどちらに敵意を向けているのかがよくわかる)、それは単なる壁ではないことを無言で示しています。その塀の奥にあるのは、かの有名なレンガの建物で、銃殺に使われた「死の壁」がすぐそこにあるということを示唆してもいます。
そんな近くで園芸をしていて「綺麗だね」とか言いながら生命を鑑賞しているんですよ。それだけでもゾっとするのに「その植物の肥料に使われているのは何なのか」を考えるともう…。
「無関心」「他者化」「非人間化」の3段コンボを全部一気にクリティカルヒットで食らった気分…。2024年で一番怖いホラー映画は本作だった…。
塀以外にも鬱蒼とした茂みも効果的に利用していて「その奥で何が行われているのか」を“見せず”に表現してきます。当然、この演出が成り立つのは、私たちはアウシュヴィッツ強制収容所で何が起きていたのか、歴史的に知っているからなのですが…。
この「見せない演出」は『サウルの息子』などでもありましたけど、『関心領域』は加害者の構造を表す演出としてただただ鋭利に強烈です。
その残酷さの上に規範的な家族の平和が築かれているというのがまた象徴的。妻であり母であるヘートヴィヒは「私はアウシュヴィッツの女王なの」とジョークを飛ばすなど、ちょっと冷笑仕草もこぼれています。
ルドルフは直球で非道に手を染めている描写はあまりないのですが(まあ、言わずとも実在の人物ですし、最悪なことをやっているのはわかるのですけど)、庭で一服する姿の背景に火葬炉の煙突の煙がもくもくとあがるシーンとか、「カッコいいキャリア男性」のPRに見える絵を組み立てているのがなんかもう「うわ…」ってなる…。
加害は自滅であり、今も日常である
『関心領域』におけるヘス家は確かに平穏そうなのですが、一方で実はじわじわと崩壊もしていることが、本作では裏で描かれており、それはどんどん表面化していきます。
例えば、娘は明らかに寝れておらず、息子も暴力性を育むような環境になっており、メンタルヘルスが心配になってくる有り様です。
そして、最も”染まっていない”(それでもユダヤ人差別感情はしっかりあるのですが)人間であるヘートヴィヒの母は来訪して1日でもう精神的に耐えられなくなって出ていってしまいます。
この「Zone of Interest」という世界の構造の影響は各自を自滅的に追い詰めているのですが、大部分の当人は自覚できていません。
ヘートヴィヒも、上手くいかないことがあるたびにメイドに当たり散らし、脅迫さえするのですけども、メイドがいなくなると、家事をするハメになるのは、ジェンダー・ロールから言えば当然のようにヘートヴィヒ自身になってしまうのですよね。でもそこまで考えは至りません。
ルドルフはキャリアの重圧と残虐行為の重さを蓄積し、夫婦不和が立ち込める中、家庭という生き抜きの場さえも失い、やがて精神に不調をきたしていくようになります。ラストで吐き気が生じるという演出は、ちょっと『アクト・オブ・キリング』を彷彿とさせますね。
この自滅の未来を黙殺してしまう当人の心理を本作は上手く捉えていて、ホロコーストという主題だけでなく、環境問題にも射程を含めているのも良かったです。
例を挙げると、焼却された収容者の遺灰が川に流されて汚染されている場面や、その煙が立ち込めて空気が汚染されている場面。確実に自分たちの所業のせいで自分たちの安寧と考えていた住処さえも壊れているのに、その現実を見て見ぬふりをし続ける。
本作の最大の刃は、ラストの演出。階段を降りているルドルフが嘔吐に苦しんでいると、パっと画面が変わり、現代に。映るのは、博物館となった今のアウシュヴィッツ強制収容所の跡地。そこでは清掃員の人たちが淡々と掃除をしています。博物資料のみを映すだけなら「歴史を忘れないようにしましょう」という教訓メッセージになるのですが、あえてここに清掃員も映すのが“ジョナサン・グレイザー”監督の技ですね。
つまり、現代における「Zone of Interest」。別に清掃員は加害者ではないのです。でも私たちは常にどこかで何かに対して「関心を寄せずに仕事している」という事実。その刃物を観客に突き立てたところで、またルドルフのシーンに戻って、暗い階段の下に降りていく…。このエンディングを考えついたらもうこの映画の勝ちだな、と。
作中で、ルドルフが娘に読み聞かせするくだりで、何度か「少女が夜中に侵入してリンゴを隠して囚人に届ける」というシーンが挿入されます。これは実際にこんな行為をした人物がおり、「Zone of Interest」を覆す行動です。それが白黒のサーマルカメラで撮った演出になるあたりが、またも“ジョナサン・グレイザー”監督流の非日常演出ですが…。
自分が今どのゾーンにいるのか自覚し、別のゾーンで起きていることを想像できるか。
ユダヤ系の“ジョナサン・グレイザー”監督はアカデミー賞の授賞式で、イスラエルによるガザへの侵攻における非人間化に言及しました(The Daily Beast)。それに対して一部のユダヤ系の業界人たちがそのスピーチを非難する公開書簡に署名しました(Variety)。一方で、別のユダヤ系の業界人たちは逆にそのスピーチを支持する公開書簡で対抗を示しました(Variety)。
これこそ「Zone of Interest」。こんな時代の瞬間にこの映画が生まれたことは、やっぱり大きな意義があったのではないでしょうか。
ROTTEN TOMATOES
Tomatometer 93% Audience 78%
IMDb
7.5 / 10
シネマンドレイクの個人的評価
関連作品紹介
第76回カンヌ国際映画祭の受賞作の感想記事です。
・『落下の解剖学』(パルム・ドール)
・『PERFECT DAYS』(男優賞)
作品ポスター・画像 (C)Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. ゾーンオブインタレスト
以上、『関心領域』の感想でした。
The Zone of Interest (2023) [Japanese Review] 『関心領域』考察・評価レビュー
#アメリカ映画2023年 #ジョナサングレイザー #歴史 #ヨーロッパ史 #ドイツ史 #極右 #ホロコースト #ナチス #ユダヤ #優生思想 #カンヌ国際映画祭 #アカデミー賞作品賞ノミネート #アカデミー賞監督賞ノミネート #アカデミー賞脚色賞ノミネート #アカデミー賞国際長編映画賞ノミネート受賞