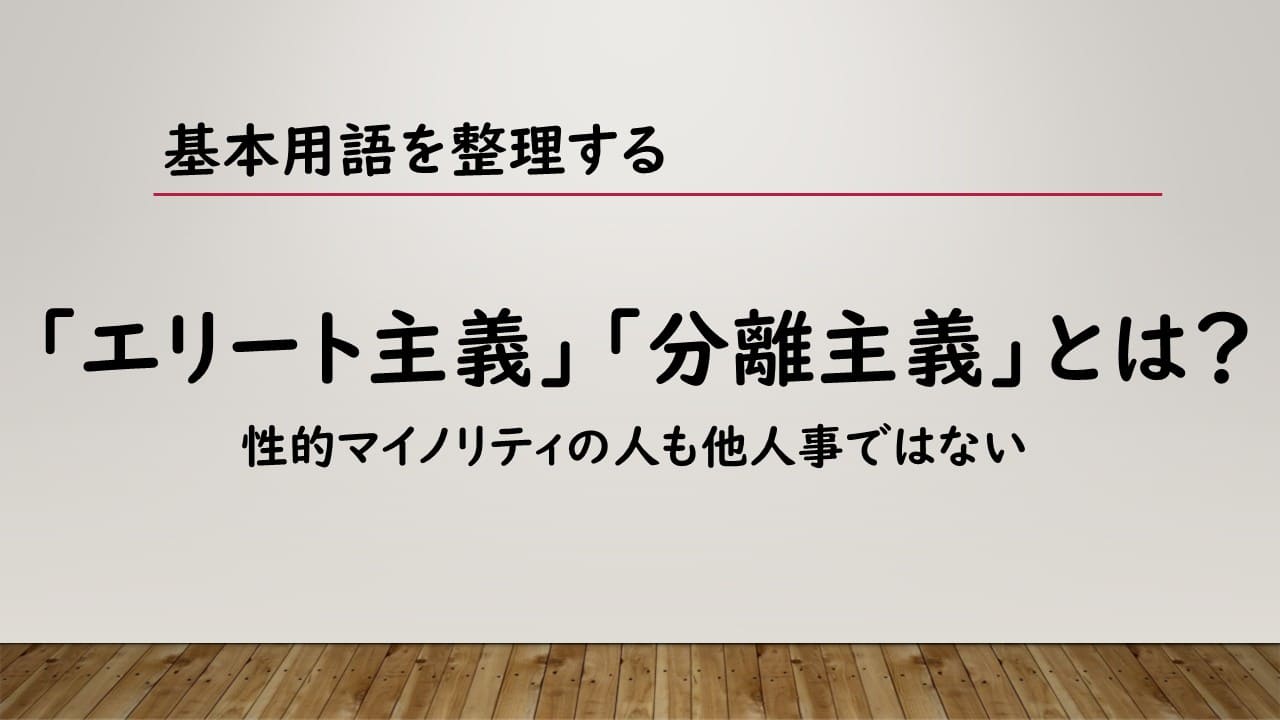今回は、性的マイノリティ(セクシュアル・マイノリティ)を論じるうえで、無視はできない「エリート主義」や「分離主義」についてまとめています。「エリート主義」や「分離主義」なんて聞いたこともないかもしれませんが、実はわりと多くの人が触れている概念です。
ではどういう意味で、どんな影響をもたらしているのでしょうか。
- 性的マイノリティのコミュニティにおける分離主義的な実践は、当事者のアイデンティティを可視化することに寄与し、世の規範を問い直す手段として機能もしてきた。
- エリート主義は、性的マイノリティのコミュニティから特定の当事者を排除しようという動きに繋がる危険性がある。
「エリート主義」とは?「分離主義」とは?
まずは「エリート主義」と「分離主義」という言葉の意味を確認しましょう。
「エリート主義」は英語で「Elitism」といいます。簡単に説明すると「ある特定の“選ばれし者”が“力”を持つべきである(もしくは標準であるべきである)という考えを前提とした態度や行動」のことです。何がどういう条件で“選ばれし者”なのか、それにどんな“力”を与えるのかは、それぞれの主張があります。
「分離主義」は英語で「Separatism」といいます。簡単に説明すると「ある特定の理由で、より大きな集団から分離するほうが良いという考えを前提とした態度や行動」のことです。どういう理由なのか、分離した結果、どんな形態となるのかは、それぞれの主張があります。
この「エリート主義」と「分離主義」は異なる概念ですが、よく重なり合いやすいものでもあり、エリート主義があるところには分離主義もたいていあり、その逆もしかりです。
「分離主義」はすべからく有害なものとはみなされていません。しかし、「エリート主義」は選民思想的もしくは排外主義的な思考を前提としていることが多く、分離主義とエリート主義の密接さはときに警戒される対象となってきました。
一方で、逆にエリート主義への批判は、「仮想上の“エリート”」を設定して、その「仮想上の“エリート”」が「私たちを脅かしている」という認識で、被害者意識ナショナリズム(犠牲者ナショナリズム;Victimhood nationalism)や陰謀論に直結してしまうリスクもあります。
性的マイノリティの「分離主義」
ではそんな「エリート主義」や「分離主義」は、性的マイノリティとどう関わってくるのでしょうか。
第一に、性的マイノリティの当事者たちはその性質や歴史に応じてさまざまなラベルを生み出し、用いてきました。「ゲイ」「レズビアン」「バイセクシュアル」「アセクシュアル」「トランスジェンダー」「ノンバイナリー」…他にもいろいろです。そういったラベルはさらなる細分化されたマイクロラベルへと繋がっています。
これは分離主義的な発想の実践であり、当事者のアイデンティティを可視化することに大いに寄与してきました。これは権利運動においてもとても大切なアプローチです。
また、「クィア・ナショナリズム」(Queer nationalism)という概念もあります。これは「性的マイノリティのコミュニティは、独自の文化と習慣によってそれ自体が固有の民族のような世界を形成している」という考えかたで、捉えかたのスケールの大小はあれど、各ラベルでコミュニティや文化を形成している実感は各当事者もあるでしょう(もちろん人それぞれで文化の帰属意識は違いますが…)。
別の例だと、「レズビアン分離主義」という概念も1970年代あたりから当事者の間で持ち上がりました。これはレズビアンの視点から男性中心社会や異性愛規範を見直す運動のいち形態であり、「レズビアン」という言葉を単なる「女性に惹かれる性的指向を持つ女性」というよくある定義の説明以上に拡大解釈して応用しています。
このように分離主義の実践は、当たり前とされてきた世の中の規範を問い直す手段として機能もしてきました。
性的マイノリティの「エリート主義」の問題点
このように性的マイノリティにおいて分離主義の実践は、根本的に「性的マイノリティ」という概念を意識づけるためにも非常に欠かせないものでした。
しかし、それがエリート主義にまで変貌すると、深刻な問題も生じさせることがあります。
最も目立つのは、性的マイノリティ全体から特定の性的マイノリティを排除しようとする潮流です。先例として、「LGBT」という言葉から「トランスジェンダー」を排除しようと画策する…いわゆる「Drop the T」と呼ばれる排外主義を試みる人たちがいます。これは反ジェンダー運動のいち形態です。簡略的に言ってしまえば「LGBT」を「LGB」に変えようとしているわけですが、性的マイノリティの権利運動の歴史の初期からトランスジェンダーの人たちが存在したという事実を抹消するものであり、極めて歴史修正主義的な運動でもあります。
また、この「Drop the T」の他にも、バイセクシュアル+の人たちやアセクシュアルの人たちを「LGBTQ+」から排除しようという言論も観察できます。これらも含めて「性的マイノリティを名乗れるのは“選ばれし者”だけだ」というエリート主義が透けてみえます。
さらに個別のラベル内部から特定の当事者を排除する事例もあります。
例えば、同性愛コミュニティであれば「同性同士とだけ恋愛や性的関係を持った人だけが“同性愛”(ゲイ・レズビアン)を名乗れるのであって、過去に一度でも異性と関係を持ったらダメだ」という考えかたです。人間関係という基準でもって「同性愛者の模範的な定義」を設定しようとしています。
アセクシュアルのコミュニティであれば、「“アセクシュアル”の言葉の定義は“他者に性的に惹かれないかほとんど惹かれない”なのであって、それに該当しない“惹かれなさ”を持つ人は“アセクシュアル・スペクトラム”なのであり、“アセクシュアル”という言葉はその意味で厳格に運用されなければいけない」という考えかたをする人たちもいます。
トランスジェンダーのコミュニティであれば、「性別適合手術など医療的処置を行った(もしくは行おうとしている)者だけが真のトランスジェンダーなのであり、そうでない人までを含めた権利運動などは“行き過ぎ”ていて、真のトランスジェンダーの当事者の立場をむしろ危うくさせる」という考えかたをする人たちがみられます。この考えかたは「トランスメディカリズム」(Transmedicalism)と呼ばれています。トランスメディカリズムを前提とする人はトランスメディカリストと呼称されますが、そうした人たちの中には、「性同一性障害」という診断名をアイデンティティとして強調する場合もあれば(その場合は「トランスセクシュアル」という言葉が従来的に使われてきたこともある)、本来は「トランスジェンダー」という言葉には「ノンバイナリー」やさらに多様なジェンダーの在り方を歴史的に保有する人々が包括されているにもかかわらず、そうした人々を排除する傾向にあったりします。
性的マイノリティにおけるエリート主義は、特定の人が「○○は“行き過ぎ”だ」と勝手に線引きしてしまうことで起きます。
そして、これらの個別のラベル内で観察できるエリート主義は、いわゆる「定義の誤謬」をレトリックとして持ち出すことが多いです。これは何かと定義ばかりで語って論破しようとする手口のことです。要するに、言葉の定義を絶対的な条件だと強迫的に認識し、それに該当しない者を除外することが、そのラベルの言葉で表されるアイデンティティの独立性を保護することだと主張します。それを「エンパワーメント」だと主張するかもしれませんが、実態としては相当に排外的です。
定義の誤謬に対応するには「良い定義の文を考えればいい」という話ではありません。この定義の誤謬はただの定義の“文章的な巧みさ”の問題ではなく、そもそもそのアイデンティティの複雑さを軽視していることがあるからです。
それを端的に指摘する言葉の代表例が「ホモナショナリズム」(Homonationalism)です。これはとくに西洋的な性的マイノリティの文脈において使われますが、性的マイノリティの受容に関する言説が、外国人嫌悪、イスラム嫌悪、あるいは人種差別的な政策を正当化するために利用されている側面を浮き彫りにさせるものです。例えば、欧米こそ性的マイノリティの権利に進歩的だと捉え、中東や中国・ロシアなど非欧米同盟国と歴史的にみなされてきた国々を、性的マイノリティの後進国と強調して他者化する行為がこれに当てはまります。
このホモナショナリズムはあくまで西洋中心の(欧米の特権意識を指摘するための)概念ですが、これを日本視点で概念化することもできるでしょう。例えば、欧米の性的マイノリティの文化はむしろ低俗・異質だと捉え、日本には日本の性的マイノリティの文化があり、そちらのほうが高尚で伝統的なものである…と強調する考えかたです。このケースだと「LGBTの概念は欧米的なものなのであって、日本には要らない」などと否定し、日本国内の差別を黙認・正当化するパターンが多いです。これはオリエンタリズム的な日本版ホモナショナリズムとも言えます。
先ほど紹介したレズビアン分離主義もエリート主義的な一面を批判されることがあります。白人女性中心的ゆえに人種の要素を無視しているといったこと、はたまたブッチ・レズビアン、AFABノンバイナリー、トランスジェンダー女性、インターセックス女性、バイセクシュアル女性、アセクシュアル女性などの排除などです。こちらはレズビアン版のホモナショナリズムといった感じでしょうか。
インターセックスのコミュニティでも、インターセックス当事者内の他の性的マイノリティの人の存在を過小評価する主張が観察できることがあります。実際は、インターセックスの当事者と、性的指向や性同一性のマイノリティの当事者は重複する割合が高く、また社会における問題も共有するところも多々あります。
連帯と交差性を意識して…
以上、ざっくりですが説明してきた性的マイノリティのエリート主義の問題は、性的マイノリティの分離主義の功罪です。
だからといって「分離主義はよくないんだ。ラベルなんて無くなればいいんだ」とか、そういう極端な話をしているわけではありません。どうバランスをとっていくかという話です。
分離主義ありきにならないように欠かせないのが「連帯」と「交差性(インターセクショナリティ)」の実践です。
「LGBTQ+」なんて言葉があるのも連帯の重要性を強調するためのものですし(ただの頭文字ではありません)、人種・民族・宗教・障害などの交差性を意識することは大切です。これらはそもそもの現実の複雑さが個々の分離主義の加速的な実践の中で除去されないようにするために必須といえるでしょう。
性的マイノリティの中にも、いろいろな人種の人がいる…いろいろな民族ルーツの人がいる…いろいろな宗教を信仰している人がいる…身体や精神の障害を抱えている人がいる…進学や就職の状況も違っている…家族や友人との関わり方も異なっている…。すごく複雑です。
性的マイノリティだからといって必ず「こうである」という前提はありません。特定の教養を持っていないといけないわけではないし、アクティビズムをしないといけないわけでもない。自分で自由に自己のありかたを決められるし、そうであるべきです。
今回の「エリート主義」と「分離主義」の問題は、性的マイノリティにかぎらず、あらゆるマイノリティに当てはまるものです。
「マイノリティ」という言葉は「マジョリティ」と対義的に用いられやすいので、何かと二項対立を印象づけやすいですが、「差別される側」と「差別する側」に単純に二分されるわけではありません。何度も言いますがとても複雑な構造の概念です。これを忘れるとマイノリティの語りが「誰が一番可哀想か」という陳腐な同情合戦になってしまいます。有害な被害者意識ナショナリズムを煽るだけにもなるでしょう。
何が「マイノリティ」かを認定する機関や仕組みは存在しません。私たち人間社会は、文化的・社会的・政治的・歴史的な文脈で合意(コンセンサス)をとりながら、マイノリティを認識し、平等を模索してきました。その合意の大前提にあるのは「この世のあらゆる人には無条件で人権がある」という考えです。
分離主義的な言説が(当人が認識しているかどうかを問わず)特定の一部の人による主張・先導でゲートキーピング状態にあると、何かとエリート主義の問題が浮上しやすいように感じます。だからより多様な人たちが人権の視座を揺るがずに参画することが大切です。
“選ばれしマイノリティ”なんて存在しませんし、ましてや“選ばれしマイノリティ”になるのが目的じゃない…みんなの人権が守られる世界を築くことが「マイノリティ」という言葉の社会に訴える役割だと思います。