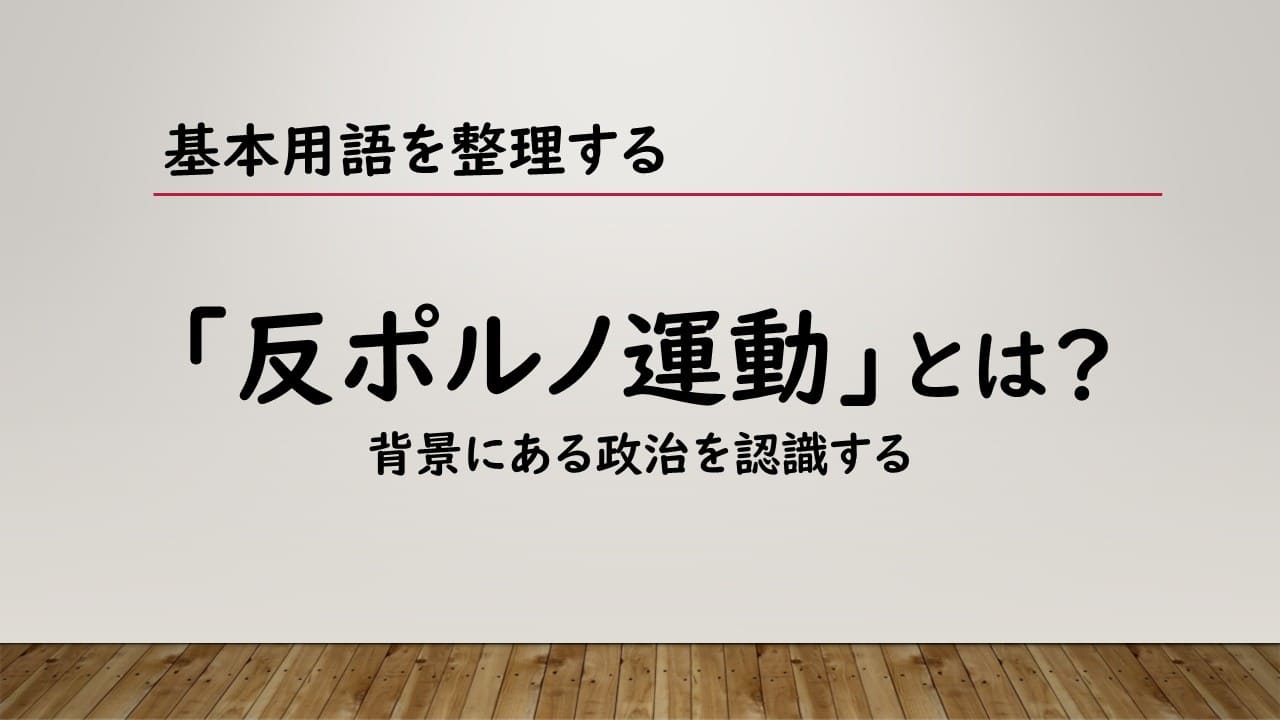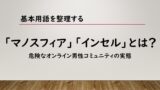今回は、何かと日本のネット上でも話題になりがちなアダルトコンテンツ規制と深く関連がある、「反ポルノ運動」についてまとめています。「エッチなものを禁止したがる感情的な人たち」とか「性的なものへの過剰な拒絶反応」なんて認識の人もいるかもしれませんが、実はもっと政治的な背景と歴史があります。
ではどういう運動で、どんな歴史があるのでしょうか。
- 反ポルノ運動は1970年代から保守的な政治と密接な関わりがあり、2020年代はさらに勢いを増している。
- 日本では反ポルノ運動に対する認識が非政治化されてしまっており、捻じれた誤解が助長されている。
「反ポルノ運動」の歴史
さっそく歴史を簡単に整理していきたいと思いますが、ここでは欧米(とくにアメリカ)を中心とした反ポルノ運動について主に焦点を絞っています。
1970年より前の重要な判決
アメリカにおいて現代に繋がる反ポルノ運動が沸き起こったのは1970年とされています。これは「宗教右派」が旺盛となった時期と一致し、1970年代からの反ポルノ運動の先導者は紛れもなく宗教右派でした(「宗教右派」の意味と歴史については以下の記事を参照)。
しかし、この1970年代にいたる前に、アメリカにおけるポルノと規制をめぐる大きな変化があり、これを語らないわけにはいきません。
それが1969年の「スタンリー対ジョージア州(Stanley v. Georgia)」の合衆国最高裁判所の判決です。
アメリカでは政治的に保守的な人々は宗教的な価値観ゆえにポルノに反対する傾向があり、一部の州ではポルノ絡みの行為を違法としているところも当時はありました。都合がいいことに、1957年に「ロス対アメリカ合衆国(Roth v. United States)」という最高裁判所の判決がありました。これはニューヨーク・シティにてアダルト書籍販売業を営んでいたサミュエル・ロスが郵便で「猥褻(わいせつ)、卑猥、好色または下品な(obscene, lewd, lascivious or filthy)」資料を送ることを犯罪とする連邦法に基づき有罪判決を受けたことに端を発します。
論点は「そもそも何が“猥褻”なのか」、そして「“猥褻”という理由で違法にすることは憲法修正第1条(表現の自由や言論の自由)に反しないのか」ということです。
従来は慣習として「ヒックリン・テスト」というものが用いられていました。これは1868年のイギリスの判例で確立されたもので、「不道徳な影響を受けやすい人々を堕落させ、腐敗させる傾向のあるすべての資料は、芸術的または文学的価値にかかわらず、猥褻である」と判示していました。
1957年の「ロス対アメリカ合衆国(Roth v. United States)」はあらためてアメリカでの法的な解釈を決定するものになりました。結果は「猥褻」の定義をやや狭め、「支配的なテーマが全体として平均的な人の好色な関心に訴える」という条件を定義し、一方でこの条件に該当する「猥褻」なものは憲法修正第1条によって保護されていないことを確認し、有罪判決を支持したのでした。
ポルノに反対する保守派の人たちは「猥褻」の定義が狭まったことには不満を示しましたが、猥褻物を違法にできる法的根拠は得られたので、堂々とポルノを規制できていました。
そして話は1969年の「スタンリー対ジョージア州(Stanley v. Georgia)」の合衆国最高裁判所の判決に移ります。
これは、ジョージア州アトランタ在住のロバート・イーライ・スタンリーが賭博の容疑で、自宅捜索され、賭博の証拠は見つからなかったものの、代わりに8ミリフィルムのポルノを発見され、ジョージア州法で違法とされていた猥褻物の所持で逮捕された…という事案です。
そして裁判の結果、「猥褻物の単なる私的所持は憲法上の犯罪とはなり得ない」と判断するという画期的な裁決をしたのでした。当時の判事のひとりはあの公民権運動で大きな実績のある“サーグッド・マーシャル”であり、彼は「もし憲法修正第一条に意味があるとすれば、それは、州が、自宅に座っている個人に対して、どのような本を読み、どのような映画を見るべきかを指図する権限を持たないということである」と多数意見で述べました。
こうして、公的と私的を切り分け、私的なポルノの所持や利用は保護されることになったのですが…。
1970年代~1980年代の宗教右派の反撃
この1969年の「スタンリー対ジョージア州(Stanley v. Georgia)」の合衆国最高裁判所の判決に激怒したのが、当然ながら保守派の人たちです。
ただ、もうすでに最高裁の判決があります。これを覆すことはできずとも、ポルノ規制に持ち込むにはどうやればいいか。「ポルノは非行や犯罪行為を誘発する!」と有害性をひたすら強調するしかありません。
そこで当時に反ポルノ運動を率いる中心的人物のひとりとなったのが“モートン・A・ヒル”という神父です。彼は1962年から「Morality in Media」という活動を立ち上げ、ポルノ撲滅に生涯を捧げていました。彼は牧師である“ウィンフリー・C・リンク”と共に、「ヒル・リンク報告書」を発表し、ポルノがいかに有害かを書き連ねました。当時から主流の研究者は「ポルノが犯罪を助長するという科学的な根拠は見当たらない」とする意見が多く、その意見を記した多数派の報告書もまとめられたのですが、なぜか共和党の“リチャード・ニクソン”大統領はその主流の報告書を無視し、「ヒル・リンク報告書」を採用してしまいます。
そして1981年から大統領となった共和党の“ロナルド・レーガン”がポルノ規制に精力的に乗り出し、”モートン・A・ヒル”はレーガン政権のポルノ対策に影響力を持つようになりました。
宗教に始まりを持つ反ポルノ運動が保守的な政治と密着化した瞬間です。
1986年にレーガン政権はポルノの有害性をまとめた「ミース報告書」を発表し、「ポルノ=有害である」という主張は政治的な根拠(科学的ではない)を得ました。
反ポルノ・フェミニストの出現
さらに同時期、別の勢力がこの反ポルノ運動を後押しします。
それが「ラディカル・フェミニスト」と呼ばれる人たちです。
誤解のないように先に書いておくと、「フェミニスト=反ポルノ」というわけではありません。フェミニストの一部に反ポルノを掲げる人が出現したということです。また、ひとくちにラディカル・フェミニストによる「反ポルノ」と言っても、「一般的なポルノにおける男性中心的な構造を批判する人」「特定のポルノの部分的な規制を訴える人」「あらゆるポルノの全面禁止を訴える人」など、その主張には極めて幅があります。
とにかく1970年代から反ポルノのラディカル・フェミニストたちに「Women Against Pornography(WAP)」といった活動団体を立ち上げたり、勢力を増しました。“アンドレア・ドウォーキン”など著名な反ポルノのラディカル・フェミニストがその中心にいました。
一方で、セックス・ポジティブなフェミニストたちもいて、そのフェミニストは反ポルノのラディカル・フェミニストと対立し、当時のフェミニズムを分断して二極化させる論争に発展しました。これは「フェミニスト・セックス戦争(ポルノ戦争)」と呼ばれています。この分裂は、第二波フェミニズムの終焉であると同時に、 1990年代初頭に始まった第三波フェミニズムの先駆けともなったと分析されることもあります。
反ポルノのラディカル・フェミニストの政治的立場はとても曖昧かつ流動的で、ときに左派、ときにリベラル、ときに保守、ときに右派だったりします。ただ、当時のアメリカの反ポルノのラディカル・フェミニストたちは、前述したレーガン政権によるポルノの有害性をまとめた「ミース報告書」にも深く関与し、間違いなくその時代の保守的な政治と一体化していました。
トランプ政権と反ポルノ・レトリックの拡張
1970年代から1980年代にかけて政治と一体化した反ポルノ運動ですが、2010年代後半から2020年代にかけて、また新しいフェーズに突入し始めました。
それは“ドナルド・トランプ”政権の出現です。
“ドナルド・トランプ”本人はとくに反ポルノを志してはいないですが、“ドナルド・トランプ”を絶大に支持する地盤を形成しているのは宗教右派です。“ドナルド・トランプ”が勢いを増せば、宗教右派も勢いを増し、当然、反ポルノも活気づきます。
右派シンクタンクとして有名な「ヘリテージ財団」が大統領選挙時に掲げた「Project 2025」というマニフェストでは反ポルノが盛り込まれました。副大統領の“JD・ヴァンス”を始めとする宗教右派系の政治家たちは「コムストック法」の復活を示唆しています。これは猥褻物を取り締まる1873年の法律なのですが、中絶や避妊に関する情報も猥褻物扱いとなり得る極めて反ポルノに都合がいい法律です。
つまり、反ポルノというのは、単純に「ポルノ」に反対するだけでなく、「権力が気に入らない人物や概念」を規制するのにうってつけとなっています。
例えば、LGBTQ(とくにトランスジェンダー)の権利運動、または多様性への取り組みを、「ジェンダー・イデオロギー(トランスジェンダリズム)」や「woke」などといって危険な過激思想扱いで規制しようと試みるのも、反ポルノのレトリックを応用しています。「子どもたちを守れ」という名目はまさに1970年代から繰り返されてきたことです。反ポルノ運動は反セックスワーカーであり、反LGBTQであり、反多様性と地続きです。
これはアメリカのみならず、影響力は甚大で、世界に波及し、反ポルノ運動を活性化させています。
例えば、決済処理会社(クレジットカード企業)へのロビー運動が象徴的です。1970年代の反ポルノ運動で先頭に立った「Morality in Media」が改名した組織「National Center on Sexual Exploitation(NCOSE)」、さらにはオーストラリアの保守派政治活動家にして反中絶&反ポルノのフェミニストである“メリンダ・タンカード・レイスト”によって設立された「Collective Shout」などが、そのロビー運動の背後にいます。このロビー運動によって、大手ポルノサイトで活動できなくなったセックスワーカーや、ゲームストアから排除されたLGBTQ作品がでてしまっています(CBC)。
日本における反ポルノ運動への誤解とミスリード
ともあれ、前述したような政治的な背景がある反ポルノ運動。
ところが、日本では反ポルノ運動に対する捻じれた誤解が目立つように思います。
どうしても日本の大衆の認識を観察していると、反ポルノ運動を、お母さんが「こんな破廉恥なものを見ちゃダメです!」と大騒ぎしてポルノを取り上げようとするやたら陳腐なイメージでしか捉えておらず、これが政治運動だとみなせていない感じです。「エッチなのはよくない」みたいな一部の「エロを理解できない分からず屋」の感情的な問題だとしか思っていないような…。
そのうえ、輪をかけてこの状況を率先して混乱させているのが、日本の一部の政治家です。アニメや漫画のオタク層から強い支持を受けているこれら政治家は、「フェミニズムやポリティカル・コレクトネスがエロ表現を規制しようとしている!」という主張を展開し、それが諸悪の根源であるかのように訴えています。
すでに説明したとおり、フェミニズム(と称するも実際は保守的な政治活動の一環)の一部が反ポルノ運動に加担しているのは事実ですが、大本は政治運動です。ましてや「ポリティカル・コレクトネスがエロ表現を規制しようとしている」事実はなく、そもそも真逆で、普段から「これはポリコレだ!」と敵視を煽っている保守系の勢力が反ポルノの中心にいます。
これでは認識が捻じれ、あげくにはミスリードで反転してしまっています。そのうえ、反ポルノ運動の中心にいる保守系の勢力への批判の機会が失われてしまっています。皮肉なことに反ポルノ運動をオウンゴールでアシストしているも同然です。
なぜこうも捻じれたのか、その原因はわかりませんが、日本における「対“反ポルノ運動”」の勢力が、すっかりマノスフィア化してしまっているのは実態として確認できます。「俺たちの好きなエロを、うるさい女どもから守れ!」程度の集団です。インセルなトキシック・ファンダムから支持を得て政治権力にしたい人たち(アニメや漫画の表現の自由を守るべく現れたヒーローとしてもてはやされる)にはそれが居心地いいのかもしれませんが…。
本来、世界の「対“反ポルノ運動”」は人権を視座に、多様な性文化に携わる労働者を保護し、ポルノ規制が「権力が気に入らない人物や概念」を悪魔化して排除することに悪用されないように監視するものです。もちろん、それは同時に表現や言論の自由も守ることと一体化しています。
「自分の好きなもの、関心あるものだけ守りたい」では、反ポルノ運動には対抗できません。
そしてやっぱり政治に関心を持ち、どんなものにでも無縁ではない政治的な力場を自覚することが何よりも大切です。
関連性のある他の特集記事の一覧です。