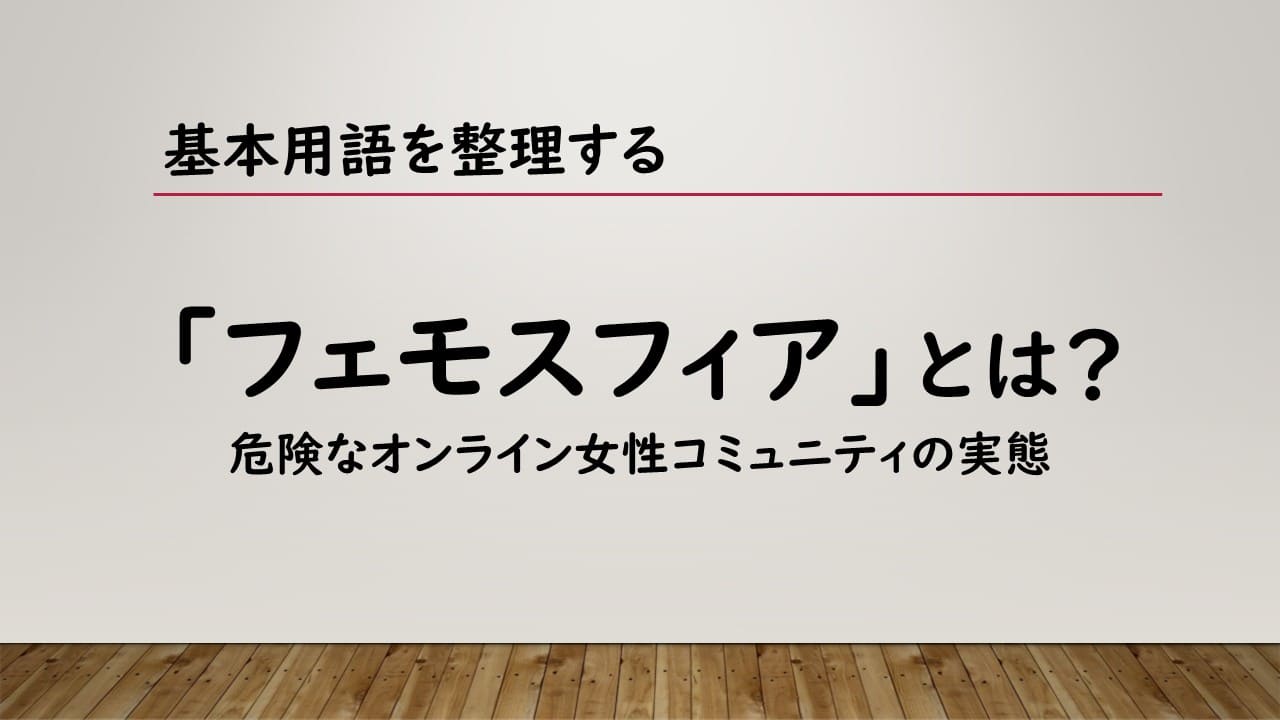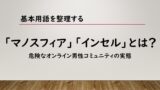以前に「マノスフィア(manosphere)」という言葉を紹介しました。
マノスフィアは「女性蔑視と結び付けられる男性中心のオンライン・コミュニティ」と一般に説明されます。
一方で、そんなマノスフィアの女性版とも言えるのがこの「フェモスフィア(ウーマノスフィア)」です。
今回は「フェモスフィア(ウーマノスフィア)」について、簡単にですが、その意味を整理していきたいと思います。
- フェモスフィアは、フェミニズムやジェンダー平等を全否定もしくは一部否定し、有害な女らしさを推進している。もしくは「女性を守る」という名目でマイノリティの排除を主張している。
- オンライン女性コミュニティとして発達するフェモスフィアにも、さまざまな形態や種類がある。
「フェモスフィア」とは? その形態の種類
「フェモスフィア」とは英語で「femosphere」と書きます。「ウーマノスフィア(womanosphere)」という別名もあります。いずれも「fem(女性)」もしくは「woman(女性)」に、接続詞「o」、そして「sphere(球体)」を組み合わせた言葉です。
フェモスフィアは、ラフバラー大学のフェミニスト・メディア・文化研究を専門とする“ジリー・ボイス・ケイ”による造語で、2024年に論文で発表されたばかりの、比較的新しい用語です。
マノスフィアの女性版と捉えれば、意味をひっくり返せば「男性蔑視と結び付けられる女性中心のオンライン・コミュニティ」と説明できそうですが、単純に「男が嫌いな女たちの集団」というわけではありません。
前述の“ジリー・ボイス・ケイ”は、大衆文化における「反動フェミニズム」の台頭を指摘しています。これはリベラルなフェミニズムへの反発の高まりから生じ、近年の新自由主義およびポストフェミニズムから離脱または変容し、独自の「この社会で女性はこうあるべきだ」という論理を振りかざすようになったものです。
フェモスフィアでも、やはり一様ではなくさまざまな形態や種類があるのですが、だいたいに共通する特徴があります。主に以下のような特徴が挙げられます。
- 女性中心で成り立っている
- 有害な女らしさを推進している
- ジェンダー本質主義や反“多様性”を内面化している
マノスフィアは「有害な男らしさ(トキシック・マスキュリニティ)」を推進していましたが、フェモスフィアは「有害な女らしさ(トキシック・フェミニティ)」とも言うべき概念を推進しています。
男性(の権力)に批判的であり、男尊女卑の社会を自覚していることもありますが、ジェンダー平等を信じていません。「“男”とは本質的にそういうものである」と半ば諦め、「そうした“男”と距離をとるか、上手く付き合うこと」が「今の女性の最も適切な人生選択」であると考えています。
つまり、「男と女は全く異なるものなのだから」という前提で、ジェンダー本質主義を強く内面化しているとも言えます。
そして、リベラルなフェミニズムは、理想主義的すぎるとみなすか、分断を深めるだけだと見放し、「女性の立場」を守るために、平等や多様性に反対する姿勢が根深いです。
フェモスフィアも特定の組織名を指すわけではなく、上記で挙げた思考でときに漫然と集団化したオンラインに存在するコミュニティです。同類の考え方の仲間たちだけで狭いオンライン空間に閉じこもることで、エコーチェンバー現象によって特定の思考がより増幅されています。こちらも、政治家・学者・有名人・インフルエンサーのような影響力を持つ一部の女性を中心に群がり、支持者集団を持続することがあります。
では具体的なフェモスフィアの形態や種類を以下に整理していきましょう。いくつかに分類することができます。
トラッド・ワイフ
「トラッド・ワイフ(tradwife / trad wives)」、簡単に言うと現代において伝統的な性別役割分担と結婚生活を信じ、実践する女性のことです。
そういうスタイルの実践をしている女性は昔の時代には大勢いたでしょうが、それら昔の女性を指してこの言葉を用いることはしません。このトラッド・ワイフは、ジェンダー平等が目指すべき姿とされるこの現代の「今」に、あえて伝統的な女性というスタイルを実践することに意義を感じている女性たちです。
オンライン文化に溶け込んで活動しており、「#tradwife」というハッシュタグを駆使するなどして、動画コンテンツなどで、伝統的な女性というスタイルの実践の「クールさ」を常にアピールしています。
トラッド・ワイフは、「女性が職場で働く」ということに強く反発しています。その反発の感情の背景の一部には、「企業などで強いリーダーになる女性こそが素晴らしい」という安直なガールボス的な概念への拒絶もあります。
しかし、トラッド・ワイフは女性の家事を奨励しており、家事も労働(しかも無給)であるということに関しては、見て見ぬふりをすることが多いです。
また、妻は経済的に男性である夫に依存するべきという考えを信念にして公然と表明していますが、先ほども説明したとおり、多くのトラッド・ワイフはインターネット・コミュニティ内でインフルエンサーとして、多くのフォロワーを獲得し、中には商品販売やタイアップなどで収益を上げている女性もいるため、こちらも自己矛盾を抱えています。
他にも、子を産むことを奨励しており、「産む身体」を健康的に維持し、「産む能力」を育むノウハウを提供しています。そういう意味では、出産促進のフェムテックとの相性は抜群です。
「良妻賢母」をネット上の「バズる」アイコンとして消費する保守的なフェミニズム…という感じでしょうか。
「Evie」といったオルタナ右翼の女性誌をみると、その価値観は一目瞭然です。主なトラッド・ワイフ的な女性としては、“エリカ・カーク”(The 19th)などが挙げられます。
ダーク・フェミニン
「ダーク・フェミニン(dark feminine)」は、男性に依存するスタイルの実践という点では、トラッド・ワイフと同じですが、こちらは「伝統」を重視していません。
女性に経済的支援をしてくれる男性を見つけることを奨励することを基本としています。要するに、家族や恋人という関係にこだわらず、とにかく男からおカネをもらって生きていこう…という考え方です。
そのために、そうした狙い目となる男性をいかに見つけ、いかに関係を持つかという、女性向けのデート戦略を解説したりしています。
ダーク・フェミニンにとってすれば、経済力のない男性は「価値が無い」とみなされ(つまり大半の男性には価値は無い)、逆に経済力のあるひと握りの男性を称賛します。
また、女性は「男性に惹かれるため」に存在しているのであり、その生まれながらの役割を活かせばいいと助言します。こうして「より美しくなる方法」「お金持ちになる方法」「極めて魅力的になる方法」といった見出しのコンテンツで、困窮する女性を惹きつけ、支持者へと変えます。
著名なダーク・フェミニンのインフルエンサーとしては、“カニカ・バトラ”などがいます。“カニカ・バトラ”は、「第三波フェミニズムは女性に男性的な役割を押し付けてきた」と持論を語っています(The Guardian)。
このダーク・フェミニンが主軸とする「女性向けのデート戦略(Female Dating Strategy;FDS)」は、ジェンダー平等な男女関係を見放しており、例えば、Redditから生まれ、ムーブメントとなったFDSのウェブサイトが作成したハンドブックには「家父長制に復讐する最良の方法のひとつは、男性にあなたの愛情をめぐって競争させることだ」と書かれています。
“ジリー・ボイス・ケイ”はこのダーク・フェミニンを象徴する考え方を「徹底的に非敗北主義的な個人的態度を伴う根深い政治的宿命論」で「政治的構造変革を求めるユートピア的願望が否定され、代わりに超個人主義的な戦略に取って代わられる、反希望的な感情」と表現しています。
フェムセル
「フェムセル(femcel)」は、マノスフィアのひとつである「インセル(incel)」の女性版です。
そもそもインセルの言葉自体は当初は男性に限定されていませんでしたが、今や有害な男性中心のコミュニティに愛用されてしまっています。そこで女性を扱う際にフェムセルという言葉が必要になりました。
こちらも意味としては、「恋愛や性的パートナーを望んでいるにもかかわらず見つけることができない女性たち」という感じで共通しています。
当初は「どうして私ってモテないのかな…」という寂し気な孤独感を象徴する言葉でしたが、その内向的なコミュニティによって特徴付けられていた地味な状況はしだいに変貌。今ではTikTokなどのプラットフォームを支配するトレンドになるケースもあります。
“ジリー・ボイス・ケイ”は、フェムセルはインセルと同様に、いわゆる「ヘテロニヒリズム」の象徴で、これは「ニヒリズム、反動主義、反政治的な気分が、否定的な異性愛体験とますます絡み合い、それを通して表現され、過激化していったもの」と説明しています(European Journal of Cultural Studies)。
フェムセルは、何かと外に敵対感情を向けるインセルと違って、内向きの憂鬱、苦悩、悲観、そして自分自身に焦点を当てた怒りを表に出す傾向があります。一方で、一見すると目立たたないフェムセルが、密かに他者への排外主義を示す傾向も観察されており、とくに(後述する)トランスジェンダー排外主義との重複が指摘されてもいます(WebSci)。
TERF(ジェンダー・クリティカル)
「TERF(ターフ)」とは「trans-exclusionary radical feminism」の頭文字をとったもので、直訳すると「トランスジェンダー排除的ラディカルフェミニスト」となります。「ジェンダー・クリティカル(gender-critical)」という呼び方もされます。
なお、「“TERF”は差別用語だ」という主張もTERFと呼ばれる当人たちから発せられることもありますが、その当人たちの一部は一方でTERFという言葉をノリノリで自称して使っていることもあるので、典型的な被害者態度とも言えます。
結局のところ、フェミニズムを掲げながら反トランスジェンダーの立場をとる人たち…という意味合いだと思ってもらえればいいでしょう。
TERFの姿勢は端的に言えば、「トランスジェンダー女性は“真の女”ではない、あれは男だ」という、性別二元論のジェンダー本質主義で一貫しています(Transgender Studies Quarterly)。そして、ノンバイナリーは性的マイノリティになりたがっている人たちによる安易な流行にすぎず、インターセックスは哀れな身体障害者だとみなしています。
TERFは女性の定義に執着し、「絶対的に不可侵で不変の定義がある」との考えにこだわります。TERFにとっては、女性は「XXの性染色体がある」や「卵子を作り出せる器官がある」といった、限定的な性的特徴で定義を行います。大昔の(女性蔑視な)男性の学者が論じていた女性の捉え方とほぼ同じです。
こうした主張は、単にトランスフォビアというだけでなく、女性差別、民族差別、障害者差別などを背景に持ち合わせていますが、TERFは「これは差別ではない。生物学の真実だ」と反論します。当然、生物学における性別の複雑さには関心はありません。
TERFという用語は、フェミニストのブロガーである“ヴィヴ・スマイス”が2008年に広めたとされています。しかし、そもそもフェミニズムの界隈で、トランスジェンダーが論点として対立軸の槍玉にあげられた最初の事例は、“ジャニス・レイモンド”の著書『The Transsexual Empire』(1979年)だと言われています(The Sociological Review)。その書籍にて、トランス女性は「女性の空間に侵入し女性の身体を盗用する暴力的な男性主体」として一方的に位置づけられました。まさに1970年代は一部のレズビアン・コミュニティ内からトランス女性が排除された時期でもありました。
TERFはトランスジェンダーを敵視することで団結しており、トランスジェンダー(およびその権利運動)は「女性の抹消」に繋がり、「レズビアンを脅かす」と、持論を掲げています。
「女性を守る」という名目の(実際は「反トランスジェンダー」を目的とした)女性団体はあちこちで組織され、“J・K・ローリング”のような億万長者が資金サポーターとなっています。
TERFはこれまではリベラルなフェミニズムの極端な先鋭化として分析されることが多かったと思いますが、フェモスフィアの一部として分析すると違った背景が見えてきます。
他のフェモスフィアの形態と同じく、TERFも「#JKRLadiesLunch」や「#RespectMySex 」などのハッシュタグを仲間内で好んで用い、オンライン上でのアピールを欠かしません。
フェモナショナリズム
「フェモナショナリズム(Femonationalism)」は、「女性を守る」という名目で、人種差別や移民差別を主導し、排外主義を推進する概念です。
社会学者の“サラ・R・ファリス”の2017年の著書『In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism』によってその言葉は知られるようになりました。
例えば、「移民を受け入れれば女性への犯罪が増える」、「イスラム教は女性差別的なので容認できない」といった主張を展開します。
“サラ・R・ファリス”は「ナショナリストがフェミニズムを道具として利用している」と説明し、その扇動者には「フェモクラット(femocrats)」と呼ばれる女性の政治的リーダーが大きく関与していることを指摘しています(openDemocracy)。
「フェモスフィア」の歴史
女性たちが「女性を守る」ために世の変化を拒絶し、退行的・反動的な勢力に与して、活動を精力的に行い始めたのは、新しい現象ではありません。
インターネットがまだなかった時代、フェモスフィアに類似する存在はいくらでもありました。
1970年代にアメリカでは男女平等修正条項に反対するべく、“フィリス・シュラフリー”は保守的な女性集団を組織しました。70年代後半には、“アニタ・ブライアント”は「子どもたちを同性愛者の魔の手から守る」ために、率先して反同性愛運動の旗頭となりました。
2020年代に本格的に出現したフェモスフィアは、それら過去の潮流に紐づいています。
しかし、現代だからこその構造もあります。
フェモスフィアの言葉を造り出した“ジリー・ボイス・ケイ”は、「反動フェミニズムは、大衆文化や政治文化における“リベラル”、“進歩主義”、“ガールボス”なフェミニズムを公然と拒絶する広範な潮流の一環である」と分析しており、「この現象はフェミニストによる新自由主義やポストフェミニズム批判に似ているように見えるかもしれないが、社会正義の拒絶、根深くトランスフォビア的なジェンダー本質主義、そして解放主義フェミニズムへの敵意に基づいている」と解説しています。
要するに、皮肉なことに既存のフェミニズムの問題点を批判する真っ当な言説が、パンドラの箱を開けてしまうかのように、より反動的な潮流を刺激してしまったとも言えるかもしれません。
今やフェモスフィアは、オンライン文化の花形です。“ブレット・クーパー”、“キャンディス・オーウェンズ”、“アリー・ベス・スタッキー”、“ライリー・ゲインズ”といった、女性インフルエンサーはネットコンテンツを大量に生み出し、不安定な社会の中で自己を見失って彷徨っている若い女性たちをフェモスフィアの沼に誘っています。
無論、世界各国の政治の世界で存在感を発揮する保守系の女性たちも、フェモスフィアの中心人物なのは言うまでもないです。
「フェモスフィア」と「マノスフィア」の関係
ところで、このフェモスフィアとマノスフィアはどういう関係なのでしょうか。
部分的には相容れないこともあります。フェモスフィアがマノスフィアを批判することもあります。
しかし、保守的な役割を受け入れて男性に従うトラッド・ワイフは、マノスフィアと相性がいいです。また、ダーク・フェミニンも、マノスフィアを否定せず、それに乗っかろうとしてしまっているので、共存関係を構築しています。彼女らなりの家父長制への適応です。
TERFは公に堂々とマノスフィアを支持しませんが、トランスジェンダーに反対するという点ではマノスフィアと結果的に言動を一致させ、反ジェンダー運動の欠かせないパートナーシップとなっています。フェムセルはそんなTERFに隠れながら劣等感をくすぶらせています。
同一ではないものの、相互補完的な関係と言えるのかもしれません。
フェモスフィアとマノスフィア、この両者を合わせて眺めていると、現代は「右派vs左派」の時代ではとうになくなったと実感します。もはや「究極的な個人主義同士の乱戦」です。
どんなイデオロギーであろうと、レトリックであろうと、陰謀論であろうと、インターネットの世界で注目を浴びるために利用し、頂点に立てたほうが「勝ち」という世界になってしまいました。
これからは政治スペクトラムよりもオンラインの力場と構造を分析することが、より重要なのかもしれません。フェモスフィアはまだまだ新しい分析の視点ですが、今後も無視できない論点となるのではないかと思います。