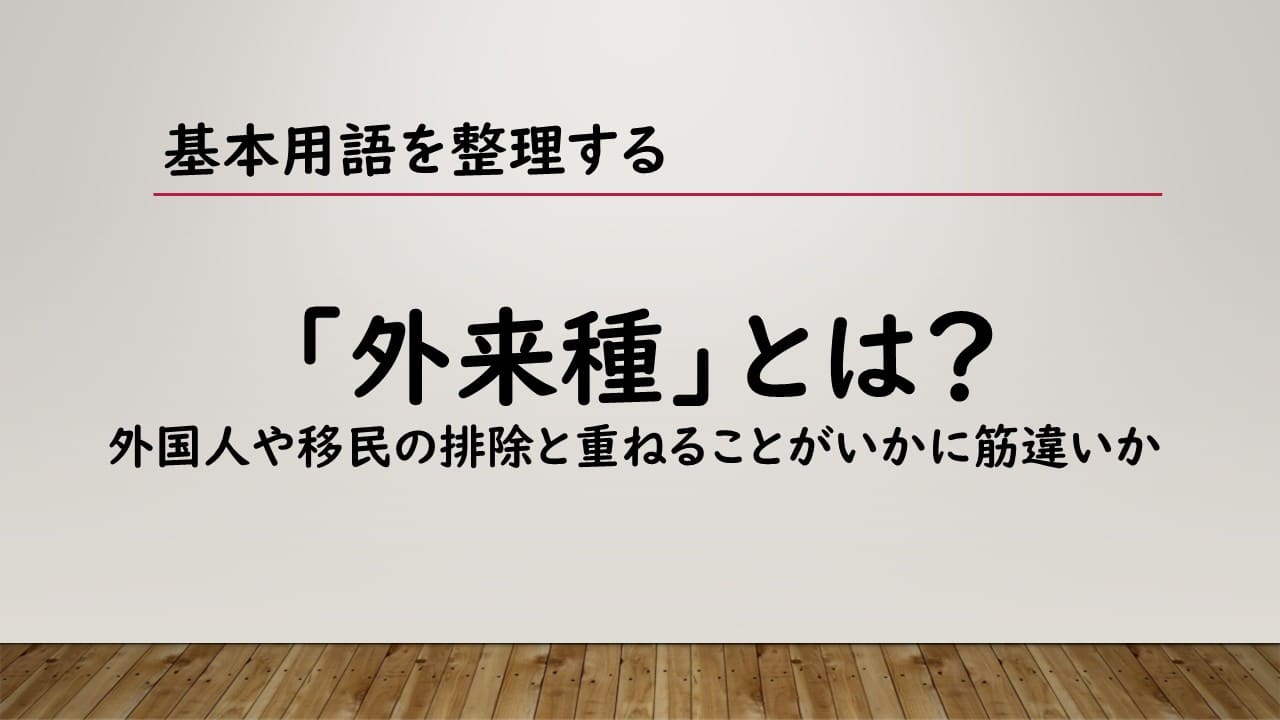「あらためて考えてみる基本用語」のシリーズ記事。
今回は「外来種」という用語をとりあげます。
生物学の用語ですが、一般にも浸透した言葉です。しかし、この言葉について科学的に適切な理解が広まっているとは言い難い光景もみられます。
例えば、近年はこの「外来種」という言葉を持ち出して、外国人や移民を危険視したり排除する説明材料に用いている事例があります。
この用法は「外来種」という言葉の意味を理解せずに誤って用いている典型的なパターンです。
では何がどう意味を間違えているのでしょうか。
そこで今回はこの「外来種」についてもっと掘り下げてみましょう。
- 「外来種」という言葉は、「海外からやってきた生き物」などと意味が誤解されていることが多々あります。
- 「外来種」という言葉は一部で、外国人や移民に対する排外主義のレトリックの道具にされていますが、そういた使い方は科学的にも間違いであり、倫理的にも不適切です。
「外来種」という単語の意味
「知っているよ。“外来種”って“海外からやってきた生き物”のことだよね」
この認識はよくある間違いです。
まず「外来種(がいらいしゅ)」という単語の基本的な意味を整理しましょう。
意味の前に押さえておきたいのは「外来種」という言葉のバリエーションの多さです。
「外来種」は日本語だと「外来生物」や「移入種」という呼び方をすることがあります。農業や園芸など植物の業界だと「帰化種」という呼び方もありますが、最近は「外来種」や「外来生物」で統一される傾向が目立ちます。例えば、日本の環境省は「外来種」という表現を用い、法律では『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』(略して『外来生物法』)の名称のとおり、「外来生物」の表現を使っています。農林水産省などでは「帰化植物」のように植物を対象としたときだけ慣習的に「帰化種」の表現を今も用いています。
英語もいろいろな表現があって、「introduced species」「alien species」「exotic species」などがよく用いられます。
この記事では「外来種」の表現で統一することにします。
では肝心の「外来種」の意味ですが、「人間の活動によって直接的または間接的に(意図的または偶発的に)本来の分布域外で生息・生育している生物種」のことを指します。
野生生物には「分布域」というものがあります。一般的にこの範囲に住んでいるというエリアのことです。そのエリア内でよく観察でき、そのエリア内を自発的に移動したりもしますが、そこから飛び越えることはほぼない…そういう理解です。
しかし、人間の活動が原因で、ある生き物がその分布域の外に移動してしまい、観察できることがあります。本来の自然ではあり得ない現象の結果です。それが外来種です。
この「人間の活動」というのはいろいろあって、例えば、ペットや園芸、漁業など何かしらの産業目的で直接的に持ち込まれたりする場合もあれば、貨物に紛れ込んだりと全く意図せずに持ち込まれる場合もあります。
一方で野生生物自身の力で大きく移動してきた場合は外来種とはみなしません。例えば、渡り鳥や、熊が市街地に出没する…などが該当します。
とにかくこの「人間の活動」と「本来の分布域外」というのが外来種の定義において最も大切な部分です。
「外来種」と「侵略的外来種」
ここでもうひとつ大事な、そして誤解されやすいことがあります。
「外来種」と「侵略的外来種」という2つの言葉の違いです。これらは区別されずにメディアで用いられていることも多く、混同しやすいのですが、明確に意味が異なります。
人間の活動によって本来の分布域外で観察できるようになった「外来種」は、必ずしも「有害」な結果をもたらすとは限りません。そもそも定着するかもわかりません。たいていの外来種は定着できずに死んでしまいます。仮に定着したとしてもその外来種が自然にどう影響を与えるかは非常に多様で複雑です。
しかし、中には明らかに有害な影響を与える外来種もいます。その外来種は定着する力が強く、その地域にもともと住んでいた「在来種」や既存の自然環境に甚大な影響をもたらします。
こうした外来種を「侵略的外来種」(日本語では「侵入種」とも呼ぶ)といいます。「侵略的外来種」は、英語では「invasive species」(もしくは「invasive alien species」とも呼ぶ)といい、その英語を直訳したものです。
「特定外来生物」という言い方もありますが、これは日本の『外来生物法』で定義される法律用語です。
つまり、早い話が有害性が科学的に検証・推測されているかどうかで「外来種」と「侵略的外来種」は区別されるということです。生態学の研究者は、ある生き物が「侵略的外来種」であると判断するために多くの研究を日々地道に行っています。基本的に科学的な証拠をもって「侵略的外来種である」とみなしています。
それは定着した環境など個別の事例によっても変わってきます。例えば、猫は日本の都会の住宅地で野良猫として歩き回って事実上野生化しているだけなら「侵略的外来種」というほどの有害性はないかもしれません。しかし、希少な生物種が分布する小さな島などに猫が持ち込まれた場合、その猫が野生化すれば重大な「侵略的外来種」となりえます。
このように「外来種」と「侵略的外来種」は意味が異なる言葉なので、「侵略的外来種」を略して「外来種」と表現してはいけません。
「侵略的外来種」は有害な問題をもたらしているので、駆除などの対応が行われることがあります。逆に「外来種」というだけならとくに問題視はせず放置されていることも多々あります。
外来種は外国人や移民とは全く異なる
では本題の、「外来種」という言葉を持ち出して外国人や移民を危険視したり排除する説明材料に用いることはなぜ誤りなのか…を解説します。
最初にも少し触れましたが、この誤解は「外来種」を「海外からやってきた生き物」と誤って認識している人がいることが背景にあります。
前述したとおり、「外来種」とは人間の活動によって本来の分布域外で観察できるようになった生物種のことです。「人間の活動」と「本来の分布域外」という要素が大事です。そして何よりも「国境」は一切関係ありません。
何となく日本では「アメリカザリガニ」や「アライグマ」など日本に本来は生息していない外来種が有名なので、日本人は「外来種=海外の生き物」だと誤認しやすいのだとも思います。確かに日本は島国なので、海外の生き物の多くは外来種になりえます。
しかし、それは一面的なものです。日本に住んでいる生き物でも日本の外来種になりえるからです。例えば、「カブトムシ」や「トノサマガエル」は日本の本州にもともと生息していますが、北海道には本来は生息しておらず、北海道に定着している個体群は外来種です。
このように野生生物は人間社会が政治的に決めた国境など眼中にありません。分布域は国境をまたがることも普通にあります。一方でひとつの国土内でも、ある生き物の分布域が細分化していることもあります。外来種は国境では語れないのです。しいていうなら外来種の水際拡散防止策のために国境でのチェックなどがひとつの防波堤になる程度です。
なので外国人や移民は外来種と同一ではないというわけです。そもそもそんなことを言ったら、地方から東京に上京してきた人や、都会から田舎に引っ越ししてきた人も、外来種ということになってしまいます。
一般的に「外来種」の概念は人間には当てはめません。それを前提に作られた言葉ではないからです。ただし、人間という生き物の重大な影響力を指摘するべく、皮肉を込めて「ヒトは究極の侵略的外来種だ」などと表現されることはありますが…(Scientific American)。無論、この場合も特定の人種や民族だけを「外来種」だとレッテルを貼っているわけではないです。
外来種の論点は昔からブレやすい
「外来種」という言葉が、一部で、外国人や移民に対する排外主義のレトリックの道具にされているのは悲しいことです。科学を偽って差別の正当化に用いるのは「優生学」の前例があるので、常に警戒しないといけません。
ただ、「外来種」という概念はかなり以前から論点がブレやすく、脱線することもしばしばでした。
その最たるものが「外来種は悪か」という論点です。
一部の人は「外来種を悪者と決めつけるのはよくない」と主張してきました。この主張における「外来種」は本来の「外来種」と「侵略的外来種」のどちらを指しているのかというツッコミはさておくとして、この主張の裏にはだいたい3つの勢力があります。
ひとつ目は、外来種対策として規制の対象となった産業界からの反発です。例えば、ブラックバスなどでおなじみのフィッシング業界は日本でも『外来生物法』制定時に猛反発し、「外来種は悪くない!」と息巻きました。その後、ブラックバスなどの侵略的外来種による悪影響に関する研究が続々と積み重ねられ、だいぶ反発は初期よりも静かになりましたが…。
2つ目は、“動物の権利”団体からの反発です。外来種への対応として「捕殺・駆除」がとられることが多いので、それに対して「外来種は悪くない!」と声をあげることがあります。これには一部一理あり、外来種対策は場当たり的な駆除に終始することも多いです。理想的には駆除一辺倒ではなく包括的な対策(未然防止・教育・産業規制など)が実施されるべきですが、資金不足や合意の得られにくさゆえに、駆除ありきで終わってしまっています。IUCN(国際自然保護連合)も「侵略的外来種の取引と移動を規制することは、それらの侵入と拡散を防ぐ最も効果的な方法です」と述べているとおり、駆除よりも規制に踏み込めるかどうかは大事です。
3つ目は、ちょっとイレギュラーですが、アウトサイダーからの反発です。一部の識者の中には外来種を論じる生態学の学問を、利権目当ての「invasionist」が推進する「invasive species ideology(invasionism)」と断言する人がいます(こういう勢力を「Invasive species denialism(侵略的外来種否認主義)」と呼んだりもする)。やや「“地球温暖化”懐疑論者」と近いところのある反応なのですが、まあ、これに関しては深掘りすると本当にどんどん脱線するので紹介にとどめておきましょうか…。
この上記3つにハッキリ当てはまることを意識していなくとも、日本のメディアなんかは漠然と「外来種は悪者なのでしょうか」と“議論してみせた”風の見出しや記述をくっつけて語っている事例もよくあります。
日本では「外来種=問題を起こす危険な生き物=人間が懲らしめないといけない」と安易に結び付けて考えている人もみかけます。少し前に日本のテレビ番組で流行った「池の水を全部抜いて外来種を見つけて“大捕り物”としてエンタメにする」みたいな図式は、そうした安直さが背景にあると言えるでしょう。
しかし、声を大にして言いたいのは、そもそも科学者は「外来種は悪だ」などと主張はしていないということです。そんなことは論点ですらありません。論点ではないものをさも論点であるかのようにミスリードしているのは他の人たちです。
外来種の定義で大事なのは「人間の活動」だとくどいくらいにこの記事でも強調しているのは、要するに「人間が悪であり、加害者である」という認識を忘れないようにということです。
侵略的外来種がこうも世界中で深刻化し始めた最大のきっかけは「植民地主義」と「大量消費をともなう経済活動」です。侵略的外来種は人間が生み出しました。
「可愛いから」「綺麗だから」「便利だから」「美味しいから」…そんな理由で多種多様な生き物を都合よく利用してきた私たち人間。あなたが最近Amazonで注文して届けてもらった商品は大きく地域を移動してきたはずですが、そこに外来種も付随してきたかもしれません。意識したことはあるでしょうか。
外来種について真っ当に考えるなら、まずは自分たちの身の回りにある自然を保全するために、自然環境を意識することから始めましょう。そして自然環境と人間の社会経済活動がどのように作用しているのかを考えてみましょう。
本気で日本の自然を守りたいなら、外国人や移民の敵視ばかりを考えている暇はないはずです。
「生物学」に関する用語の意味を解説した記事の一覧です。
・「生物学的性別」とは?