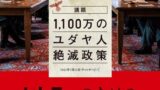警鐘を鳴らし続けるために…ドキュメンタリー映画『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:イギリス(2019年)
日本では劇場未公開
プレゼンター:アンジェラ・サイニー、アダム・ピアソン
人種差別描写
ゆーじぇにっくす さいえんすずぐれーてすとすきゃんだる
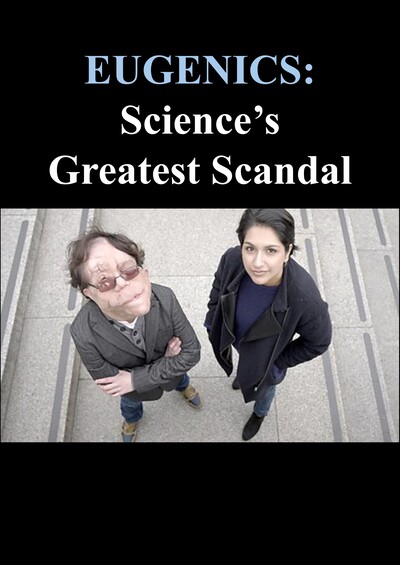
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』簡単紹介
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』感想(ネタバレなし)
優生学は一部の極端な過激思想ではない
「あの有名な研究者も、政治家も、フェミニストも、みんな支持している最新の学問があるんだって…!」
「社会で苦しんでいる人を減らし、不平等を無くして、世界をより良い未来に変えることに繋がる根本的な解決策になるらしいよ…!」
もしそんな話が耳に聴こえてきたら…あなたはどう思うでしょうか。
19世紀末、実際にそんな雰囲気の中である学問が話題になりました。
それが「優生学(eugenics)」です。
優生思想に基づき、それを学術的に体系化することを試みた優生学。名前は聞いたことがあるという人も多いはず。
「でも優生学ってナチスとか極右が支持しているやつでしょ?」というイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
確かに、ナチス・ドイツが第二次世界大戦時に主にユダヤ人に対して虐殺(ホロコースト)を実行しましたが、その背景には間違いなく優生学があります(『ヒトラーのための虐殺会議』で描かれているように)。
このホロコーストによって「優生学の恐ろしさ」が世間的に認知されたので、「優生学=極右」の印象が深いです。
しかし、本来の優生学は極右のみならずその政治的スペクトラムに関係なく、実に幅広いエスタブリッシュメント(知識人層)に普及し、推進されていました。その事実を無かったことにするわけにはいきません。
その優生学の起源を含んだ歴史、そして現在の状況にいたるまでを貴重な映像資料と専門家の解説で整理したドキュメンタリーが今回紹介する作品です。
それが本作『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』。
本作は2019年に「BBC Four」で放送された2話構成のドキュメンタリーです。
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』は、2人の人物がプレゼンターを務めています。
ひとりは、インド系イギリス人の科学ジャーナリストの“アンジェラ・サイニー”。『Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story(科学の女性差別とたたかう: 脳科学から人類の進化史まで)』や『Superior: The Return of Race Science(科学の人種主義とたたかう: 人種概念の起源から最新のゲノム科学まで)』、『The Patriarchs: The Origins of Inequality(家父長制の起源 男たちはいかにして支配者になったのか)』といった著書をだしており、いずれも科学の視点から性差別や人種差別を解きほぐしています(日本でも出版されているので読めます)。
もうひとりは、神経線維腫症1型の当事者であり、障害者権利活動家としても活躍し、最近は『顔を捨てた男』で重要な役を務め、社会のディサビリティに対する偏見に向き合っている“アダム・ピアソン”。
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』を観れば、優生学(優生思想)は一部の人が持つ極端な過激思想ではなく、普遍的で誰しもが持ちうる考え方だということがわかると思います。だからこそ危険なのだ、と…。
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | — |
| キッズ | 社会勉強の教材に利用できます。 |
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』感想/考察(ネタバレあり)

ここから『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』のネタバレありの感想本文です。
優生学の始まり;進化論を人間に…
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』はまず優生学の原点を探っていきます。本作がイギリスのドキュメンタリーであるのは、まさに優生学の発祥の地だからです。
優生学の誕生のきっかけとなった人物…それは「チャールズ・ダーウィン」でした。
多くの人がご存じのとおり、「進化論」を提唱したことで有名であり、1859年の著書『種の起源』をはじめ、その理論は現代の生物学の礎となっています。「進化論」はあくまで動植物を対象としており、その多様性が「進化」と呼ばれる生物の形質が世代を経る中で変化していく現象によって築かれていることを説明していました。
そんなチャールズ・ダーウィンですが、実は1871年には『人間の進化と性淘汰』という別の著書もだしており、こちらでは進化の理論を人間に応用して考察していました。
その19世紀後半に生まれ始めたのが「社会進化論(社会ダーウィニズム)」であり、チャールズ・ダーウィンの進化論を土台に、人間社会の変化を分析しようと試みる観点が広まっていきます。
そして作中で大々的に取り上げられる「フランシス・ゴルトン」という人物に辿り着くわけですね。今となっては皮肉なことに彼はチャールズ・ダーウィンは従兄にあたる関係性なのですが、このフランシス・ゴルトンが1883年に「優生学」という言葉を生み出すことになります。
優生学は現在では信用性のない「正当な学問として扱われていない」かつての信念と実践…とみなされていますが、その起源は紛れもなく科学史の中にあることが本作でもハッキリ提示されます。ちゃんと博物館に資料として残ってますから。
フランシス・ゴルトンも多才な学者で、統計学の基礎を築いたひとりであったりと、現代の科学に大きな功績を残しているのですが…。彼は神童だったとも言われており、その「天才」に対する信奉が優生学を推進する原動力だったのか…そこはわからないですけど…。
本作はあくまで科学的な資料を整理しているにとどまっており、フランシス・ゴルトンの人となりまで掘り下げません。ただ、当時のゴルトン含め社会進化論を支持していた人たちは、別に異様なマッドサイエンティストとか、そういうわけではないと思います。こういう能力主義に傾く研究者って科学コミュニティにわりといるでしょう。
「より良い能力のある者がより良い世界を築ける」という発想…。進歩を求める欲求が持ちうる恐ろしさという一面にはやはり自覚的でないといけないなと痛感するドキュメンタリーでした。
みんな「好ましくない人」を排除したかった
優生学は科学コミュニティに起源がありますが、その枠を超えて、とても多くの人々に支持を広げていきました。『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』はその実例を紹介してくれます。
その中であらためてわかるのは、優生学が幅広く支持される理由です。それはおそらく一見すると「良いことを言っているようにみえる」…非常に気持ちのいい響きがあるからなんだろうな、と。
これもナチスのせいだと思うのですが、優生学ってどうしても「お前は下等だ! 劣等な奴らを滅ぼせ!」みたいな、コテコテの大仰な悪役風の仕草で想像されやすいじゃないですか。
でも実際はそうではないんですね。前述したとおり、優生学自体は「社会をより良くする」という進歩主義の仮面を被っています。
1912年7月に開催された第一回国際優生学会議にはウィンストン・チャーチルなどそうそうたる顔ぶれが参加し、優生学はもはやひとつの学問分野というよりは、それを旗にしてさまざまな有力者が結集するエスタブリッシュメント・コミュニティへと発展を遂げています。
ジュリアン・ハクスリー、シリル・バートなど男性の知的エリートだけでなく、マリー・ストープスといったフェミニストのパイオニアのような女性も、優生学に魅入られていったことも特筆されます。優生学フェミニズムについては、『レッド・バージン』のような映画で題材になった事例もあるとおり、これだけでも歴史は深いです。
「避妊」というのは今も大切な権利ですが、それが操作的に社会に応用されてしまえば、いともたやすく「出生管理(birth control)」に変貌してしまう…。
作中でプレゼンターの“アンジェラ・サイニー”が複雑な顔を浮かべるように、優生学と無縁でいられるものはありません。
エベネザー・ハワードによるユートピアの都市構想が、優生学をいかに練り込んでいるかという切り口も興味深いところでした。
「社会をより良くする」うえで「全ての者に平等を与える」のではなく「誰かをスケープゴートにする」のが優生学です。
ではスケープゴートにされるのは誰か。それは作中の言葉を借りれば「undesirable」(好ましくない人)です。
プレゼンターの“アダム・ピアソン”が歴史を探究するように、すでにあの時代から精神障害者や身体障害者は「deficient」(欠陥あり)として、隔離され、排除されていました。ホロコーストが全ての始まりではありません。
誰だって「こいつ、嫌いだな」っていう他人がひとりやふたり、いや、大勢いると思います。それ自体は別にいいんですよ。しかし、優生学はその「嫌いな人」を排除するもっともらしい口実に使えてしまう…。そこが怖いですね。
人権っていうのは自分が大嫌いな相手でも適用されるということを何よりも一番に忘れてはいけないってことですが…。
本当に今の「科学」は大丈夫か?
『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』の後半は、優生学はナチスとともに滅んだ…わけではないことを整理し、その姿形を変えて実践されている「優生学らしきもの」、もっと言えば「優生学と極めて近似的で危ういもの」を映し出していきます。
「Mankind Quarterly」と呼ばれる「科学的人種主義」の疑似科学雑誌が生まれたり、「新優生学」が産声をあげます。これらを支持する人は「自分たちはかつてのような優生学ではない。これは本物の科学だ」と主張していますが…。
ちなみに作中で取り上げられませんが、反トランスジェンダーの立場で有名なレイ・ブランチャードといった研究者も新優生学のコミュニティに属しています(Trans Data Library)。
とくに現代で最も存在感を強めているのが遺伝子工学です。ダウン症のスクリーニングの是非を当事者をめぐりながら取材するプレゼンターの“アダム・ピアソン”の表情はツラいものがありました。
ゲノム編集(遺伝子編集)のテクノロジーは確かに有用かもしれません。より良い未来に繋がるという言い分もわかる…。でもそれって、あの19世紀末の優生学と同じ空気では…。
本作で19世紀末と今の時代を歴史で直結させることで、その印象は危機感として深まりやすいものになっていました。
本作は「INTERGROWTH-21st Project」を最後に映しつつ、この今の「優生学と極めて近似的で危ういもの」を全否定するまで語気を強めることはしませんが、最大級の懸念を投げかけて終わります。
科学コミュニティが人権と倫理の信念を失わなければ大丈夫…と、私も少し前なら言っていたかもしれませんが、このドキュメンタリーが製作された2019年からたったの6年も経たないうちに、露骨に差別主義的な権力が科学を乗っ取る事態が起きているのを目にしてしまうと…。
やはり優生学の警鐘は今こそ強く打ち鳴らすべきときにきていると言わざるを得ません。それは決して過剰な危険意識ではないでしょう。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
作品ポスター・画像 (C)BBC
以上、『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』の感想でした。
Eugenics: Science’s Greatest Scandal (2019) [Japanese Review] 『Eugenics: Science’s Greatest Scandal』考察・評価レビュー
#科学ドキュメンタリー #アダムピアソン #優生思想 #ユダヤ #BBC