壮大なスケールゆえの固定観念…映画『HERE 時を越えて』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:アメリカ(2024年)
日本公開日:2025年4月4日
監督:ロバート・ゼメキス
恋愛描写
ひあ ときをこえて

『HERE 時を越えて』物語 簡単紹介
『HERE 時を越えて』感想(ネタバレなし)
Here ? Yes, Here !
私の住んでいるところの近くにある集合住宅団地が改修されるというニュースを耳にしました。かなり古い団地で、この地域の初期の住居のひとつだったそうなので、年月を感じます。今の日本では放置されてしまう老朽化した団地も多い中、改修されるだけマシですし、まだ住んでくれる人が期待されているということでしょうし、良いことではあるんですけどね。
どんなで家でもそこに誰かが住んでいたはず。ただ、住人は移り変わりますが、家自体はそこから移動できません。改修されるか、立て直しか、はたまた解体されるか。その運命です。
だから家は常に「ここ」に建って、いろいろな変わりゆく人や物事を見守っています。
今回紹介する映画はそんな全てをここで見守る家が主人公と言ってもいいような作品です。
それが本作『HERE 時を越えて』。
「時を越えて」という副題がついていますが、別にタイムトラベルとかはしません。本作は、あるひとつの家で暮らしていくさまざまな家族に焦点をあてた物語が展開されます。
ただし、最大の特徴はカメラが家のある位置でずっと固定されており、そこから動かないということです。全編固定視点の実験的映画なんですね。
この固定視点は監視カメラほど冷たい感じではなく、普通の撮影の延長線上にありますが、なにせ動きません。同じ視野で同じ範囲を映し続けます。こうなってくると、家の空間を利用したアートインスタレーションみたいです。
『プレゼンス 存在』や『SKINAMARINK スキナマリンク』など、家だけで展開する実験映画というのはありますけど、『HERE 時を越えて』にはホラーやサスペンスはなく、家族の営みが淡々と描かれますので基本は穏やかです。
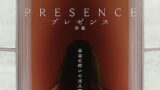

しかし、そこにもうひとつ演出的なアプローチのバリエーションがあって、固定視点なのですけど、何度も漫画のコマみたいな四角い枠が映し出され、その中だけ時間軸が変わるんですね。つまり、その空間の昔の様子が映ったりするわけです。
こうして時間を交差させてその家のある空間で起きたことを同時的に描くという、何ともスケールの壮大な内容になっています。視点は動かないのにスケールがデカいというのも変な話ですが…。
この『HERE 時を越えて』は“リチャード・マグワイア”によるグラフィックノベルが原作で、当初は1989年に出版された際は6ページしかなかったのですが、2014年には304ページもの大作に拡大したそうです。
1991年に短編映画になったことがあり、2020年にはVR映画にもなったらしいのですが、2024年にあの“ロバート・ゼメキス”監督のもとで長編映画化となり、『HERE 時を越えて』が生まれたのでした。
“ロバート・ゼメキス”監督が好きそうな原作ですよね。しかも、今回は、“エリック・ロス”と共同脚本を務め、“トム・ハンクス”が主演をやって、“ロビン・ライト”がその“トム・ハンクス”演じる男の妻の役をするという…完全な『フォレスト・ガンプ 一期一会』の座組の再来。
確かに『フォレスト・ガンプ 一期一会』と作品性が似ているし、あれをより実験的映像演出で表現したようなものと言えるのかもしれません。
“トム・ハンクス”ら俳優陣はいわゆる「ディエイジング」という最新のCGIで若返った顔で映し出されるのですが、今作では演技中でもリアルタイムで生成AIを使用して若返らせているそうです。
映画館のスクリーンという巨大な四角い枠の中で、いくつもの四角い枠の中で織りなされる家族ドラマを見つめるのはなんとも不思議な気分になりますよ。
『HERE 時を越えて』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | 死別が一部で描かれます。また、コロナ禍の描写があります。 |
| キッズ | 大人向けのドラマです。 |
『HERE 時を越えて』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
恐竜が自由に闊歩する大地。遠くには火山が見え、噴煙をあげています。そして突然に大噴火を起こし、空は暗闇に包まれ、火山灰が降り注ぎます。しかし、それだけでは終わりません。空を覆いつくすような巨大な隕石が近くに落下し、凄まじい衝撃が一帯の森を跡形もなく吹き飛ばします。炎が降り注ぎ、命が消え失せ、塵だけの世界になってしまいました。
大地は氷と雪に覆われて年月が経過しましたが、しだいに解けていき、緑が生え始めます。そして森が再生しました。
豊かな生き物が反映し、そこには鹿を追いかける人間の姿も…。野生の中で生きる人間たちはここで社会を育み、家族を築きます。
やがてこの地に他所からやってきた入植者たちが現れ、家を建設するようになります。家の数はまだ少ないですが、レンガを並べて木材をくみ上げて、一軒の家がここに建ちました。
その家はベンジャミン・フランクリンの息子ウィリアム・フランクリンの邸宅の一部であり、アメリカの歴史の欠かせない場所でしたが、これも年月が経っていくとただの家でしかなくなります。
そしてその家に住みだしたのは、ジョン・ハーターとその妻ポーリンでした。ジョンは飛行機のパイロットに夢中で、情熱だけが先走ります。
次に住んだのが、リーとステラのカップルです。リーは発明が好きで、座ると自由に背もたれを傾けて向きも変えられるひとり用の椅子を手作りしてご満悦。ステラはピンナップモデルで、リーに写真を撮ってもらってこちらも満足そうです。
第二次世界大戦後の1945年、今度は戦地から帰還したアルと妻ローズがその家を購入し、暮らし始めます。ローズは妊娠しており、リチャード(リッキー)が生まれます。さらにエリザベス、ジミーと、合わせて3人の子どもが家族に加わり、家は賑やかになります。やんちゃな子どもたちが駆け回っているので、常に何かが巻き起こります。
リチャードは絵に興味を持ち始めますが、それはまだ漠然とした関心でしかありません。
18歳になったリチャードはガールフレンドのマーガレットを家に連れてきて、親に紹介します。そしてグラフィック・アーティストになりたいという夢を語りますが、父のアルは現実味がないとあまり相手にしてくれません。
そのうち、リチャードの恋人のマーガレットが妊娠したと報告され、父アルは突然のことすぎて息子に激怒。
こうしてこの家にまた新しい命が生まれますが…。
映像の制約の中で

ここから『HERE 時を越えて』のネタバレありの感想本文です。
『HERE 時を越えて』の原作はあくまで漫画なので、四角い枠を登場させてそこの時間軸が違うという演出もそれほど違和感なくビジュアルでは納得できます。平面の絵であれば、少々変わったコマ割りくらいの感覚で無理なく仕込めるでしょう。
しかし、これを映像作品でみせるとなると想像以上に大変でしょうね。今回の映画を観てよくわかりました。
まずそもそも映像内に四角い枠が多用されて表示される時点でだいぶ異色の雰囲気になります。一般的な映画ならオープニングでちょこっと使う程度の演出だったり、途中でトーンを変えるためのシーン切り替えの手段として採用する程度でしょう。
本作は非線形の物語で、つまりこの時間軸を描いたかと思えば、次は別の時間軸を描いたりと、タイムラインが行ったり来たりします。通常の非線形の物語と違って、本作の場合はそのタイムラインが全体で切り替わるのではなく、同一の映像内で部分的に切り替わったりするので、すごく忙しい映画です。空気感は常に穏やかですが、情報量と頻度自体は結構忙しいですよね。非線形の物語が苦手な人はかなりキツイ作品かもしれません。
しかし、固定視点になっていることである程度は情報が制限されるのがまだ整理しやすさにもなっています。
けれどもこの固定視点というのもなかなか厄介です。映画的な技法として普通に用いられる撮影手法の多くが封じられますからね。
ズームにしたいときはキャラクターが視点に近づくしかないです。そのせいかリチャードを演じる“トム・ハンクス”なんかはところどころやけに視点側に近づいて顔が大写しになるように立ちます。正直、不自然なシーンもなくはないです。なんで部屋の中でもわざわざこの位置で抱き合ってるんだろう?とか、そんな角度で食卓テーブルを設置するか?とか、観ていて「ん?」と思う場面もありました。
カメラワークでみせるというテクニックは使えないというだけでなく、リビングルームが全部の舞台にならないといけない制約も生じます。リチャードとマーガレットの結婚パーティーも普通は家の外でやるものをわざわざ居間で、ちゃんと固定視点の画角に収まるようにやってくれています。
リビングルームでドラマが起きまくりですよね。他の人はどうなのか知りませんけど、私は人生でリビングルームでそんなドラマが起きたこと、ほぼ無いんですけど…。私自身がリビングルームにいるときの様子を50年固定カメラで記録したとしても何一つ面白いシーンは無いと確信を持って言えますよ。ほんと、代わり映えないからな…。
ラストは認知症のマーガレットが久しぶりの空っぽの家を訪れて、記憶を思い出すという、とてもベタにエモいシーンが用意されていますが、そこでカメラがついに動き出し、家の外から家を中心に世界全体を映し出すという幕引き。これしかないというエンディングです。
まあ、実験映画ならこれくらい尖った作りにしても全然いいのですが、やっていることに対して描かれる物語がド定番すぎるのは少々面白くなかったかなとは思いました。
いらなかったシーン、あったら困っただろうシーン
個人的に『HERE 時を越えて』で一番に残念というか、欠点だなと感じたのは、スケールが壮大すぎることです。ベンジャミン・フランクリン家からデヴォンとヘレンの家庭までならいいですよ。問題はそれより過去、まさかの太古から描いてしまうことで…。
本作は恐竜の時代から始まり、凄いディザスターが起きます。「え? もう家が作れるような平地ではなくなるのでは?」と心配になりましたけど、なんかどういうわけか平地は維持されてましたね。
それで私たち人類の祖先が描かれるわけです。ここが問題です。本作の舞台はアメリカなので、ここで描かれるのは先住民です。で、その後に入植者がやってきます。
本作はこの変化を時の移り変わりという不可抗力な壮大なスケールとしてどこかノスタルジックと畏怖を交えて映し出していますけど、先住民がフェードアウトするのは植民地施策ゆえです。本作はその植民地主義の歴史をかなり薄味に変えてしまっており、あまり白人に都合がよすぎると思います。
しかも、先住民のパートでも男女で愛を育み、子育てし、生と死を経験するという、後の白人家庭と同じ展開を描くことで、時代が違ってもここで起きていることは同じだという普遍性を語りたいのでしょうけど、俗にいう「人類みな同じ」というフワっとしたレトリックで包んでいるのが露骨で、余計に嫌な感じがでてしまったな、と。
実際は先住民にはその民族特有の文化があり、その土地に根付いた歴史があり、それを破壊したのが植民地主義ですからね。「ここ(here)」から強制的に追い出された側はこの映画をどう見つめればいいんだという話で…。
だったらいっそのこと恐竜や先住民を描くまでスケールを拡張しないほうが良かったと思います。
ちなみに原作では家が未来に取り壊される姿も描かれるのですが、映画版では維持されたままです。しかし、なんと制作途中の段階では、あの家が一帯を襲った津波か洪水か何かで押し流されて破壊されるという展開を考えていたようです。ちゃんと映像も完成しており、以下の本作のCGIを手がけた「DNEG」の動画で確認できます。

もしこの水害展開が採用されていたら、どういう気持ちで鑑賞すればよかったんだろうか…。日本で公開する配給会社はちょっと悩むことになったろうな…(無くてよかったと胸をなでおろしているはず)。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
関連作品紹介
ロバート・ゼメキス監督作の映画の感想記事です。
・『ピノキオ』
・『魔女がいっぱい』
・『マーウェン』
作品ポスター・画像 (C)2024 Miramax Distribution Services, LLC. All Rights Reserved. ヒア時を越えて
以上、『HERE 時を越えて』の感想でした。
Here (2024) [Japanese Review] 『HERE 時を越えて』考察・評価レビュー
#アメリカ映画2024年 #ロバートゼメキス #トムハンクス #ロビンライト #ポールベタニー #家族 #認知症 #死別 #COVID19 #先住民 #ネイティブアメリカン



