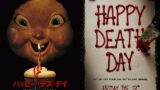見るだけしかできません…映画『アンティル・ドーン』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:アメリカ(2025年)
日本公開日:2025年8月1日
監督:デヴィッド・F・サンドバーグ
ゴア描写
あんてぃるどーん
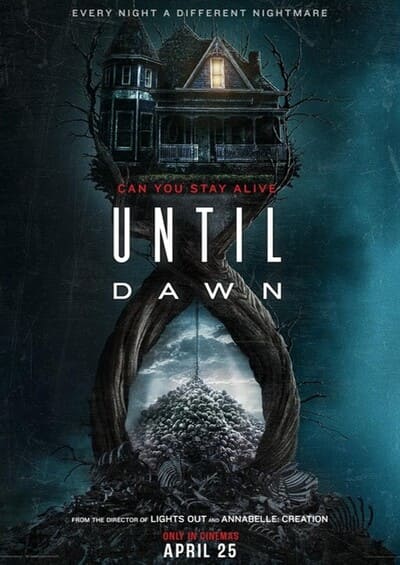
『アンティル・ドーン』物語 簡単紹介
『アンティル・ドーン』感想(ネタバレなし)
ゲームよりも怖さに対処しやすい映画版
ホラーゲームをプレイすることはホラー映画を観るよりも、苦手な人にはハードルが高いかもしれません。なにせ映画だったらとりあえず目を閉じていれば怖いシーンをやり過ごすことができますが、ゲームだと目を閉じて操作が止まってしまえば進行しません。強制的に恐怖に向き合わせられるのがホラーゲームの醍醐味ではありますが…。
そう考えるとホラー映画はホラーゲームよりも恐怖に対処しやすくなっているので、あれです…親切ですね! いい奴だったんだ、ホラー映画は…。
今回紹介するホラー映画もきっとそんな奴に違いない…。
それが本作『アンティル・ドーン』。
本作は『UNTIL DAWN -惨劇の山荘-』というタイトルでソニーから2015年に「PlayStation 4」でリリース(リメイクも「PlayStation 5」と「steam」で2024年にリリース)されたホラーアドベンチャーゲームが原作となっています。
若者のグループが主人公で、山荘に集って、そこで次々と殺されていくという、王道のスラッシャーホラーを土台にしています。でもゲームなので、そこに操作の要素があり、プレイヤーの操作や選択肢しだいで登場人物の生死が変わり、「どうやったら死なないか」ということをあれこれ考えて楽しむのが醍醐味でした。
その人気ゲームの映画化ということで、企画したのは「うちのソニーのゲームをどんどん映画化してついでにゲームの売り上げもアップだ!」と息巻いている「PlayStation Productions」。これまで『アンチャーテッド』(2022年)、『グランツーリスモ』(2023年)と続いてきて、今回で映画としては初のホラーのジャンルです。


でも次の「PlayStation Productions」映画は『バイオハザード』らしいので、ゲーム原作のホラー映画が続きそうですが…。
映画『アンティル・ドーン』はゲームとコンセプトは同じですが、キャラクターやストーリーは変わっています。
でも日本の人々にとっての一番の違いは、ゴア描写かもしれません。というのも、このゲームはもともとかなり激しいゴア描写があって残酷なのですが、日本のゲーム業界はレーティング規制が厳しく、激しいゴア描写はそもそも表現できず、日本版のゲームだけ極端に表現規制が多くて、肝心の残酷なシーンが見られないことになっていました。
その点、ゲームと違って映画は激しいゴア描写も映せるので、この映画『アンティル・ドーン』も日本では「R18+」のレーティングですが、ちゃんとゴア描写は目にできます。
結果、先ほども書いたように映画なのでとりあえず目を閉じていれば怖いシーンをやり過ごすことができますけども、ゲーム以上にゴア描写も楽しめるという、日本の人々にとってはちょっと変わった立ち位置の映画になりました。まあ、誰にとっても両得と言えるのかな。
その映画『アンティル・ドーン』の監督を手がけるのは、スウェーデンの“デヴィッド・F・サンドバーグ”。2016年の暗闇を題材にしたシンプル・イズ・ベストホラーな『ライト/オフ』で鮮烈にデビューし、『アナベル 死霊人形の誕生』(2017年)で大手スタジオに拾われ、それからDCのスーパーヒーロー映画『シャザム!』シリーズを2作任されました。
その“デヴィッド・F・サンドバーグ”が久しぶりにホラー映画に帰還しました。個人的にはホラーに戻ってきてくれて嬉しいですね。やっぱり“デヴィッド・F・サンドバーグ”監督はホラーなんだ…うん…。
映画『アンティル・ドーン』に出演するのは、『フィアー・ストリート プロムクイーン』の“エラ・ルービン”、ドラマ『Love, ヴィクター』の“マイケル・チミノ”、『Fresh Kills』の“オデッサ・アジオン”、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の“ユ・ジヨン”、『君と一緒に過ごした夏』の“ベルモント・カメリ”、ドラマ『アートフル・ドジャー』の“マイア・ミッチェル”など、若手勢が揃っています。
ホラーゲームが無理な人でも映画『アンティル・ドーン』ならセーフ…かな?
『アンティル・ドーン』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | — |
| キッズ | 非常に残酷な殺人描写が満載なので不向きです。 |
『アンティル・ドーン』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
1年前に失踪した姉メラニー(メル)を捜すため、クローバーは友人たちとともに車で出かけていました。同行しているのは、元カレのマックス、友人のニーナとメーガン(メグ)、そしてニーナのボーイフレンドであるエイブです。
車は森に囲まれた何の変哲もない舗装された一本道の道路を走っており、エイブが運転しています。
手がかりはメラニーが残した動画でした。その撮影地のガソリンスタンドに到着します。普通のみすぼらしい建物です。わざわざここに来る理由は一般的に考えられません。ましてや若いメラニーがひとりでなんて…。
クローバーは先に店内へ入り、店員の男に去年にこの人を見なかったかと画像をみせて質問します。すると「行方不明になったのか」と言ってもいないのに当ててきます。なんでもこの先の鉱山の町の近くで行方不明者が出ることが多いのだそうです。
もしかしたらこのまま進めばもっと手がかりが見つかるかもしれないと思い、一同は車でさらに走っていきます。
ところが突然の激しい雨に遭遇。しかし、ある場所で急に途切れるように雨がやんでいました。その場所は周囲をぐるっと雨雲が囲み、なぜか雲が中に立ち入ることもないです。
そこにあったのは小さな家、そして粗末な木の十字架の墓らしきもの。とりあえず家の中に入ってみると、ひととおりの家具があるものの、人影はないです。
室内は1998年とカレンダーにあり、その時代の内装を再現しているビジターセンターなのかはよくわかりません。大きな砂時計が壁に飾ってあります。行方不明者の張り紙がいくつも貼られていおり、老若男女さまざま。数が尋常ではなく、しかもそこにメラニーの顔写真もありました。
クローバーは人影を見た気がして雨の中へ足を踏み入れてしまい、一瞬で方向感覚を失います。たまたま見ていたマックスに戻ろうと引っ張られ、なんとか家に戻ってきました。
ニーナはセンターの来客帳に記帳します。ゲストの欄には他にも名前があり、メラニーの名もありました。それもいくつも名が書かれており、下にいくほど筆跡がぐちゃぐちゃです。
一行は情報を整理。確かにここが怪しいです。でも不自然すぎます。
ふと壁の砂時計がひっくり返っていることに気づきます。誰も触っていないはずなのに…。
どの死に方がいいですか?

ここから『アンティル・ドーン』のネタバレありの感想本文です。
『アンティル・ドーン』の導入はいたってよくあるものです。
若者たちが人里離れた山荘(今回はビジターセンターのようですが)に集まって、そこで恐怖を体験することになります。
ただし、そこはドラマ『フロム 閉ざされた街』のように、一度入るとそう簡単に出られないような超常現象的な閉鎖空間になっており、餌食となった人たちはここから脱するにはその謎を解く必要もでてきます。
さらにただの物理的な脱出困難空間というだけでなく、いわゆるタイムループまで起きていき、何度も死を繰り返すハメになりますから…。踏んだり蹴ったりとはこのことです。
何回も殺されてはタイムループしていく酷い状況に陥る映画と言えば、『ハッピー・デス・デイ』がありますけど、それと比べてこの『アンティル・ドーン』は複数の登場人物がターゲットになるのでわちゃわちゃしています。
殺され方もバリエーション豊かです。そして何よりもどうせまた生き返った状態に戻るので、殺し方に出し惜しみがありません。人物は5人いても、実質的には50人くらいいるのとそう変わらないですから。
最初は『ハロウィン』のブギーマンばりの剛腕怪力によるマンハントなスラッシャーがお出迎え。みんなが人体破壊で悲惨なことになっていきます。発泡スチロール並みにボロボロです。
お次は『エクソシスト』風の悪魔憑依ホラーに早変わり。体を乗っ取られて死んでいくのは、むしろそれを眺める側のほうが嫌かもしれない。
とか思っていたらこの後は、はい、本作のメインディッシュかもしれませんね…お待ちかねの大爆発芸の始まりです。このパートにいたってはもうギャグ同然で、「笑ってください!」とばかりに盛大に吹き飛んでくれます。ちゃんとじわじわ部分的に爆発したり、順番をズラして爆発したり、爆発職人の愛嬌が光りますよ。
この人体爆発は最後でも大活躍しますが、もうずっと爆発だけでもいいんじゃないかってくらいには爆発オチがしっくりくる映画です。
終盤は「ウェンディゴ」の真相も明らかになって、モンスターホラーに突入するのですけど、私は終始「こいつらも全部爆発すればいいのに」と思ってばかりだったので、「私の姉が怪物に…!」という悲壮感に浸るタイミングを逃してしまったかもしれない…。
映画化されたことで実質的に本作は死亡シーン集みたいになり(映画内で本当に自分たちの死亡動画を見るのですが…)、余計に振り切った構成の印象が増した気がします。
でもちゃんと死ぬたびに各人物の見た目がどんどんボロボロになっていくなど、細部の演出の丁寧さはありましたし、やっぱり“デヴィッド・F・サンドバーグ”監督はこういうややユーモアに傾いたホラーの魅せ方もノリノリで練ってくれるので、結果的には(ろくに解決していないわりには)楽しいホラー映画だったと思います。
ホラー映画にする意味
ゲームを未プレイの人にも映画『アンティル・ドーン』を観るだけで伝わったと思いますが、この作品はいろいろなホラー映画のパロディで成り立っており、それを自分で体験できることに醍醐味があります。
ただ、ここで問題点が浮上し、もともとのゲームの前提は「ホラー映画を自分で操作して楽しむ」というコンセプトがあり、とてもインタラクティブな体験に変換してくれているんですね。
それが映画化されてしまうと、「ホラー映画を自分で操作して楽しむ」という重要な前提が消えてしまうわけです。単なるホラー映画になってしまう…観ることしかできないホラー映画に…。
となると、観客はプレイヤーではなく傍観者です。「どうやったら死を回避できるだろうか?」と自分の頭を駆使して試行錯誤する必要もありません。映画なのでゲームオーバーもなければ、完全クリアのために隅々までやりつくそうという執念も生まれません。
だとすれば、この映画『アンティル・ドーン』の面白さはどこにあるのかな…という…。
そう考えてしまうと、やはりこの結論に行きついてしまうわけですよ。
この映画はあくまで「ゲームを売るため」のカネのかかった宣伝動画なんだ、と。俳優を使って、ハリウッド監督も起用して、ゲームのプロモーション映像を作っているだけなんじゃないか、と。
ゲームの映像化は最近は大成功をおさめるものも珍しくないですが、非常に産業複合的な儲けに帰結しやすいです。ましてやこの『アンティル・ドーン』はゲーム会社がプロダクションになっているわけですし…露骨です。
ホラーゲームの歴史を振り返ると、ゲーム自体が後発のメディアだったこともあり、映画を追いかけるような図式が目立っていたと思います。「映画っぽい演出をゲームに取り入れよう」とか「あの映画のオマージュで作品を構築しよう」とか。
しかし、現在は距離のあったゲーム産業と映画産業の差が無くなりつつあり、ある種の融合が進んでいるのかもしれません。それもクリエイティブな面ではなく、各社の提携的な意味で…。それはゲームはゲーム、映画は映画…というようなメディアの独自の個性を失ってしまうものなのか、それとも上手くバランスを掴んで全く新しい体験を生み出せるものなのか…。
ちょっと現時点ではそれは不確かすぎるところがあるなと日々感じています。
少なくとも現状はゲーム産業は高コスト化が深刻になり、マネタイズのためにIPを映画産業に売ってそこでも収益をだすしかないという厳しい現実があるので、あまり理想論を語れる余裕もないのですけどね…。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
作品ポスター・画像 (C)Sony アンティルドーン
以上、『アンティル・ドーン』の感想でした。
Until Dawn (2025) [Japanese Review] 『アンティル・ドーン』考察・評価レビュー
#アメリカ映画2025年 #デヴィッドFサンドバーグ #エラルービン #マイケルチミノ #スラッシャー #サバイバルミステリー #タイムループ