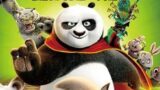ワイルドロボットは自分を見つける…映画『野生の島のロズ』の感想&考察です。前半パートはネタバレなし、後半パートからネタバレありの構成です。
製作国:アメリカ(2024年)
日本公開日:2025年2月7日
監督:クリス・サンダース
やせいのしまのろず

『野生の島のロズ』物語 簡単紹介
『野生の島のロズ』感想(ネタバレなし)
これだからロボット映画は大好きです
「ロボット」という言葉が最初に生み出されたのは、チェコの作家である“カレル・チャペック”が1920年に発表した戯曲『R.U.R.』だと言われています。
この「R.U.R.」は「Rossumovi univerzální roboti」の略で、「ロッサム万能ロボット会社」がロボットを販売しているという世界観です。この作品におけるロボットは化学的な製作でボディが作られており、メカメカしくはないのですが、プログラムで動く人型のロボットで、人間よりもはるかに従順な労働の役割を担います。
今から100年以上前の作品においても、「ロボットに人権はあるか」…つまり、ロボットはいかにして人間らしさを獲得し、人間と区別されうるのか(もしくはされないのか)というテーマを追求しています。そのテーマは現在にもいろいろな作品で受け継がれて見られます。漫画やアニメの『PLUTO』、ゲームの『Detroit: Become Human』など、挙げだすとキリがないです。
私はロボットものだと、ロボットが他者と触れ合って交流する温かいホープパンクが好物なんですよね。『フィンチ』とか、『ベイマックス』とか、最近だと『ロボット・ドリームズ』もそのカテゴリです。


さらにその中でも大好きなのはロボットが人間ではない生き物と触れ合うタイプ。ロボットが植物を世話する系だと、『サイレント・ランニング』や『ウォーリー』などですね。
今回紹介する映画は、ロボットが動物を世話する系の大傑作として語り継がれていくでしょう。
それが本作『野生の島のロズ』です。
原題は「The Wild Robot」で、2016年にイラストレーター作家の“ピーター・ブラウン”が書いた児童書が原作になっています。
それをアニメーション映画化したのが、「ドリームワークス」であり、監督はあの“クリス・サンダース”です。2002年に『リロ・アンド・スティッチ』で監督として才能を発揮し、2010年の『ヒックとドラゴン』が大評判となりました。その後、2020年に『野性の呼び声』で実写の監督にも挑戦しましたが、またドリームワークスに戻ってきたのがこの『野生の島のロズ』。
そして…やってくれましたよ…。『ヒックとドラゴン』のあの興奮が蘇る体験を新しいかたちで届けてくれました。『ヒックとドラゴン』は人間とドラゴンの友情をダイナミックな映像&物語で映像化したエモーショナルな作品でしたが、『野生の島のロズ』はそれをロボットと野生動物の組み合わせで実践。これは私には好きすぎるやつです。ええ、最高です。ありがとうございます…本当にありがとうございました…。
人間はほとんど登場せず、基本的に喋る動物たちの大自然の世界が舞台になっており、『バンビ』と『ベイマックス』を合わせた感じですかね。
野生動物しかいない島に流れ着いたロボットが、動物に囲まれて暮らしながら、小さなある動物を育てることになる…。シンプルなストーリーですが心を打ちます。子どもはもちろん大人も感動できる大作です。
オリジナルの英語の声を担当しているのは、主人公のロボットを『ブラックパンサー』シリーズの“ルピタ・ニョンゴ”、キツネを『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』の”ペドロ・パスカル”、鳥の雛を ドラマ『HEARTSTOPPER ハートストッパー』の“キット・コナー”…とそんな顔触れ。私の好きな人ばかりで耳が幸せ…。
近年のドリームワークス・アニメーション映画は、日本では『カンフー・パンダ4』ですらも劇場未公開になってしまうありさまでしたが、今回の『野生の島のロズ』はなぜか劇場公開されました。良かったけど…。
スクリーンの大画面で映像を思う存分に味わってください。あなたもあの大自然の生き物の一部になった気分で…。そうですね、ハエとかになれば、邪魔もせずに傍にいられますよ。
『野生の島のロズ』を観る前のQ&A
鑑賞の案内チェック
| 基本 | — |
| キッズ | 子どもでも安心して楽しく観れます。 |
『野生の島のロズ』感想/考察(ネタバレあり)
あらすじ(前半)
とある島の海岸に流れ着いた大きな箱。その中には1対のロボットが梱包されていました。嵐に巻き込まれてユニバーサル・ダイナミクスの貨物船から落下したもので、「ROZZUMユニット」と製品名がふられています。
この島には人間はいません。住んでいるのはさまざまな野生生物のみ。今も中型の哺乳類が興味津々でまわりに寄ってきました。そのとき、動物によって偶然にロボットが起動してしまいます。いろいろな国の言語で挨拶をしながら、「ご購入ありがとうございます」と起動メッセージを発するロボット。
「私はユニバーサル・ダイナミクスのROZZUM7134。どんな仕事も完璧にこなします。何でもお申し付けください」
しかし、突然の大波で吹き飛ばされます。さらに巨大な波の接近を感知。近くにいた蟹の動きを参考に切り立った崖を登って避難します。
目の前にあったのは鬱蒼とした森です。ロボットは気ままに自身の役割をアナウンスしながら森を闊歩し、手当たり次第に見かけた野生動物に声をかけます。しかし、警戒されるだけです。頑張っても相手にされません。そこで学習モードに移行し、その場でひたすらじっと動かなくなります。
こうしてロボットは動物の言葉を理解できるようになりました。あらためて起動し直し、自分を盛大にアピール。でも「怪物だ!」と怖がられるだけ。
運搬の失敗だと認識し、出荷工場に戻るために位置情報を伝えようとしますが、雷の直撃で故障します。さらにアライグマに体中をいじくりまわされ、送信機を奪われます。続いて獰猛な熊に追いかけられる始末。急斜面を滑落し、なんとか引っかかって助かりました。
ところが、自分は何かを下敷きにしたことに気づきます。そばにあるのは鳥の死体。その巣の中には粉々の卵。でも奥に1個だけ無事な卵を見つけました。
その卵を興味深そうに手で持って見つめていると、今度はキツネに卵を盗られます。取り合いをしつつ、なんとか卵を確保。すると孵化しました。
雛はロボットを親として認識しますが、ロボットはあくまで顧客としてしかみなしていません。 送信機は雛のくちばしのひと突きで破損。
自分では何をすればいいのかわからないので、近くにいた子連れのオポッサムに雛を預けます。この母親のオポッサムは見かねて子育てを教えてくれます。
なんでもこの雛は鳥なので「食べる」「泳ぐ」「飛ぶ」…この3つを教えて育てればいいらしいです。そのような業務は未知でしたが、ロボットは自分なりに思考して試してみます。しかし、何を食べさせればいいのかも不明です。
こうして初めての仕事に手探りでとりかかることに…。
「名付ける」ことの生存上の価値
『野生の島のロズ』は島漂流モノの出だしです。そして孤立した唯一無二の存在がその現地の環境の先住者である野生動物に囲まれて暮らしていく物語でもあり、例を挙げるなら『ジャングル・ブック』に近い構造でしょう。『野生の島のロズ』の舞台は、登場する野生動物の種類を観察するとどうやら北アメリカのどこかっぽいですが…。
ただ、『野生の島のロズ』はその主人公が非生物のロボットであり、同時に自分以外の孤立した小さな存在を育てることになります。異なる孤立した者同士の支え合いが描かれるわけです。
私は本作は「ロボットが母性に目覚める」というよりは「個がアイデンティティを獲得する」までを描いた物語なのだと思いました。
そもそも物語の序盤では野生動物がやたらといっぱいでてきますが、その動物たちに個性はなく、背景的な「動物」にすぎません。しかし、ロボットのロズが「学習」することで、動物の言葉を認識し、そこで初めてこれら動物たちにも個性があり、名があり、つまりアイデンティティがあるのだと理解します。
それは同時にロボットのロズもそうで、当初は製品名しかないので、製品番号で自身を識別して表します。でもこの世界ではそれはあまりに意味がなく、そこで「ロズ」という名前を用いるようになります。ここでアイデンティティが芽生えます。
さらに孤独な卵から孵化した雛に「キラリ」(これは日本語版の名前で、オリジナルの英語版だと「ブライトビル」)とも名付け、アイデンティティを与えます。「食べる」「泳ぐ」「飛ぶ」を教える以前にこの「名付ける」というステップこそ、ものすごく大切で、本作の根幹のエッセンスになっていると感じました。
初期のロズも考えていたように、別に名前なんてなんの価値があるのだという意見も当然あります。それ自体が生存に直結して有利に働くわけでもないです。理屈だけで考えると無意味だと考えてしまうのも無理はありません。
しかし、名前は全ての土台になるものである、と。その名前を原点にして、「キラリを育てるロズ」という帰属意識が育ち、「多種多様な野生動物に囲まれて生きるロズ」というさらにスケールを広げた帰属意識が育つ。
それはロズにとどまらず、終盤はロズとキツネのチャッカリ(英語版だと「フィンク」)の作った「家」の中で、たくさんの野生動物が集まり、種の本能的な衝動を超えて、他者を尊重する心を発揮します。これもまた他者のアイデンティティを認識したからこそできる所業です。
この終盤の平和的な描写は、当然ながら本来の野生下ではあり得ません。非常に私たち人間向けの教訓的な展開といえるでしょう。原作は子どものための童話としての味わいが主ですから、これでいいのかもしれません。
けれども本作がそこまで理想的すぎるとも感じないのは、ずっと序盤から生死を描くことにも専念していたからなのかな、と。ロズでさえ偶発的とは言え、キラリの親や他の卵を殺めてしまっており、それは無視できぬ事実。アイデンティティを認識すればするほどにその事実の残酷さが際立ちます。
終盤ではさらに渡りをしていたキラリ含むカナダガンの群れが、近未来的な施設の農地に迷い込み、そこでロズと同企業のロボットに「害獣」として敵認定され、攻撃される展開を描くことで、アイデンティティの無視が生命を脅かすことにも繋がることを示します。
やはりアイデンティティは軽視されがちですけども生存の要なんですよね。自己満足ではありません。
ラストは一見すると脱個性へと戻ってしまったかのように見える中での「ロズ」というアイデンティティの表明が繰り返される、とても一貫したテーマ性をみせる綺麗な結末でした。
ユーモアとダイナミックな映像だけで
『野生の島のロズ』はそんな深遠なテーマも読み解けますが、感触としては敷居の低いエンターテインメントで、楽しさ満点です。
序盤の、ビジネス口調でタスク遂行だけに集中するあまり、野生動物たちに半ばサービスという名のハラスメントを連発しまくるロズもユーモラスで笑えます。キツネのチャッカリに騙されていく姿も滑稽です。
一方で、雛のキラリを世話する中で、子育ての苦労を身をもって味わったり、ロズが観客にとってどんどん共感できるキャラクターとして魅力的になっていく展開の積み重ねも良かったです。
中盤では育児への自信を失い、己とは何なのかを他のロボットを手がかりに模索する。これもまた、育児に限らずともよくありがちな振る舞いで…。
そして育児に舞い戻り、いよいよ飛ぶシーン。ここはさすがの“クリス・サンダース”監督。エモーショナルな映像を作るのが抜群に上手いです。今作では渡りでの別れも加わり、ますます感情を揺れ動かされますし、あの一瞬のロズの挙動もグっときますね。
鳥の渡りを描くCGアニメーション映画と言えば、つい最近も『FLY! フライ!』があったのですけど、撮り方が全然違いました。
『野生の島のロズ』はより自然的なダイナミックな撮影でアプローチしていましたから。あのブワーっと鳥の群れが飛び立つ圧巻の光景の中にロズが手を広げて走っている…あれは鳥肌の立つ名シーンですよ。アニメーションでこれを観られるのがたまらない…。
個人的には私はロボットが好きなので、終盤で実質的には「敵」側として出現するヴォントラなどの他のロボットたちにもエピソードがあってほしいところではありましたが、まあ、それは次回作に持ちこしということで。
シネマンドレイクの個人的評価
LGBTQレプリゼンテーション評価
–(未評価)
関連作品紹介
ドリームワークス・アニメーションの映画の感想記事です。
・『ルビー・ギルマン、ティーンエイジ・クラーケン』
・『長ぐつをはいたネコと9つの命』
・『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』
作品ポスター・画像 (C)2024 DREAMWORKS ANIMATION LLC. ワイルド・ロボット
以上、『野生の島のロズ』の感想でした。
The Wild Robot (2024) [Japanese Review] 『野生の島のロズ』考察・評価レビュー
#アメリカ映画2024年 #ドリームワークスアニメ #ロボット #鳥 #キツネ #楽しい #アカデミー賞長編アニメ映画賞ノミネート